”B・Thomson指揮のCDを中心とした、”
◇◇ 協奏曲について、(ピアノ)page Ⅱ ◇◇
※ ・・・ラフマニノフ・フンメル・ハーティー・ヴォーン ウィリアムス
& ブラームス・サン サーンス etc ・・・
『 Rachmaninov Comp. Piano Concertos :
Shelley, Thomson / Scottish National. O 』
『 Vaughan Williams :
Piano Concerto /THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA』
(pf)ハワード・シェリー
〈 前のページより、続く 〉
ところが2番の場合、序奏部分は、和声的にシンボリックで、旋律的には 別個の”門
構え”といったもので、結果的にその部分だけを見れば、続く部分と断裂したものだが
、1番の場合は、そのようなものでなく、その続く旋律的部分と同等な感じで、あとの
展開部、再現部以下というような部分でも、この断裂自体が、重要な要素になる。
序奏の厳しい半音的下降音階は、ピアノが主として弾き、続く哀しげな旋律は弦楽合奏  が主。それをピアノが引き継ぐが、すぐに落ち着きのない気まぐれなピアノの走句部分
になったりしたあと、一応、第2主題の夢見る様な部分に移り、そこではピアノとオケ
が融和的な雰囲気醸し出すが、そこに断裂的な荒々しい序奏の主題が、また オケで来
る。・・・こういった唐突な呈示部の曲の進行が、再現部、カディンツアでも、少し要約
され、楽器の役割を変えるくらいで、ほぼ同じまま出てくる。
序奏的下降要素がピアノで奏された後、再現では、呈示部と反対にピアノで哀しげな旋
律を弾き出し、また、経過的な落ち着き無いピアノがあって、夢見る風の融和的部分が
ピアノとオケのソリスト的扱いで再現される。そこにまた、極端に対比的な荒々しい序
奏部分の音楽でもって、オケが断ち切って直ぐカデンツァに移る。
この独奏ピアノの部分でも、序奏にあった重厚なピアノの和音の響きを威圧的にならし
たあと、同じ序奏部分の下降的音階をより派手にやったあと、ゆっくりした第2主題的
な夢見る部分をやり、それが力強く発展して、哀しげだった冒頭での弦楽の第1主題の
旋律を、ピアノだけで、フルに壮大化させて、この1楽章の結論的に再登場させる。
そのあと、ヴィヴァーチェのコーダが、オーケストラでつむじ風のように始まり、この
やはり序奏の速い部分と関係のある音楽に誘われるようにして、ソロのピアノは第1主
題の旋律を捨て、断ち切って、飛んでいくように終わる。(楽長クライスラー的ロマン
主義的終わり方??)
だから、この1楽章の音楽は、後半、終盤においても、始めの呈示部分の序奏と第1主
が主。それをピアノが引き継ぐが、すぐに落ち着きのない気まぐれなピアノの走句部分
になったりしたあと、一応、第2主題の夢見る様な部分に移り、そこではピアノとオケ
が融和的な雰囲気醸し出すが、そこに断裂的な荒々しい序奏の主題が、また オケで来
る。・・・こういった唐突な呈示部の曲の進行が、再現部、カディンツアでも、少し要約
され、楽器の役割を変えるくらいで、ほぼ同じまま出てくる。
序奏的下降要素がピアノで奏された後、再現では、呈示部と反対にピアノで哀しげな旋
律を弾き出し、また、経過的な落ち着き無いピアノがあって、夢見る風の融和的部分が
ピアノとオケのソリスト的扱いで再現される。そこにまた、極端に対比的な荒々しい序
奏部分の音楽でもって、オケが断ち切って直ぐカデンツァに移る。
この独奏ピアノの部分でも、序奏にあった重厚なピアノの和音の響きを威圧的にならし
たあと、同じ序奏部分の下降的音階をより派手にやったあと、ゆっくりした第2主題的
な夢見る部分をやり、それが力強く発展して、哀しげだった冒頭での弦楽の第1主題の
旋律を、ピアノだけで、フルに壮大化させて、この1楽章の結論的に再登場させる。
そのあと、ヴィヴァーチェのコーダが、オーケストラでつむじ風のように始まり、この
やはり序奏の速い部分と関係のある音楽に誘われるようにして、ソロのピアノは第1主
題の旋律を捨て、断ち切って、飛んでいくように終わる。(楽長クライスラー的ロマン
主義的終わり方??)
だから、この1楽章の音楽は、後半、終盤においても、始めの呈示部分の序奏と第1主  題に続く部分との、極端な対比は、何か別のものに融合、発展したりなどせず、単に順
序を変えたり、楽器を変えているだけで、むしろ、よりはっきりバラバラなままなのを
強調して、終わるのである。
もちろん、その前に今、書かなかった展開部にあたる部分がどうかということが、ここ
で問題になる訳だが、第2、3協奏曲の1楽章のような大きな扇状の流れを持とうとす
るのと、程遠い、薄い扱いで、1番の1楽章全体では、一定の情緒を連続的に増大、発
展させる部分が、大してなく、情緒的な連続感の無いバラバラな情緒の部分が、とても
目立つことになる。
2番の1楽章なら、展開部といえるところになって、ピウ・ヴィヴォでピアノが参加し
てくる部分は、第1主題の頭から、いえるものが右手で、第2主題が左手というカンジ
で、1番の展開部の部分もそれに近いやり方をもつが、以降も含め、それ以上に主題の
綜合的扱いが行われ、また、ここは線的動きの複雑さをもった部分でもある。この入り
組んだせわしい小さな動きが、ピウ・ヴィヴォの2分音符の80の指示のある頃から、
解きほぐれるように、同じ旋律を持ちながら拡がっていき、だんだん速くポコ・アッチ
ェランドで、オケに第2主題のはっきり出る状態で、それが両手の流れるような動きに
まで変化する。そこに両手の重厚な和音でロシアの土俗的な力みたいな新しい主題みた
いな部分がアッチェランドで加わってくるが、再現部で第1主題がオケで奏される部分
にも連続する調子のところでもあり、またそれらの主題に和声的に関連して作られてい
る、そのパワフルなカンジのものに、流れが移る。そして、ピアノで”鐘”の上昇的音
が鳴り、土俗的ピアノの音楽が豪快に第1主題を連れてきて、その主題がメノ・モッソ
へ連続して流れ込み、そこでピアノのソロのアルペジオの音楽による、ロシア風哀愁の
部分に変わり、だんだん緩やかになり、音楽の”エネルギー”も終わりに向けて、明瞭
に落ち着いたもの下っていく。
こういった展開部からの流れは、類似性のある主題や、その部分的要素を、つなげていっ
たもので、主要な流れが出来ているし、それが速度が速まっていったり、音程差が拡がっ
たり、厚く重ねられた和音の激しい動きになったりまでする事で、よく似た情緒が拡大、
興奮的強い信念へ変化し、また落ち着いていく情緒の扇状の発展パターンの典型的なもの
で、1楽章全体を見ても、第1主題の旋律的だが重々しく暗い感じでピアノのアルペジオ
の波のうねりで始まり、第2主題はほっとする明るさもあるが、似た長いロシア的メロデ
ィーで、情緒はとても連続していて、連続する影と光の表情の反映そのもので、つなぎの
部分のウン・ポコ・ピウモッソの部分なども、一見違った音楽の闖入風だが、似た素材で
ムードの流れを壊さない、蔓草模様の装飾的つなぎになっている。
これに対して、1番の1楽章は、2つの主題のつなぎといえる部分も、気散じ的に動き回
るようなものだし、また、全体の4部分位の各部をつなぐような序奏部分の半音階的要素
も無機的に、情緒の連続を切り裂くし、何より、肝心の展開部が如何にもウェイトが措か
れていない書かれ方で、2番のような念の入った連続した展開はないし、再現部の盛り上
がりに上手くつながるような書かれ方はされず、オケだけでファンファーレの頂点部分を
作るし、後半部分のピアノの入る部分と完全に分裂していて、この楽章中、結局、類似性
のある情緒の発展的部分は、大きな構造を成さない。だから、この1楽章全体に、前に述
べた対比的情緒の奇矯な強力さは、それに勝る大きな構造がないので、全体の何か、一見
すると、”唐突”なような印象をそのまま作り出しているともいえる。
2番だけでなく、3番の1楽章も、もっとも単純で素朴なロマンティックな歌の呈示に始
まり、(2番の2楽章の途中のピアノの扱いを移してきたようでもある。)そのメロディ
ーが、オケの弦に移り、ピアノが走句で装飾するようになり、その動きが自然で延長的な
ものだが、経過部分の複雑なものに一旦なる。その豊かな装飾が小さなカデンツアになり、
また、その後の、濃密な情緒のアラガラントなどテンポの揺れをもつオケだけの音楽の小
さなつなぎの部分も、全く最初のテーマから類縁性のあるもので、ごく自然な情緒で連続
するし、次の第2主題の呈示も、押し流すながれから、一旦 身を離した気楽なリズムで
また、トーンも少し光の射し込んだ感じの簡明さから、独奏ピアノのショパンのノクター
ン風な伴奏音形を繰り返す優しげな格好で、始まるが、その動きが再び速く、大きく、激
しくなっていく。ピアノの左手の下降音や分厚い和音が、走句に変わって流れたあと、テ
ンポ・プリモで、再び 最初の第1主題がほぼそのままの格好で戻ってきた後、直ぐ音楽
はピウ・モッソで、ピアノの羽ばたくような動きになり、そこで1楽章の頂点の状態の大
きな準備みたいになり、例のピウ・ヴィーヴォのスクリャービンのエチュードみたいな部
分があって、オーケストラとピアノが打ち合うfffにまで、速度と音量、複雑さは増して
行く。そのあと音楽は目に見えて緩やかな揺らぐような動きになり、長い激しく複雑な
カディンツアを挟むが、再現部は非常にあっさりと短くそのまま弱まって終わる。
だから、3番の1楽章全体の流れは、単純な指一本的メロディーが、だんだん複雑的密な
状態に増大し、一旦優しい第2主題のトーンに移ってまた増大化、さらに展開部で第1主
題が戻ったのち頂点的増大化し、あとはカディンツアを除くと弱まり、収まっていく大き
な凸的流れがある。
3段階みたいな感じで、類似した情緒が、音構造の速度と音量、複雑さの増大で連続的に
拡大し、興奮的強い信念へ変化し、また落ち着いていく訳で、2番とやはり共通する情緒
の扇状の発展パターンなのだが、2番の方は、寄り集まる線の動きの変化に、もっと依存
しているが、3番の方は、より、単純から複雑への”物量的”なものに依存している。
とはいえ、2番3番は、共に大きな類似した連続する情緒の構造部分を中心にしているの
は、明白で、それに対して1番の1楽章は、これまで描写してきたように、呈示部、再現
部、カディンツアでも、そういうものはないし、反するものが狙われている。そして、全
体のまとまりの必要性から、そういうものがあってよいはずの展開部でも、集中感には遠
く、前半のオケだけの部分と後半が分かれているくらいなのである。
しかし、詳しく見ると、1番の展開部にあたる部分は、先程の呈示的部分の終わりのヴィ
ヴァーチェのフレーズからは、そのフレーズが一通り言い終わった後、オーケストラだけ
の部分となり、第1主題の始めと関係する音形が繰り返し、激しくなって展開されるのだ
が、ここでは、実は2番の展開部とよく似たやり方で、序奏の要素も重ねられている。さ
らに、その第1主題と関係する音形の発展部分が このソナタ形式風の構造の頂点を作り
るのだが、そこで目印のようにファンファーレが、今度はFで鳴る。そして、それは1楽
章冒頭のファンファーレに対応するものなのである。そのあと、後半部分が、続き、ホル
ンのソロで第1主題を優しく鳴らし、ピアノを加えて慰撫する調子になるが、ぐるぐる速
くなる感じで激しくなって、また、序奏の要素が現れ、ピアノで第1主題からの、先に呈
示されたのとほぼ似た音楽の再現部分とつながる。
後半部分でソロのホルンが奏す第1主題は、遠くで鳴っているように響き、その周辺で戯
れ、彷徨うようなピアノの動きがあって、その前のオーケストラ部分だけの突き進むよう
な前半部分の最後のファンファーレが、正に1楽章の折り返し地点であり、展開部全体の
パースペクティブが、”ある遠いところ”にもっていかれている重要なことにも気付くと
、2番の展開部と似た扱いも含めて、2番3番のような連続的な大きな構造が作れなかっ
た、というのでなく、そのような連続性をパースペクティブの”一部分”として、意図的
に簡素化して置かれていると見ることが出来るのである。
確かに、このような各部分バラバラなムードの作曲作品は、十分、自らの楽想を大曲でコ
ントロールできない作曲技術の未熟さと一脈通ずるところがあると考えられ、実際、この
1番の原初的なもとの格好は、ある程度、そのような傾向があったのでないかとは想像し
うる。しかし、現行の1番は、そのようなもの単純なものでなく、多分、それを元にして
はいるが、意図的に構成され、むしろ、2番3番的な構成を、部分として包含するみたい
なものでもある。
未熟さ、みたいに見える一番の協奏曲としての問題は、展開部が薄い感じがし、大きな連
続感を感じさせる構造が乏しいというのが、やはり理由みたいになって、カディンツァぐ
らいの部分が、目立ちすぎ、ソロが、今まであった全てを一人でカバーするみたいなこと
になり、その前の協奏曲の構造の主たる全体を、1人で凌駕しよう、としていることにな
り、あるイミ、協奏曲の構成の必然性をここで、自ら否定してしまうことなのではある。
そしてまた、同時に そのように一見あえて、自らの存在を不確かなものにしてしまいそ
うでいて、ホロビッツが「・・・とても好きだ。・・」と言っていたように、曲になじんでくる
と2、3番以上に”不思議で謎めいた魅力”を感じる曲であるのも本当なのである。
もちろん、カディンツァが、その楽章を聴くとき、一番聞き所で山場だと云うことはあり
うる。モーツアルトにとってピアノ協奏曲は、重要なジャンルで、しかし、それでもその
ソナタ形式の前の部分全体がガッチリした建築として存在していて、華やかで自由なカデ
ンツァがあるので、最後は肝心の最も重要なテーマをオケと一緒に奏したりもするのであ
る。だから、やはり、ラフマニノフの1番の積極的につなでいくようなムードのない曲の
流れは、非常に例外的なものといったほうが、いいと思う。(全く、古典の曲の作り方を
無視する場合や、また、作品として問題なく?価値が低い場合を、除くと・・・)
といっても、1番の1楽章をつないでいる大きな構造といえるものがある。それは、ソリ
ストが、全てを引き受けてしまうという成り行きで、呈示部で、激しい序奏をピアノが受
け持ち、優しい第一主題をオケで始め、再現部で逆に序奏をオケで、第一主題をピアノで
持ち替え、綜合するようにカディンツアでピアノが全部一人でやってしまうということ。
極端な名人が、相対立し、融合しないものを強力な名人芸で一つにしてしまう。
結局のところ、これはヴィルトージティーの音楽で、ただ2番3番が、ヴィルテュオーソ
的存在が、”自ら働きかけるもの”としての、意識的発展的な情緒のつながりの音楽であ
ったのに対して、1番は、むしろ”ヴィルトオジティー自体の音楽”と呼べるような、自
らの働きかけに応じない様相も含めた意識の限界の織りなす”遍歴”の情緒の流れで、そ
のイミで、意識外の関連まで問題にしているのだし、また 主体的な意識を離れたヴィル
ティオーソ的存在の持つ”気まぐれ”でもある。
ニーチェのツァラトウストラが、落ちてしまった”綱渡り師”に対して、ニーチェ的でな
いような共感を、ちらりと示すところがあるが、最終的に「徳」virtueを表現するものを
”理想”とするとはいえ、個人の”技”を、何であろうと極めようとする名人芸には、人
々に直接非常に訴えかける、ある種の輝かしさと、一瞬一瞬の不安定さ、一貫しない気ま
ぐれの上に成り立ったものというところがある。
ホロヴィッツは、先の引用したインタビューの中で、”1番は、大変好きだ。余りやられ
ないが・・・”と答えていたわけだが、ホロヴィッツ自身の第1番の演奏の録音は、若い時
のものも、残されていないようで、代わりに?、バイロン・ジャニスの演奏の方は、優れ
た腕前の録音を聴くことはできる。
バイロン・ジャニスの演奏は、”無関心”なまでに、さらさらと全体を弾き通す”クール”
さと、冒頭部分、カディンツアなどの冴えた音の技の”切れ味”みたいなものに伴う強い
情緒の対照など、この曲の”気まぐれ”な輝きを生む一連の流れに、この人の個性が、重
なり合った説得力になっている。 (2003/4/5)
バイロン・ジャニスの演奏の特徴は、判りやすい例でいえば、ラフマニノフの例の前奏曲
嬰ハ短調などの録音を聴いてみれば、独特の揺らぐようなテンポを取っていることが判る。
厚く両手で重ねた和音の連続だけ位で出来ている、この最初期の曲は、ほぼ三部形式で、
コーダが付いたものだが、もう代表作の手法と殆ど同じものがちゃんとある。
コーダの重厚に重ねられた殆ど同じ和音の柱の連続に、右手だとA・G#・A・A#・A・G#
みたいに半音的に動くラインで、怪奇趣味調の変化和音を綴っていくやり方は、第2協奏
曲と全く同じといっていいくらいだし、その2楽章の冒頭もそのヴァリエーションで、ラ
フマニノフのトレードマークに近いものだし、半音づつ降下して中間部の3連符の回転す
るような動きのあとfffから両手で、和音を交叉させて打ち鳴らすように降りてくるとこ
ろも、第2協奏曲の終わり、第1協奏曲の終わりのみならず、ラフマニノフの好む手法に
なる。
この曲は、再現的部分で4段譜になったりするくらいで、ピアノで最大限に分厚い和音を
作ろうとするため、バスを鳴らしたまま飛び離れた和音を鳴らしたりしなければならない
ところが、多いからテンポの作り方が通常より問題になる曲だが、バイロン・ジャニスの
演奏だと、それほど力強い感じでもないが、鮮やかな感じと共に、この人のテンポが特に
掴みづらく、ふらふらする感じが目立ってくる。ワイセンベルクにも、この曲の録音はあ
るが、比較すれば、始めからずっと安定した感じでテンポがとれるし、中間部のアジター
トの指示のあるところは、ピアノ協奏曲の箇所のところの様にアッチェランドしているが、
そのような感覚が保たれ速くなるので、変化も安定して聞こえる。バイロン・ジャニスの
場合、そういう安定感とは遠いし、何かふわふわしたテンポ感覚を作り出すのが、本質的
に必要なことで、むしろ、そうであるからこそ、その少し船酔いしたような気分の中で、
独特のピアノの音の輝きが生きるということがあり、このことは又ホロヴィッツの場合も
、ほぼ似たようなことがある。
この前奏曲が、ラフマニノフの全作品の中で示すものと、ちょうど同じ様な関係で、スク
リャービンの場合、最初期のエチュード作品2の1(1887)があり、この2曲は、両方の
作曲家の特徴を、不思議なほど対照して見せてくれている。 (2003/4/8)
ラフマニノフの嬰ハ短調のほうは、単調なまでにガッチリした素材を、それを一定に変形
させ、また出来る限り壮大な音構造に、如何にも建築的に組立ることによって成り立って
いるのに対し スクリャービンの嬰ハ短調のほうは、一方でずっと和音を刻み続け、その
上にショパンの風の、しかし、もっと濃厚な風味の旋律を歌わすことで出来ている音楽。
中間部分は短く 簡単な長調部分。そのあと始めの旋律が戻ってくるが、デリケートな対
旋律が加わってくるし、また全体的にショパンより線的動きが、常に復綜的に考えられる。
スクリャービンの歌わせる音楽の、デリケートで濃密な語り口を作るのは、多分に言語的
な詩的想像力によっているのでないかと、受け取るのは無理のない考えである。
「・・・何ものかが、かすかに光り脈動を始めた。・・・・それは、揺れ動き、光ったが複数
でなく一つだった。・・・それは意識の出発点の混沌でもない。全歴史、全将来、永遠
が、その中にあり、全要素が混ぜ合わせられているが、そこには存在可能性の全てが
ある。・・・それは、色彩、感情、夢など、を滲み出させる。・・・過去と未来の瞬間は、
同時に到来する。予感と回想。恐怖と歓喜の錯綜。・・・」
「・・・私は、咲き盛る花であり、私は至福だ。全てを燃やす熱情で、全てを飲む宇宙を覆
う炎だ。混沌に帰すための、私は、解放された盲目の力だ。私は眠れる創造、抑えられ
た英知だ。・・・」(以上、本文の参考のため、短くして、適宜に要約したもの。)
cf T・S・エリオット
というのは、スクリャービンのメモにある、彼自身の言葉なのだが、従来、こういうスク
リャービンの言葉は、晩年の大規模な音楽と色光を結びつけ、また匂いまで加えようとし
た奇矯な”総合芸術”の計画や、私生活のスキャンダルの方向で、もっぱら奇妙な作曲家
のナンセンスな文句のように受け取られている。しかし、また
「音楽だけを書くという方法が、私には解らなくなった。・・・音楽とは、確かに、それが
世界的見地の全体の計画の中の単一の計画と関連して、はじめて理想と意義を持ちうる
ものだ・・・」
という友人に宛てた手紙の中の言葉といわれる、この文句も、例によって、その後の”総
合芸術”の計画という類いの話しだけに結びつけて考えるのは、短絡的でないのか?
むしろ、スクリャービンの音楽の考えの中には、後年にこの発想が、露骨に出てきただけ
で、もともと初期から後年まで通して、この傾向があったことを、見ることの方が重要で
、先程の詩めいたメモの書き付けに描かれたような感覚も、”焔に向かって”というよう
なものに、具体的なくらい、近いことは明かに思えるし、また 初期の前奏曲の中、そし
て作品2の1のエチュードの甘く包み込まれる世界の感覚の中に、ショパンとの違いみた
いなものなど、として、すでにはっきりとある。
『焔に向かって』作品72(1914)を、ホロヴィッツが、自宅で弾いている元々プライベー
トな録画が、残っていて「非常に難しい曲だよ・・・」というように語ってもいたが、実際
私などでも、弾いてみると、譜面の音符が、割と閑散とした状態であることもあり、むし
ろ、いきなり通して弾いても曲にしやすいもので、曲のポイントさえ掴んでいれば、リズ
ムがゴマカシ気味になってしまうのを勘弁してもらうなら、愉しく弾けるし、”効果”も
高い曲だということが解る。
勿論、ホロヴィッツのような立派な音で、鮮明な音の渦を作っていくのは、大変 難しい
だろうが、それ以前に、この曲を、普通の演奏者たちにとって、難しくするのは、この曲
のある種の”単調さ”になる。
この曲は、最初は右の2音、左の2音で、律動のような短い旋律で、神秘感のある4度和
声的響きが、だんだん厚みが増していくかんじで、次のバスがEとGを動かす部分に始まる
、ひらひら動くような部分に移る。それが、中声部の冒頭主題と、アルペジオ、装飾する
音符などが、見事な線的絡み合いを作り出し、続くC#・H・A#・G#の鈴を振るような鐘
の音が、出る部分になり、バスの音がドンドンと鳴ったあと、波のゆれるような、バスが
上下に動く中、タターンと冒頭の旋律が断片的に高音で鳴る部分があり、その動きが静止
的動きに変わった後、延々と F#・B・Eというような音形を打ち鳴らし始め、F#・C・
G#・Bなどといったような組み合わせの鐘の音を、ずっと熱狂的に鳴り響かせ続ける終盤
になる。そこで、最初の旋律の音が、低音部で重厚に奏され、最後に意味深なE・B・G#
・B・E・G#・A#・D#・A#・D#・G#・C#の上向する単音を、各々付点4分音符で響
かせて終わる。
非常に良くできていて、スクリャービンの手法の多彩さが、凝縮しているような曲だが、
それでも似たような音形が、延々続くし、旋律も発展が、指向されている訳でもないから
演奏によっては、随分単調な印象になる。そんな場合、何が欠けているかと云えば、この
曲を、単純な音量増大に近いものと考えて、この曲のバスの入り方、鐘の音の鳴り方、主
題の断片、うねる音のスリルといったものに顕れる我々の”現実”に埋め込まれた情緒の
展開を、曲から読みとった”語り口”に出来ないのである。
もちろん、こういう展開は類似性した情緒の”エネルギーの増大”(フロイトの云うとこ
ろのイミで”エネルギー”と一応考えてもいい)みたいなものである、一方 ”われわれ
の言語”に埋め込まれた各々の情緒で、単なる歓喜への増大では決して無く(そう見れば、
ある種の悪いイミでの”抽象”であろう)むしろ、”歴史感情”を語る、に近いと考えた
ほうが、浅薄な演奏を防いでくれる。
先程のスクリャービンのメモからの引用に在ったような観点で、多彩なピアノの響き、フ
レージングなどを積み重ねて、一つの統一された曲の世界を作っていく。こういった語り
口、こうして読みとって語ること、の配慮無しには、このような曲の演奏は単調で成り立
たないものになる。
スクリャービンも、ラフマニノフ同様、非常に優れたピアノ演奏家だったと云われている。
ただし、非常に違ったタイプの演奏法で、それは両者の曲作りの違い、とほぼ同じ傾向を
示していたらしく、スクリャービンの追悼演奏会で、ラフマニノフが、スクリャービンの
曲を演奏したとき、余りにもラフマニノフ流の演奏だったので、スクリャービンの友人た
ちは非常に不満を感じたらしい。また、この時 聴いていたプロコフィエフが両者の演奏
を、評した言葉が残っていて、スクリャービンの演奏は「・・全編が、微妙な色合いの魅惑
と暗示に満ちて流れていた・・」一方、ラフマニノフの演奏は「すべての音が、しっかりと
大地に根付いたもの」であったというように云っていたらしい。(この辺りの、引用や逸
話などは、H・ショーンバーグの便利で分かりやすい本からのもの、です。)
スクリャービンとラフマニノフの演奏法の違いは、ここまで書いてきた幾つかのことを踏
まえると、ピアノ演奏のやり方において、現代で、極めて影響の大きい”ロシア型”のピ
アノビルティオーソというものの本質を、典型的な対立したタイプとして、示しているも
のといえるかもしれない。
それは、スクリャービンが、演奏を詩的言葉と(先の引用したメモの文句)関連する多彩な
色合いの表情の流れるような演奏をするのが重要と考えたに対し、ラフマニノフは、むしろ
演奏を、すべての音を均一にちゃんと鳴らし、その上で力強い音楽を構成する(これは、残
っている録音からも分かる。)ことを考えたもの、というような違いになるだろう。(2003/4/11)
こういったことに関して、身近な経験からも、云えることの一つは、スクリャービンの音楽
は、非常に凝った技巧的な音楽という印象が、前面にある割に、そんなにバリバリと、音符
をこなしていくピアニストの能力ばかりを要求するものではないということは、云えるのだ
と思う。例えば、有名な練習曲嬰ニ短調作品8の12など、シャープが、いっぱい付いたり、
相当 ごちゃついた譜面だが、手の動きの流れとして自然で、前半が左手の一定の回転運動
をして、後半が和音連打している間、右手が、オクターヴで旋律を歌うといいうような曲に
なっている。
厚く重なった和音同志が、離れたところに飛んだりする部分があっても、一方が、単純なオ
クターヴだったりするし、最初の方で両手のオクターヴの練習曲みたいなところに、11度と
か12度なども要所に挟まっていたりする訳だが、実際の演奏を聞く側にすれば、高い方の音
が抜けたり、単純なオクターヴになっていても、大雑把にいえば、場合によっては、そんな
に目立たなかったりする。また、そんなバスの動きから、ややこしいところに飛んだ音が譜
面に書かれているが、それも結構、同様だったりする。
もちろん、こんな言い方は、極端なものでしかないけれど、あるロシア人?のベテラン風の
ピアノ女性教師が、練習曲の作品42の5の演奏で、甘い旋律的なものが、戻ってくるとこ
ろで、内声部のようになる細かく揺れ動いたりする部分を、完全に弾き通す必要はない、み
たいに明言していたし、一方でロシアの学究っぽいピアニストの男性は、スクリャービンに
1音たりともムダな音はないとも云っていたけれど、やっぱり、スクリャービンのピアノ曲
は、その種の傾向があって、ちゃんと弾くのは望ましいけれど、しかし如何に楽譜を”完全
に”弾いたとしても、”語り口”が的外れであれば全然ダメみたいなことはある。曲の一番
大事なところを考えること。そこにどうやってもっていくかを考えること。
演奏会でやるのでなく、「ブラインド・テスト」紛いに聴いてもらうため、練習曲嬰ニ短調
作品8の12や、前奏曲の幾つかを、私が自分で録音して、例えば、アマチュアオーケストラ
でやる”新世界”の1stヴァイオリンのパートを、練習しながら「もう、速すぎて弾けない・
・・」などとこぼしている、うちの母親程度の人の耳(??・・・・・)を相手に”実験”する場
合、細部が少々いい加減なのにも、かかわらず、曲に不向きな場合もある普通のピアニスト
たちの演奏と、並べて聴かせると、結構もっとそれ風に聞こえたり、区別がつかなかったり
する事実は、身近な経験でも確かめうるスクリャービンの音楽のある側面を語ると思う。
※ 誤解の無いように、書き加えておくと、ラフマニノフとスクリャービンといった”ロシア音楽”に詳しい
方は、日本では多分たくさんいらっしゃるわけだし、私などウォルトンやシェーンベルク、ウエーベルン
(これはとても少ないけど・・笑い)の殆どの曲は聴いたことはあるけれど、ラフマニノフのオペラや歌曲
は、全く部分的にしか聴いたこともないし、好きなピアノ曲を弾いたり、聴いたりするくらいなものなわけ
だから、その他、ちゃんと扱うには全く不十分な準備しかしていないというのは、断っておかなければなら
ないと思います。
しかし、ウォルトンやヴォーン ウィリアムスを捉える場合と、似た問題が、ラフマニノフにはやはりあっ
て、そこから見ると非常に重要な言わねばならなかったことがあると考えますし、この文章全体は、そうい
った話題からの脇道程度といえますし、尚更、まず全体の輪郭を見通すことが優先される書き方になってし
まいます。これまでの他のページでも 同様ですけれど、曲の作られ方を、言葉で簡単に説明しようとする
と、書き方の都合で誤解を招きやすい表現になる場合が、どうしても出てくるので、もっとより良い表現に
気がついたら、改めようと考えています。また、メトロノームの数字も、私の手持ちの機械で、計った結果
を参考までに書かせてもらっているので、ミスっていなければ、細かく言えば計る箇所によって、相当安定
したテンポの演奏でも、やはり揺れるので、その構成部分の代表的なテンポと思えるもの、ということにな
ります。
逆に、ラフマニノフの場合などは、そいうふうになりにくく、前奏曲ト短調の作品23の5
など、譜面は、スクリャービンの先の練習曲より、一見易しそうだが、弾いてみると、”不
安定さ”が、あるとずっと粗が目立ちやすい。
そういう具合に、ラフマニノフとスクリャービンの作品の違いは、演奏家として望むものの
典型的違いの傾向に関係しているのであるが、しかし、ラフマニノフとスクリャービン的演
奏法の対比が、絶対的対立なのではない。彼らは、リスト辺りから続く、19世紀の作曲家
・ピアニストのほぼ最後の人たちと考えることが出来て、録音機械によって、真に作曲家か
ら独立的存在となる”演奏家の時代”のやっと入り口の人たちと見た方が良い。
だから、後の世代で”演奏家”というものを、さらに掘り下げていった場合、どんな作品も
”語り口”の音楽の要素は、結局出てくる。 それで、ラフマニノフ自身は均質な音で、積
み上げるように弾いただけ、ともいえなくもない3番の協奏曲を、ホロヴィッツは、"大き
な記念碑的イミ"をすべてに意識的に持たせるようにして、全体を通じた流れを作り出して、
作曲家自身の演奏と異なる”語り口”の演奏にしている訳で、また逆に、ガッチリした音で
弾かれるスクリャービンも可能ということになる。
パガニーニなどの19世紀の曲芸的な演奏を披露したといわれる音楽家たちは、聴衆を沸か
せることだけを狙った悪趣味な傾向と考えられる場合もあるが、その楽器の技術的可能性の
開発ということだけでなく、聴衆が自ら”価値判断”出来る、なるべく見え易い、ある”分
量的”きっかけを与えておくという”社会的方法”というべきものでもあり、大雑把な言い
方をすれば ”開かれた”率直な「市民性」の顕れという面も持つのは、決して軽んぜられ
ない。
リスト、アントン・ルービンシュタイン、パデレフスキなども含めた、19世紀のピアノヴ
ィルテュオーソたちが、どんなものだったかは、ともかく、20世紀初頭頃からのロシア、東
欧系のピアノヴィルテュオーソたちは、、音符を勝手に付け加えたりしない傾向、代わりに
、演奏の”肉体的技術”に重きをおいたそれまでより、もっと作曲家と別の存在になってい
って、そういった限定された分野ゆえにより繁盛していくことになる。そして、いわゆる
”演奏家の時代”において様々なかたちで、独立的存在として、より掘り進められることに
なった・・・ぐらいのことは言えそうである。
ラフマニノフには、ドレスデン時代に書いたとされる交響詩『死の島』という曲があり、当
時のサロン文化の中で、相当 複製が出回って飾られ、流行みたいになっていたベックリン
(1827-1901)の絵画作品を題材として、描出した曲だといわれている。
ベックリンの『死の島』という作品は、ほぼ似たような構図で何枚かあるみたいだが、この
前のページで、参考画像として貼り付けてあるものは、代表的な 1880年の111×155cmある
大きさの作品。
ベックリンの絵は、確かに独特の弛んだ”悪趣味”なものが、混じる場合もあるし、野暮っ
たい人体描写など、弱点もあるのだと思うし、そういう面からの共鳴者も確かにいたと思う
が、それでも幾つかの絵の、独自の面白さは、やはり無視しないほうがいい。
ラフマニノフの交響詩『死の島』は、チャイコフスキーの交響詩みたいに、交響曲と映画音
楽の中間的(むしろ、どっちつかずの)作品といえるようなもので、この絵の陰気な海と空
と手こぎボートの揺れなどを単純に描写したような曲になっている。ラフマニノフが、この
絵に相当共感を持っていたのは、わざわざ管弦楽曲まで書いていることからも確かなわけだ
が、けれど、この絵を、今日観て、興味深いのは、そういったもっともらしい表面的ムード
よりも、むしろ「得体の知れないものが描かれた得体の知れないカンジの絵」ということが
重要で、実際 こういったところは、デ・キリコなどに直接的影響を与えた要素でもあり、
この絵の本質的面白さの要素”得体の知れない唐突な組み合わせ、バラバラさ”というのは
、そういった面では 案外、第1ピアノ協奏曲の方に、もっと近いところががある。
というのは、絵画『死の島』の真ん中の布きれを巻き付けた人物のようなものは、外界から
遮断されて直立しているが、ボートの漕ぎ手の女性?のままに糸杉の数本(糸杉は当然、墓
地とかのイメージを持つ)そびえ、石窟風な建造物と一体に成ったような孤島に頼りないよ
うなゆっくりさで進んでいく。同様にピアノ協奏曲も、こり固まったような半音階的序奏と
感傷的な揺らぐような主題と一緒になって、どこか”消失”(飛び去っていく)”死”を連
想させる方向に進んでいく訳だし、序奏と緩やかな主題は最後まで本質的には遮断されたま
ま、というのが基本的発想になっていることは、まず考え得るから。
布きれを巻き付けたようなものは何か?作者が、この絵に関して直接何か言っているのか、
また こういう絵画の研究者といえるような人たちが何を言っているのか、余り気にしすぎ
ても、一般につまらない議論になりやすいことは、ここでも言っておく必要がある。
むしろ、”正統的な”やりかたは、この絵を見て、自分がどういうようなことを、考えたく
なるか、どういうものと類似性や比較を考えるか、注意することである。何故そうなのかと
いうと、そもそも絵の鑑賞とは、そういったようなことだから。(ちなみに、ベックリンは
自らの絵の中の神話的人物たちの、余り細かい文献的詮索を好まなかったらしい・・・)
一応、もっと詳しく考えてみるならば、その中央のボートの上に立つ布きれを巻き付けたよ
題に続く部分との、極端な対比は、何か別のものに融合、発展したりなどせず、単に順
序を変えたり、楽器を変えているだけで、むしろ、よりはっきりバラバラなままなのを
強調して、終わるのである。
もちろん、その前に今、書かなかった展開部にあたる部分がどうかということが、ここ
で問題になる訳だが、第2、3協奏曲の1楽章のような大きな扇状の流れを持とうとす
るのと、程遠い、薄い扱いで、1番の1楽章全体では、一定の情緒を連続的に増大、発
展させる部分が、大してなく、情緒的な連続感の無いバラバラな情緒の部分が、とても
目立つことになる。
2番の1楽章なら、展開部といえるところになって、ピウ・ヴィヴォでピアノが参加し
てくる部分は、第1主題の頭から、いえるものが右手で、第2主題が左手というカンジ
で、1番の展開部の部分もそれに近いやり方をもつが、以降も含め、それ以上に主題の
綜合的扱いが行われ、また、ここは線的動きの複雑さをもった部分でもある。この入り
組んだせわしい小さな動きが、ピウ・ヴィヴォの2分音符の80の指示のある頃から、
解きほぐれるように、同じ旋律を持ちながら拡がっていき、だんだん速くポコ・アッチ
ェランドで、オケに第2主題のはっきり出る状態で、それが両手の流れるような動きに
まで変化する。そこに両手の重厚な和音でロシアの土俗的な力みたいな新しい主題みた
いな部分がアッチェランドで加わってくるが、再現部で第1主題がオケで奏される部分
にも連続する調子のところでもあり、またそれらの主題に和声的に関連して作られてい
る、そのパワフルなカンジのものに、流れが移る。そして、ピアノで”鐘”の上昇的音
が鳴り、土俗的ピアノの音楽が豪快に第1主題を連れてきて、その主題がメノ・モッソ
へ連続して流れ込み、そこでピアノのソロのアルペジオの音楽による、ロシア風哀愁の
部分に変わり、だんだん緩やかになり、音楽の”エネルギー”も終わりに向けて、明瞭
に落ち着いたもの下っていく。
こういった展開部からの流れは、類似性のある主題や、その部分的要素を、つなげていっ
たもので、主要な流れが出来ているし、それが速度が速まっていったり、音程差が拡がっ
たり、厚く重ねられた和音の激しい動きになったりまでする事で、よく似た情緒が拡大、
興奮的強い信念へ変化し、また落ち着いていく情緒の扇状の発展パターンの典型的なもの
で、1楽章全体を見ても、第1主題の旋律的だが重々しく暗い感じでピアノのアルペジオ
の波のうねりで始まり、第2主題はほっとする明るさもあるが、似た長いロシア的メロデ
ィーで、情緒はとても連続していて、連続する影と光の表情の反映そのもので、つなぎの
部分のウン・ポコ・ピウモッソの部分なども、一見違った音楽の闖入風だが、似た素材で
ムードの流れを壊さない、蔓草模様の装飾的つなぎになっている。
これに対して、1番の1楽章は、2つの主題のつなぎといえる部分も、気散じ的に動き回
るようなものだし、また、全体の4部分位の各部をつなぐような序奏部分の半音階的要素
も無機的に、情緒の連続を切り裂くし、何より、肝心の展開部が如何にもウェイトが措か
れていない書かれ方で、2番のような念の入った連続した展開はないし、再現部の盛り上
がりに上手くつながるような書かれ方はされず、オケだけでファンファーレの頂点部分を
作るし、後半部分のピアノの入る部分と完全に分裂していて、この楽章中、結局、類似性
のある情緒の発展的部分は、大きな構造を成さない。だから、この1楽章全体に、前に述
べた対比的情緒の奇矯な強力さは、それに勝る大きな構造がないので、全体の何か、一見
すると、”唐突”なような印象をそのまま作り出しているともいえる。
2番だけでなく、3番の1楽章も、もっとも単純で素朴なロマンティックな歌の呈示に始
まり、(2番の2楽章の途中のピアノの扱いを移してきたようでもある。)そのメロディ
ーが、オケの弦に移り、ピアノが走句で装飾するようになり、その動きが自然で延長的な
ものだが、経過部分の複雑なものに一旦なる。その豊かな装飾が小さなカデンツアになり、
また、その後の、濃密な情緒のアラガラントなどテンポの揺れをもつオケだけの音楽の小
さなつなぎの部分も、全く最初のテーマから類縁性のあるもので、ごく自然な情緒で連続
するし、次の第2主題の呈示も、押し流すながれから、一旦 身を離した気楽なリズムで
また、トーンも少し光の射し込んだ感じの簡明さから、独奏ピアノのショパンのノクター
ン風な伴奏音形を繰り返す優しげな格好で、始まるが、その動きが再び速く、大きく、激
しくなっていく。ピアノの左手の下降音や分厚い和音が、走句に変わって流れたあと、テ
ンポ・プリモで、再び 最初の第1主題がほぼそのままの格好で戻ってきた後、直ぐ音楽
はピウ・モッソで、ピアノの羽ばたくような動きになり、そこで1楽章の頂点の状態の大
きな準備みたいになり、例のピウ・ヴィーヴォのスクリャービンのエチュードみたいな部
分があって、オーケストラとピアノが打ち合うfffにまで、速度と音量、複雑さは増して
行く。そのあと音楽は目に見えて緩やかな揺らぐような動きになり、長い激しく複雑な
カディンツアを挟むが、再現部は非常にあっさりと短くそのまま弱まって終わる。
だから、3番の1楽章全体の流れは、単純な指一本的メロディーが、だんだん複雑的密な
状態に増大し、一旦優しい第2主題のトーンに移ってまた増大化、さらに展開部で第1主
題が戻ったのち頂点的増大化し、あとはカディンツアを除くと弱まり、収まっていく大き
な凸的流れがある。
3段階みたいな感じで、類似した情緒が、音構造の速度と音量、複雑さの増大で連続的に
拡大し、興奮的強い信念へ変化し、また落ち着いていく訳で、2番とやはり共通する情緒
の扇状の発展パターンなのだが、2番の方は、寄り集まる線の動きの変化に、もっと依存
しているが、3番の方は、より、単純から複雑への”物量的”なものに依存している。
とはいえ、2番3番は、共に大きな類似した連続する情緒の構造部分を中心にしているの
は、明白で、それに対して1番の1楽章は、これまで描写してきたように、呈示部、再現
部、カディンツアでも、そういうものはないし、反するものが狙われている。そして、全
体のまとまりの必要性から、そういうものがあってよいはずの展開部でも、集中感には遠
く、前半のオケだけの部分と後半が分かれているくらいなのである。
しかし、詳しく見ると、1番の展開部にあたる部分は、先程の呈示的部分の終わりのヴィ
ヴァーチェのフレーズからは、そのフレーズが一通り言い終わった後、オーケストラだけ
の部分となり、第1主題の始めと関係する音形が繰り返し、激しくなって展開されるのだ
が、ここでは、実は2番の展開部とよく似たやり方で、序奏の要素も重ねられている。さ
らに、その第1主題と関係する音形の発展部分が このソナタ形式風の構造の頂点を作り
るのだが、そこで目印のようにファンファーレが、今度はFで鳴る。そして、それは1楽
章冒頭のファンファーレに対応するものなのである。そのあと、後半部分が、続き、ホル
ンのソロで第1主題を優しく鳴らし、ピアノを加えて慰撫する調子になるが、ぐるぐる速
くなる感じで激しくなって、また、序奏の要素が現れ、ピアノで第1主題からの、先に呈
示されたのとほぼ似た音楽の再現部分とつながる。
後半部分でソロのホルンが奏す第1主題は、遠くで鳴っているように響き、その周辺で戯
れ、彷徨うようなピアノの動きがあって、その前のオーケストラ部分だけの突き進むよう
な前半部分の最後のファンファーレが、正に1楽章の折り返し地点であり、展開部全体の
パースペクティブが、”ある遠いところ”にもっていかれている重要なことにも気付くと
、2番の展開部と似た扱いも含めて、2番3番のような連続的な大きな構造が作れなかっ
た、というのでなく、そのような連続性をパースペクティブの”一部分”として、意図的
に簡素化して置かれていると見ることが出来るのである。
確かに、このような各部分バラバラなムードの作曲作品は、十分、自らの楽想を大曲でコ
ントロールできない作曲技術の未熟さと一脈通ずるところがあると考えられ、実際、この
1番の原初的なもとの格好は、ある程度、そのような傾向があったのでないかとは想像し
うる。しかし、現行の1番は、そのようなもの単純なものでなく、多分、それを元にして
はいるが、意図的に構成され、むしろ、2番3番的な構成を、部分として包含するみたい
なものでもある。
未熟さ、みたいに見える一番の協奏曲としての問題は、展開部が薄い感じがし、大きな連
続感を感じさせる構造が乏しいというのが、やはり理由みたいになって、カディンツァぐ
らいの部分が、目立ちすぎ、ソロが、今まであった全てを一人でカバーするみたいなこと
になり、その前の協奏曲の構造の主たる全体を、1人で凌駕しよう、としていることにな
り、あるイミ、協奏曲の構成の必然性をここで、自ら否定してしまうことなのではある。
そしてまた、同時に そのように一見あえて、自らの存在を不確かなものにしてしまいそ
うでいて、ホロビッツが「・・・とても好きだ。・・」と言っていたように、曲になじんでくる
と2、3番以上に”不思議で謎めいた魅力”を感じる曲であるのも本当なのである。
もちろん、カディンツァが、その楽章を聴くとき、一番聞き所で山場だと云うことはあり
うる。モーツアルトにとってピアノ協奏曲は、重要なジャンルで、しかし、それでもその
ソナタ形式の前の部分全体がガッチリした建築として存在していて、華やかで自由なカデ
ンツァがあるので、最後は肝心の最も重要なテーマをオケと一緒に奏したりもするのであ
る。だから、やはり、ラフマニノフの1番の積極的につなでいくようなムードのない曲の
流れは、非常に例外的なものといったほうが、いいと思う。(全く、古典の曲の作り方を
無視する場合や、また、作品として問題なく?価値が低い場合を、除くと・・・)
といっても、1番の1楽章をつないでいる大きな構造といえるものがある。それは、ソリ
ストが、全てを引き受けてしまうという成り行きで、呈示部で、激しい序奏をピアノが受
け持ち、優しい第一主題をオケで始め、再現部で逆に序奏をオケで、第一主題をピアノで
持ち替え、綜合するようにカディンツアでピアノが全部一人でやってしまうということ。
極端な名人が、相対立し、融合しないものを強力な名人芸で一つにしてしまう。
結局のところ、これはヴィルトージティーの音楽で、ただ2番3番が、ヴィルテュオーソ
的存在が、”自ら働きかけるもの”としての、意識的発展的な情緒のつながりの音楽であ
ったのに対して、1番は、むしろ”ヴィルトオジティー自体の音楽”と呼べるような、自
らの働きかけに応じない様相も含めた意識の限界の織りなす”遍歴”の情緒の流れで、そ
のイミで、意識外の関連まで問題にしているのだし、また 主体的な意識を離れたヴィル
ティオーソ的存在の持つ”気まぐれ”でもある。
ニーチェのツァラトウストラが、落ちてしまった”綱渡り師”に対して、ニーチェ的でな
いような共感を、ちらりと示すところがあるが、最終的に「徳」virtueを表現するものを
”理想”とするとはいえ、個人の”技”を、何であろうと極めようとする名人芸には、人
々に直接非常に訴えかける、ある種の輝かしさと、一瞬一瞬の不安定さ、一貫しない気ま
ぐれの上に成り立ったものというところがある。
ホロヴィッツは、先の引用したインタビューの中で、”1番は、大変好きだ。余りやられ
ないが・・・”と答えていたわけだが、ホロヴィッツ自身の第1番の演奏の録音は、若い時
のものも、残されていないようで、代わりに?、バイロン・ジャニスの演奏の方は、優れ
た腕前の録音を聴くことはできる。
バイロン・ジャニスの演奏は、”無関心”なまでに、さらさらと全体を弾き通す”クール”
さと、冒頭部分、カディンツアなどの冴えた音の技の”切れ味”みたいなものに伴う強い
情緒の対照など、この曲の”気まぐれ”な輝きを生む一連の流れに、この人の個性が、重
なり合った説得力になっている。 (2003/4/5)
バイロン・ジャニスの演奏の特徴は、判りやすい例でいえば、ラフマニノフの例の前奏曲
嬰ハ短調などの録音を聴いてみれば、独特の揺らぐようなテンポを取っていることが判る。
厚く両手で重ねた和音の連続だけ位で出来ている、この最初期の曲は、ほぼ三部形式で、
コーダが付いたものだが、もう代表作の手法と殆ど同じものがちゃんとある。
コーダの重厚に重ねられた殆ど同じ和音の柱の連続に、右手だとA・G#・A・A#・A・G#
みたいに半音的に動くラインで、怪奇趣味調の変化和音を綴っていくやり方は、第2協奏
曲と全く同じといっていいくらいだし、その2楽章の冒頭もそのヴァリエーションで、ラ
フマニノフのトレードマークに近いものだし、半音づつ降下して中間部の3連符の回転す
るような動きのあとfffから両手で、和音を交叉させて打ち鳴らすように降りてくるとこ
ろも、第2協奏曲の終わり、第1協奏曲の終わりのみならず、ラフマニノフの好む手法に
なる。
この曲は、再現的部分で4段譜になったりするくらいで、ピアノで最大限に分厚い和音を
作ろうとするため、バスを鳴らしたまま飛び離れた和音を鳴らしたりしなければならない
ところが、多いからテンポの作り方が通常より問題になる曲だが、バイロン・ジャニスの
演奏だと、それほど力強い感じでもないが、鮮やかな感じと共に、この人のテンポが特に
掴みづらく、ふらふらする感じが目立ってくる。ワイセンベルクにも、この曲の録音はあ
るが、比較すれば、始めからずっと安定した感じでテンポがとれるし、中間部のアジター
トの指示のあるところは、ピアノ協奏曲の箇所のところの様にアッチェランドしているが、
そのような感覚が保たれ速くなるので、変化も安定して聞こえる。バイロン・ジャニスの
場合、そういう安定感とは遠いし、何かふわふわしたテンポ感覚を作り出すのが、本質的
に必要なことで、むしろ、そうであるからこそ、その少し船酔いしたような気分の中で、
独特のピアノの音の輝きが生きるということがあり、このことは又ホロヴィッツの場合も
、ほぼ似たようなことがある。
この前奏曲が、ラフマニノフの全作品の中で示すものと、ちょうど同じ様な関係で、スク
リャービンの場合、最初期のエチュード作品2の1(1887)があり、この2曲は、両方の
作曲家の特徴を、不思議なほど対照して見せてくれている。 (2003/4/8)
ラフマニノフの嬰ハ短調のほうは、単調なまでにガッチリした素材を、それを一定に変形
させ、また出来る限り壮大な音構造に、如何にも建築的に組立ることによって成り立って
いるのに対し スクリャービンの嬰ハ短調のほうは、一方でずっと和音を刻み続け、その
上にショパンの風の、しかし、もっと濃厚な風味の旋律を歌わすことで出来ている音楽。
中間部分は短く 簡単な長調部分。そのあと始めの旋律が戻ってくるが、デリケートな対
旋律が加わってくるし、また全体的にショパンより線的動きが、常に復綜的に考えられる。
スクリャービンの歌わせる音楽の、デリケートで濃密な語り口を作るのは、多分に言語的
な詩的想像力によっているのでないかと、受け取るのは無理のない考えである。
「・・・何ものかが、かすかに光り脈動を始めた。・・・・それは、揺れ動き、光ったが複数
でなく一つだった。・・・それは意識の出発点の混沌でもない。全歴史、全将来、永遠
が、その中にあり、全要素が混ぜ合わせられているが、そこには存在可能性の全てが
ある。・・・それは、色彩、感情、夢など、を滲み出させる。・・・過去と未来の瞬間は、
同時に到来する。予感と回想。恐怖と歓喜の錯綜。・・・」
「・・・私は、咲き盛る花であり、私は至福だ。全てを燃やす熱情で、全てを飲む宇宙を覆
う炎だ。混沌に帰すための、私は、解放された盲目の力だ。私は眠れる創造、抑えられ
た英知だ。・・・」(以上、本文の参考のため、短くして、適宜に要約したもの。)
cf T・S・エリオット
というのは、スクリャービンのメモにある、彼自身の言葉なのだが、従来、こういうスク
リャービンの言葉は、晩年の大規模な音楽と色光を結びつけ、また匂いまで加えようとし
た奇矯な”総合芸術”の計画や、私生活のスキャンダルの方向で、もっぱら奇妙な作曲家
のナンセンスな文句のように受け取られている。しかし、また
「音楽だけを書くという方法が、私には解らなくなった。・・・音楽とは、確かに、それが
世界的見地の全体の計画の中の単一の計画と関連して、はじめて理想と意義を持ちうる
ものだ・・・」
という友人に宛てた手紙の中の言葉といわれる、この文句も、例によって、その後の”総
合芸術”の計画という類いの話しだけに結びつけて考えるのは、短絡的でないのか?
むしろ、スクリャービンの音楽の考えの中には、後年にこの発想が、露骨に出てきただけ
で、もともと初期から後年まで通して、この傾向があったことを、見ることの方が重要で
、先程の詩めいたメモの書き付けに描かれたような感覚も、”焔に向かって”というよう
なものに、具体的なくらい、近いことは明かに思えるし、また 初期の前奏曲の中、そし
て作品2の1のエチュードの甘く包み込まれる世界の感覚の中に、ショパンとの違いみた
いなものなど、として、すでにはっきりとある。
『焔に向かって』作品72(1914)を、ホロヴィッツが、自宅で弾いている元々プライベー
トな録画が、残っていて「非常に難しい曲だよ・・・」というように語ってもいたが、実際
私などでも、弾いてみると、譜面の音符が、割と閑散とした状態であることもあり、むし
ろ、いきなり通して弾いても曲にしやすいもので、曲のポイントさえ掴んでいれば、リズ
ムがゴマカシ気味になってしまうのを勘弁してもらうなら、愉しく弾けるし、”効果”も
高い曲だということが解る。
勿論、ホロヴィッツのような立派な音で、鮮明な音の渦を作っていくのは、大変 難しい
だろうが、それ以前に、この曲を、普通の演奏者たちにとって、難しくするのは、この曲
のある種の”単調さ”になる。
この曲は、最初は右の2音、左の2音で、律動のような短い旋律で、神秘感のある4度和
声的響きが、だんだん厚みが増していくかんじで、次のバスがEとGを動かす部分に始まる
、ひらひら動くような部分に移る。それが、中声部の冒頭主題と、アルペジオ、装飾する
音符などが、見事な線的絡み合いを作り出し、続くC#・H・A#・G#の鈴を振るような鐘
の音が、出る部分になり、バスの音がドンドンと鳴ったあと、波のゆれるような、バスが
上下に動く中、タターンと冒頭の旋律が断片的に高音で鳴る部分があり、その動きが静止
的動きに変わった後、延々と F#・B・Eというような音形を打ち鳴らし始め、F#・C・
G#・Bなどといったような組み合わせの鐘の音を、ずっと熱狂的に鳴り響かせ続ける終盤
になる。そこで、最初の旋律の音が、低音部で重厚に奏され、最後に意味深なE・B・G#
・B・E・G#・A#・D#・A#・D#・G#・C#の上向する単音を、各々付点4分音符で響
かせて終わる。
非常に良くできていて、スクリャービンの手法の多彩さが、凝縮しているような曲だが、
それでも似たような音形が、延々続くし、旋律も発展が、指向されている訳でもないから
演奏によっては、随分単調な印象になる。そんな場合、何が欠けているかと云えば、この
曲を、単純な音量増大に近いものと考えて、この曲のバスの入り方、鐘の音の鳴り方、主
題の断片、うねる音のスリルといったものに顕れる我々の”現実”に埋め込まれた情緒の
展開を、曲から読みとった”語り口”に出来ないのである。
もちろん、こういう展開は類似性した情緒の”エネルギーの増大”(フロイトの云うとこ
ろのイミで”エネルギー”と一応考えてもいい)みたいなものである、一方 ”われわれ
の言語”に埋め込まれた各々の情緒で、単なる歓喜への増大では決して無く(そう見れば、
ある種の悪いイミでの”抽象”であろう)むしろ、”歴史感情”を語る、に近いと考えた
ほうが、浅薄な演奏を防いでくれる。
先程のスクリャービンのメモからの引用に在ったような観点で、多彩なピアノの響き、フ
レージングなどを積み重ねて、一つの統一された曲の世界を作っていく。こういった語り
口、こうして読みとって語ること、の配慮無しには、このような曲の演奏は単調で成り立
たないものになる。
スクリャービンも、ラフマニノフ同様、非常に優れたピアノ演奏家だったと云われている。
ただし、非常に違ったタイプの演奏法で、それは両者の曲作りの違い、とほぼ同じ傾向を
示していたらしく、スクリャービンの追悼演奏会で、ラフマニノフが、スクリャービンの
曲を演奏したとき、余りにもラフマニノフ流の演奏だったので、スクリャービンの友人た
ちは非常に不満を感じたらしい。また、この時 聴いていたプロコフィエフが両者の演奏
を、評した言葉が残っていて、スクリャービンの演奏は「・・全編が、微妙な色合いの魅惑
と暗示に満ちて流れていた・・」一方、ラフマニノフの演奏は「すべての音が、しっかりと
大地に根付いたもの」であったというように云っていたらしい。(この辺りの、引用や逸
話などは、H・ショーンバーグの便利で分かりやすい本からのもの、です。)
スクリャービンとラフマニノフの演奏法の違いは、ここまで書いてきた幾つかのことを踏
まえると、ピアノ演奏のやり方において、現代で、極めて影響の大きい”ロシア型”のピ
アノビルティオーソというものの本質を、典型的な対立したタイプとして、示しているも
のといえるかもしれない。
それは、スクリャービンが、演奏を詩的言葉と(先の引用したメモの文句)関連する多彩な
色合いの表情の流れるような演奏をするのが重要と考えたに対し、ラフマニノフは、むしろ
演奏を、すべての音を均一にちゃんと鳴らし、その上で力強い音楽を構成する(これは、残
っている録音からも分かる。)ことを考えたもの、というような違いになるだろう。(2003/4/11)
こういったことに関して、身近な経験からも、云えることの一つは、スクリャービンの音楽
は、非常に凝った技巧的な音楽という印象が、前面にある割に、そんなにバリバリと、音符
をこなしていくピアニストの能力ばかりを要求するものではないということは、云えるのだ
と思う。例えば、有名な練習曲嬰ニ短調作品8の12など、シャープが、いっぱい付いたり、
相当 ごちゃついた譜面だが、手の動きの流れとして自然で、前半が左手の一定の回転運動
をして、後半が和音連打している間、右手が、オクターヴで旋律を歌うといいうような曲に
なっている。
厚く重なった和音同志が、離れたところに飛んだりする部分があっても、一方が、単純なオ
クターヴだったりするし、最初の方で両手のオクターヴの練習曲みたいなところに、11度と
か12度なども要所に挟まっていたりする訳だが、実際の演奏を聞く側にすれば、高い方の音
が抜けたり、単純なオクターヴになっていても、大雑把にいえば、場合によっては、そんな
に目立たなかったりする。また、そんなバスの動きから、ややこしいところに飛んだ音が譜
面に書かれているが、それも結構、同様だったりする。
もちろん、こんな言い方は、極端なものでしかないけれど、あるロシア人?のベテラン風の
ピアノ女性教師が、練習曲の作品42の5の演奏で、甘い旋律的なものが、戻ってくるとこ
ろで、内声部のようになる細かく揺れ動いたりする部分を、完全に弾き通す必要はない、み
たいに明言していたし、一方でロシアの学究っぽいピアニストの男性は、スクリャービンに
1音たりともムダな音はないとも云っていたけれど、やっぱり、スクリャービンのピアノ曲
は、その種の傾向があって、ちゃんと弾くのは望ましいけれど、しかし如何に楽譜を”完全
に”弾いたとしても、”語り口”が的外れであれば全然ダメみたいなことはある。曲の一番
大事なところを考えること。そこにどうやってもっていくかを考えること。
演奏会でやるのでなく、「ブラインド・テスト」紛いに聴いてもらうため、練習曲嬰ニ短調
作品8の12や、前奏曲の幾つかを、私が自分で録音して、例えば、アマチュアオーケストラ
でやる”新世界”の1stヴァイオリンのパートを、練習しながら「もう、速すぎて弾けない・
・・」などとこぼしている、うちの母親程度の人の耳(??・・・・・)を相手に”実験”する場
合、細部が少々いい加減なのにも、かかわらず、曲に不向きな場合もある普通のピアニスト
たちの演奏と、並べて聴かせると、結構もっとそれ風に聞こえたり、区別がつかなかったり
する事実は、身近な経験でも確かめうるスクリャービンの音楽のある側面を語ると思う。
※ 誤解の無いように、書き加えておくと、ラフマニノフとスクリャービンといった”ロシア音楽”に詳しい
方は、日本では多分たくさんいらっしゃるわけだし、私などウォルトンやシェーンベルク、ウエーベルン
(これはとても少ないけど・・笑い)の殆どの曲は聴いたことはあるけれど、ラフマニノフのオペラや歌曲
は、全く部分的にしか聴いたこともないし、好きなピアノ曲を弾いたり、聴いたりするくらいなものなわけ
だから、その他、ちゃんと扱うには全く不十分な準備しかしていないというのは、断っておかなければなら
ないと思います。
しかし、ウォルトンやヴォーン ウィリアムスを捉える場合と、似た問題が、ラフマニノフにはやはりあっ
て、そこから見ると非常に重要な言わねばならなかったことがあると考えますし、この文章全体は、そうい
った話題からの脇道程度といえますし、尚更、まず全体の輪郭を見通すことが優先される書き方になってし
まいます。これまでの他のページでも 同様ですけれど、曲の作られ方を、言葉で簡単に説明しようとする
と、書き方の都合で誤解を招きやすい表現になる場合が、どうしても出てくるので、もっとより良い表現に
気がついたら、改めようと考えています。また、メトロノームの数字も、私の手持ちの機械で、計った結果
を参考までに書かせてもらっているので、ミスっていなければ、細かく言えば計る箇所によって、相当安定
したテンポの演奏でも、やはり揺れるので、その構成部分の代表的なテンポと思えるもの、ということにな
ります。
逆に、ラフマニノフの場合などは、そいうふうになりにくく、前奏曲ト短調の作品23の5
など、譜面は、スクリャービンの先の練習曲より、一見易しそうだが、弾いてみると、”不
安定さ”が、あるとずっと粗が目立ちやすい。
そういう具合に、ラフマニノフとスクリャービンの作品の違いは、演奏家として望むものの
典型的違いの傾向に関係しているのであるが、しかし、ラフマニノフとスクリャービン的演
奏法の対比が、絶対的対立なのではない。彼らは、リスト辺りから続く、19世紀の作曲家
・ピアニストのほぼ最後の人たちと考えることが出来て、録音機械によって、真に作曲家か
ら独立的存在となる”演奏家の時代”のやっと入り口の人たちと見た方が良い。
だから、後の世代で”演奏家”というものを、さらに掘り下げていった場合、どんな作品も
”語り口”の音楽の要素は、結局出てくる。 それで、ラフマニノフ自身は均質な音で、積
み上げるように弾いただけ、ともいえなくもない3番の協奏曲を、ホロヴィッツは、"大き
な記念碑的イミ"をすべてに意識的に持たせるようにして、全体を通じた流れを作り出して、
作曲家自身の演奏と異なる”語り口”の演奏にしている訳で、また逆に、ガッチリした音で
弾かれるスクリャービンも可能ということになる。
パガニーニなどの19世紀の曲芸的な演奏を披露したといわれる音楽家たちは、聴衆を沸か
せることだけを狙った悪趣味な傾向と考えられる場合もあるが、その楽器の技術的可能性の
開発ということだけでなく、聴衆が自ら”価値判断”出来る、なるべく見え易い、ある”分
量的”きっかけを与えておくという”社会的方法”というべきものでもあり、大雑把な言い
方をすれば ”開かれた”率直な「市民性」の顕れという面も持つのは、決して軽んぜられ
ない。
リスト、アントン・ルービンシュタイン、パデレフスキなども含めた、19世紀のピアノヴ
ィルテュオーソたちが、どんなものだったかは、ともかく、20世紀初頭頃からのロシア、東
欧系のピアノヴィルテュオーソたちは、、音符を勝手に付け加えたりしない傾向、代わりに
、演奏の”肉体的技術”に重きをおいたそれまでより、もっと作曲家と別の存在になってい
って、そういった限定された分野ゆえにより繁盛していくことになる。そして、いわゆる
”演奏家の時代”において様々なかたちで、独立的存在として、より掘り進められることに
なった・・・ぐらいのことは言えそうである。
ラフマニノフには、ドレスデン時代に書いたとされる交響詩『死の島』という曲があり、当
時のサロン文化の中で、相当 複製が出回って飾られ、流行みたいになっていたベックリン
(1827-1901)の絵画作品を題材として、描出した曲だといわれている。
ベックリンの『死の島』という作品は、ほぼ似たような構図で何枚かあるみたいだが、この
前のページで、参考画像として貼り付けてあるものは、代表的な 1880年の111×155cmある
大きさの作品。
ベックリンの絵は、確かに独特の弛んだ”悪趣味”なものが、混じる場合もあるし、野暮っ
たい人体描写など、弱点もあるのだと思うし、そういう面からの共鳴者も確かにいたと思う
が、それでも幾つかの絵の、独自の面白さは、やはり無視しないほうがいい。
ラフマニノフの交響詩『死の島』は、チャイコフスキーの交響詩みたいに、交響曲と映画音
楽の中間的(むしろ、どっちつかずの)作品といえるようなもので、この絵の陰気な海と空
と手こぎボートの揺れなどを単純に描写したような曲になっている。ラフマニノフが、この
絵に相当共感を持っていたのは、わざわざ管弦楽曲まで書いていることからも確かなわけだ
が、けれど、この絵を、今日観て、興味深いのは、そういったもっともらしい表面的ムード
よりも、むしろ「得体の知れないものが描かれた得体の知れないカンジの絵」ということが
重要で、実際 こういったところは、デ・キリコなどに直接的影響を与えた要素でもあり、
この絵の本質的面白さの要素”得体の知れない唐突な組み合わせ、バラバラさ”というのは
、そういった面では 案外、第1ピアノ協奏曲の方に、もっと近いところががある。
というのは、絵画『死の島』の真ん中の布きれを巻き付けた人物のようなものは、外界から
遮断されて直立しているが、ボートの漕ぎ手の女性?のままに糸杉の数本(糸杉は当然、墓
地とかのイメージを持つ)そびえ、石窟風な建造物と一体に成ったような孤島に頼りないよ
うなゆっくりさで進んでいく。同様にピアノ協奏曲も、こり固まったような半音階的序奏と
感傷的な揺らぐような主題と一緒になって、どこか”消失”(飛び去っていく)”死”を連
想させる方向に進んでいく訳だし、序奏と緩やかな主題は最後まで本質的には遮断されたま
ま、というのが基本的発想になっていることは、まず考え得るから。
布きれを巻き付けたようなものは何か?作者が、この絵に関して直接何か言っているのか、
また こういう絵画の研究者といえるような人たちが何を言っているのか、余り気にしすぎ
ても、一般につまらない議論になりやすいことは、ここでも言っておく必要がある。
むしろ、”正統的な”やりかたは、この絵を見て、自分がどういうようなことを、考えたく
なるか、どういうものと類似性や比較を考えるか、注意することである。何故そうなのかと
いうと、そもそも絵の鑑賞とは、そういったようなことだから。(ちなみに、ベックリンは
自らの絵の中の神話的人物たちの、余り細かい文献的詮索を好まなかったらしい・・・)
一応、もっと詳しく考えてみるならば、その中央のボートの上に立つ布きれを巻き付けたよ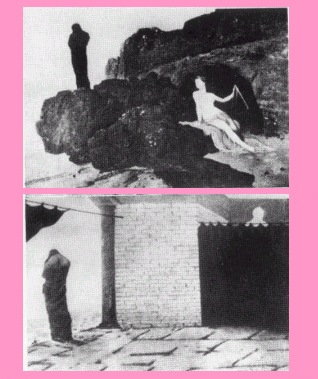 うな人物?について、まず制作年代の近い『聖なる森』(1882)という絵があってその絵は
、顔の描かれないそういった風体の人物たちが森で祈っているから、『死の島』での人物?
も、ひとつは、修道士みたいなものだろうと想像される。
また、ドレスデンに長く住み、そこで亡くなったフリードリッヒ(1774-1840)には、『海辺
の修道士』(1810頃)という絵があり、中央に小さな後ろ姿の長い衣を着た人物が、広大な
灰色の海辺の空間の中に描かれた有名な作品。 ベックリンは、スイス生まれで、絶えず
イタリアの南方に憧れた画家だったが、ドイツで絵の勉強をし、認められた画家で、50年
位前の世代のドイツ絵画の似た傾向をもつフリードリッヒを、当然意識したろうから、『死
の島』の真ん中の人物のようなものと『海辺の修道士』の関連は考えても良いであろう。
また、フリードリッヒは、ターナー(1775-1851)、コンスタブル(1776-1837)と殆ど同世代
で、あるイミ、同様に非古典的、非ルネッサンスの”風景の画家”であり、また ベートー
ヴェン(1770-1827)と同時代人でもある。 『海辺の修道士』は、ターナーの『Light and
Colour』と同じく、もう既に”抽象絵画”すれすれの作品で、そういった類の”進歩観”に
よるなら、ホイッスラー『花火』やゴッホの『烏の群れ飛ぶ麦畑』に先んじているともいえ
る。また実際、『海辺の修道士』の中央の小さな人物を除けば、灰色の分割された色面でし
か無く、そう観るなら、ジャクソンン・ポロック辺り( Bニューマンなど、例は、この類のもの何でも
別にいいけど・・2003/5/12付記)とも、大差ない。
ベックリンは、そういう”抽象”の方向に進まず、顔の見えない人間を残し、より意図的な
”形態”群の中に、一つとして置いた。この流れの方向が、ジョルジョ・デ・キリコ(1888
-1978)にも、つながっていったとも考えられ、キリコは、自らその影響を認め、『ベック
リン論』を書いているらしい。
そして、その影響関係の代表的例として、よく挙げられるのがベックリン『オデュッセウス
とカリプソ』(1882)とキリコの『神託の謎』(1909)の関係になる。ベックリンの絵画を、
もっと深く考えてみようとするとき、この2つの絵のことを参考にすると、とても役に立つ
のである。
例えば、ベックリンのこの絵にも、例の長い衣を着た後ろ姿の人物が重要な存在として、登
場してきている。この絵の場合、登場人物の関係と話しは、結構 はっきりしている。
後ろ姿の人物は、オデュッセウスで、彼はトロイア戦争で活躍して後、本国イタケに帰ろう
とするが、様々な困難に遭いなかなか帰国できない。その途中に、絵の右側の洞穴の前にい
る、美しい女性として描かれた妖精カリュプソの島に、難破したオデュッセウスは唯1人漂
着する。カリュプソは、親切に世話をしているうちに、オデュッセウスをとても好きになっ
たので、何とか引き留めようとする。
そこで”不死性”を与えるから留まって、とまでカリュプソは、申し出る。しかし、イタケ
で待つ、妻子の元に帰ろうとする固い決心を、オデュッセウスは変えないし、ゼウス神も、
帰してやれ という神託の命令を下したので、仕方なくカリュプソは、筏を与えて、帰国を
許す・・・
という話し。
(もっと細かく言うと、ややこしくなるが、ゼウスの意思を、直接 伝えているのは
ヘルメスで、一応直接は、頭部は、この伝令神のものになる・・・付記2005・7・28)
このベックリンの絵で特異なのは、そっぽを向いて、固まった岩のようなオデュッセウス、
(そして、それは、『死の島』での先程言った、”修道士”みたいな存在と大変よく似たも
のであることにも、当然注意して置いてほしいが)彫像のような優美なポーズを取るカリュ
プソと、何かバラバラの不可思議なムードがあることだが、そのことに関して、デ・キリコ
の『神託の謎』が、重要な参考になる。
キリコは、ニーチェ哲学に影響を受けているのは明らかだし、彼が広場で倒れたトリノの町
を1911年訪れ、強い印象を与えられ、そのイメージは絵に残されている。また、ヴァイニン
ガーとシュペングラーの本も、好んで読んでいたという。彼が、実際 絵についてどんな説
明をしたかとは、絵描きが、いちいち種明かしをして回るとは限らないから、その書いてい
ることを単純に受け取るより、まず、絵自体を見た方が良い。
『神託の謎』は、一見 全く謎めいた作品で、通常解説もベックリンの絵に対しての、関係
に触れる程度で、全くぼんやりした説明がなされているだけのように思う。
(ついでに、言っておくと、少なくとも日本の場合、音楽の分野では、その作品の意味内容に関する言語
表現が、臆病なまでに抑えられているか、音符的訓練に関して同じ様な話しばかり繰り返される他は、
非常に素朴な情緒の言語表現が与えられるだけみたいであり、一方、美術の分野では、その作品の意味
内容に関する言語表現が、”抽象的表現”などで、いたずらに膨らまされて、何も言っていないかんじ
になったり、また、やたらと西欧の美術表現には、固定したような”実証”できる修辞的語法が、歴史
的に存在したと思い込もうとしている、というような共に空虚な言語表現が溢れる状態になっていて、
分野で極端な違いが起こってしまっていることは注目に値する。)
私が思うに、この絵は”オデュッセウスとカリュプソ”という2人の真の関係を、解説して
いるのであって、すなわち、本当はカリュプソは、何でも良いのであって、真の関係は、カ
ーテンから、頭を出しているゼウスとオデュッセウスとの2者関係であり、愛し合っている
ように見える2人は、厚いベールで隔てられている。カリュプソは、”永遠の生”この場合
”永遠の愛”を約束しようとするが、恋人たちの意志、働きかけと無関係に、バラバラにな
ってしまう。目の前に見える甘美な愛は、オデュッセウス的本来の意志を、覆させることは
出来ない。というのも、オデュッセウスの意志は、本来、ゼウス神の意志であり(だから、
キリコの絵では、ベックリンの絵以上に後ろ姿の人物の”頭”が、欠けているように描かれ
ている。)彼は盲目の身体的固い意志で、故郷イタケに戻ろうとする訳で、頭はゼウスにあ
るのである。(ちなみに、キリコの絵では、後ろ姿の人物が、向かっている方向には、キリ
コの幼くして去ったギリシャのアテネの街が遠景で描かれているらしい)
近くにいると見える2人が、永遠なまでの”見えない隔絶した関係”を隠して並んでいる。
『死の島』でも、この解釈は参考になって、この絵は、後ろ姿の人物と、そのボートが向か
っているはずの、「死の島」との”本質的に隔絶した関係”が、問題となっていると考えら
れる。というのは、固まったようなオデュッセウスとカリュプソの間に、不可思議な断絶が
の雰囲気が、感じられたように、この島に向かう人物と、島の間には、ごく普通のボート遊
びのレジャーを楽しもうとする人と、その人が渡ろうとしている、どこか現実の島、といっ
た場合にある日常的文脈の”行動と目的”という雰囲気が、全くない、何か得体の知れない
”関連もしくは断裂”の雰囲気が重要なのである。
すなわち、ボートに乗った人物は、身動きもせず白い布に包まれ、生きたものかも判らない
遮断された存在で、ただパートナー的な女性が、ボートを漕いで運ぼうとしているだけで、
また、目的地である島も、通常 目的になりそうな望ましい感じでなく、糸杉がそびえる何
か死の匂いのする所であり、また、一方大事なことは、必ずしもそんなネガティヴだけのも
のでもなさそうなことで、例えば、蓬莱島ではないが、穏やかで静かな雰囲気は漂っている
し、島と融合したような見事な建造物は、人間の人工的構築物と自然の融合みたいなもので
もある。
だから、島と後ろ姿の人物との関係は、”行動目的と行動する人”という普通の関係でなく
むしろ、”オデュッセウスとカリュプソ”のように”神”が、真の関係を作っている。もし
くは、オデュッセウスのように厳しく意志を貫こうとする身を固めている人物、もしくは、
修道士のような人物(白黒の違いは別に考える必要はあるけど)が、緩やかな波のボートの
甘い戯れの気分に身を委ねながらも、本質的に”遮断された”存在であり、また、自ら ボ
ートを漕ぎ向かうのでなく、たまたまのパートナーに任せて漂うように進む過程の存在。そ
して、島と後ろ姿の人物は、一方で、強くつながっているのであって、それが目的地のよう
でもあり、「死」「消失」のようでもある場所、点、に何らかの力、関係によって操られる
ように進んでいく有様にもなる。
そして、ここから、ラフマニノフの一見 唐突でバラバラなムードを持つ、1番ピアノ協奏
曲の構成を、想い出してもらえば、その不思議な謎めいたような魅力を含めて、改めてとて
も近いことに、気付かないだろうか?
もちろん、ベックリンの絵の『死の島』の、ある重苦しい静かなような雰囲気や、怪奇映画
のようなイメージは、第1番ピアノ協奏曲には、あんまり無いし、交響詩『死の島』では、
もっぱら、そんな表面的イメージが再現されているが、一方、ベックリンの絵の『死の島』
を、想い起こす雰囲気は、交響曲2番なども含めて広い範囲で存在していること自体が重要
で、そう考えるならば、ラフマニノフの、感受性の半面の、ある基本的な態度である何か根
本的な次元が、問題になってくるだろう。
ラフマニノフの第1番ピアノ協奏曲と、ベックリンの絵の『死の島』の先程、少し詳しく触
れた”内容”みたいなものと、一番 違うところは、修道士もしくはオデュッセウス的存在
が、ロシア的ヴィルテュオーソ的存在として、もっと諸相に展開されて、”内容”に関わっ
ていることで、その他は、ほぼ重なった感じにすら見えてくる。
ここで、いままで書いたことを、繰り返すのに 少々近くなる部分もあるが、全て通してま
とめてみることは、必要なので《 協奏曲1番1楽章全体の流れ 》を、前に書いた部分より、
新たに付け加えた視点による見方を含めて、改めて書いておこう。
すなわち、まず、曲頭のファンファーレによって誘い出され、ピアノは非常に厳しい調子の
下降する序奏の音形を弾き出す。これは、独奏者の側の基本的立場といえるものでもあるが、
そこに独奏者に対する外部世界であるオーケストラは、非常にロシアの大地的?民衆的?と
いえるような切ない感じの対照的旋律をぶつけてくる。
その切なさに、対しても独奏ピアノは、やはり従わねばならないというように、しおらしい
感じで旋律を受け継ぎ、調子を合わせる。その音楽は、そのままの感じでは進まず、気散じ
で歩き回るようなピアノ部分を挟む、そこからやっとくつろげるような第2主題といえるよ
うな安らいだ音楽をオーケストラから得、そこからピアノはある種の勝利感を感ずるような
興奮した短い部分を奏する。
が、そこに安易な勝利感を打ち消すように、今度はオケが、序奏の厳しい音楽を激しく奏し
て、さらに、最初の旋律の部分が変形され、厳しい感じになり、序奏の要素も加わったりし
て、それが突き進む感じで展開され、曲頭に対応するようなファンファーレが、現れるとこ
ろまでオーケストラだけで行く。そこで折り返すようにピアノが戯れ止まって回転するよう
な軽い音楽となった後、最初の旋律が遠い感じでソロの管で鳴り、その旋律の最初の部分が
だんだん想い出されてくる感じで、繰り返され大きくなる。ここの展開部全体でもまとまっ
た重量感のある存在でなく、とくに展開部の後半は薄く遠い感じで、続く、1楽章の呈示的
部分のほぼ繰り返す部分と対照的な、”何か向こうの場所”になっていて、そこでは対立的
な序奏の固い感じの部分と最初の切ない旋律の部分が何か融合したようでもある。
そこでまた、ピアノ独奏の動きが激しくなった頂点に、序奏の厳しい音楽が半音階的な速い
動きで引き裂くように又割り込んできたあと、すぐ、最初の切ない感じの旋律を、呈示部と
違って、いきなりピアノ独奏で、そして前よりは力強い感じで弾き、そして、曲の構成とし
ては、後は呈示部と殆ど同じで、発展された要素があるというより、そのまま少し短縮した
感じで、続く、気散じの歩き回るような部分、オケでまた奏されるくつろいだ優しげな部分
が同じバラバラさで出てくる。違うのは、呈示部よりもっとピアノの受け持つ割合が増えて
いること、さらにくつろいだ部分で、オケのソロバイオリンが個人的ロマンスを想わせる調
子で絡むことぐらいである。
そして、その甘い雰囲気をバラバラにする感じで、また序奏の厳しい音楽が、激しく割り込
んできて直ぐ、ピアノ独奏のカディンツアになる。序奏部分のような重厚なピアノの低音の
響く和音をドンドンと鳴らした後、順序どうり、最初の切ない旋律を軽く予告程度にはさみ、
次にくつろいだ旋律までを、はじめてピアノが華やかな感じで弾き、カディンツアの最後に
1楽章全体の結論みたいにオーケストラ全体を圧する感じで、さっきの切ない旋律を最もエ
ネルギッシュな格好にして弾く。そこに、すぐオケがヴィヴァーチェで序奏の音形からくる
音楽を奏しだし、ソロのピアノを引きさらい、飛んでいくように終わる。
だから、この1楽章のながれは、序奏の厳しいカンジの音楽、直ぐ続く、その反対の切ない
ようなロシア的旋律、それから、くつろいだ感じの音楽という、分裂したような音楽の流れ
が、薄い感じの展開部を除くと、3回繰り返すことで、気分をつなぐような部分もほぼなく
、分裂を、意図的により濃縮して強調している構成になっている。
このバラバラさ、というものを考えるには、ちょっと、例として随分奇妙になるかもしれな
いが、参考までに云い足せば、同じようにトッカータみたいな部分がはじめに、出てくる月
光ソナタでも、旋律的な次の主題は、和音連打的な主題に連続的に移って行くし、再現部以
降、でも 呈示部でのそうした流れに加えて、減和音のアルペジオの激しい音があって、コ
ーダもそれを連続的に発展したもので、その主題が低音に行き、より刻んだ動きの中、旋律
が跳ねるようなオクターブで鳴り、大きなアルペジオ、右手の独奏部分?また旋律が戻って
きての、両手の上昇する和音の渦での終わり、という連続し、発展する気分の大きな部分が
あり、この中に冒頭のトッカータのような動きが何度も、挟まれたらどうなるか?というの
を想像してみると、近いかも知れない?
ただ、この中で発展的なのは、独奏ピアノの役割で、最初は序奏部分だけが主導して、第1
の旋律も第2の旋律もオケ主導。再現部では、序奏の音形をピアノが弾いた後、第1の旋律
も、ピアノで弾き出すが、第2の旋律は主としてオケ。カディンツアでピアノが3つの部分
全部引き受け、とくに最後に第1の旋律を情熱的に弾くわけで、役割が増大していること。
このことは、ピアノの独奏者が、ビルテュオーソ的なものを典型的に示す立場のものである
のを、考えるならば、以下のような”思想”を、読みとることは決して不可能ではない。
これは、外部世界に対して、厳しく自らを、意志的に律して始めた者が、外部世界の非意志
的、感傷的、大地的?優しさに触れて、そこに少し身を委ねようとする。そこでくつろげる
ことになることで、ある勝利感すら得られるが、直ぐに外部世界のもう1面の厳しさが噴出
して、打ち砕かれる。そこで、その者の視点は、遠くに移され、どこか遠くを彷徨うように
動いて後、また 意欲をもって戻ってくると再現部では、呈示部より、もっと積極的に非意
志的なものを認められ、くつろいだ中に、さらに個人的ロマンスさえ見いだせるようになる。
しかし、外部世界はまた試練の側面を噴出させ、雰囲気を打ち壊す。しかし、個人はそれに
答え、今まであったものに対して、すべて自分一人で、対応できることを示し、元々厳しく
自らを律する者であった、その個人は、反対の存在であるような感傷的な非意志的な優しさ
の旋律すらも、力強く肯定できるようにまでなっていることに到るが、そのある種の勝利は
、本質的関連性によって形成された物でなく、本質的にバラバラで、単に肉体的なまでの個
人的技芸に過ぎないから、すぐ一時的な物として崩壊して、永遠のような流れの中に消えて
しまう。・・・・・
こういった”ビルティオーソ的なものの諸相”は、大雑把にいえば、19世紀の以降の産業
社会の専門家、分業化における鍛錬した”有能な人々”の持つ問題から、の”芸術分野”に
おける一つの派生形態といえ、例えばドイツにおいては、 ”ワグネリアン”の格好をとっ
たもののは一つの顕れでもあり、やはり、ベックリンの『死の島』も、その類に属す、社会
全般の大きな傾向が、反映したものということが、理解されねばならない。
(ついでにいえば、アドルノらのオデュッセウスのとらえ方は、もうひとつ拡がりに欠け、
非常に西欧的な視点ともいえるもの。2003/4/25)
ただ、ロシアにおいては、単なる”専門家”という以上の、芸術的肉体的技芸、すなわち、
代表的には”演奏家”という形をとったため、ある単純な肉体的統一、勝利の現象を含めた
このラフマニノフでの”ビルテュオーソ的なものの諸相”の考え?に通じていると、考えて
良いだろうと思う。
バイロン・ジャニスの第1協奏曲の演奏の面白さは、ある”専門家”としての芸術的肉体的
技芸の、感覚がストレートに顕れた、それは演奏者としての資質が全体的に上手くあってい
ることからくることで、あるイミで演奏者としてのラフマニノフ以上に、語り口の音楽とは
言えないタイプで、1楽章でもカディンツァ辺りの輝かしいな鳴り方ばかり、耳に残って余
り全体を考えさせない。
しかし、この曲の複雑な情緒構造、一見 全く意図的でないように見える意図的な作られ方
を、考えた場合、こういった曲は、本来、聴取者のためにも「語り口」を、強く要求してい
る作品といえると思う。
トムソン・シェリー盤は、少々固い感じがするくらい、(この盤の場合は必ずしも悪い意味
でなく)各部分の旋律のつながりをきっちり鳴らし、オーケストラも、ソロと対等な存在感
で、拮抗するから、この曲の本質的な対照性が明確になるし、曲の部分的構成がはっきりす
るから、得体の知れないような不思議な、この曲の魅力の骨格をぼんやりさせない。
第1楽章に、比較して短い2,3楽章の演奏も、軽く扱わず、同様にきっちりとした演奏を
して、余分な部分に注意を惹いたり、妙にもっともらしく敷居を高くする、高尚ぶった表現
もしないので、北欧風の叙情の音楽と、フレンチカンカン風のけたたましい対比性もまた、
1楽章の内部の対比性の各々延長にあるもの、自己相似形を拡大している重要な形式的問題
もストレートに、見えてくる。
ソフロニツキやホロビッツが、スクリャービンのピアノ曲でやっているような「語り口」で
は、全くなくて、几帳面すぎるくらいの感覚だが、この曲の隠された意味を浮き立たせてく
れると言う点では、とても、”別種の”優れた”語り口”の演奏でもある。
実際、私の、この協奏曲のこれまでの描写をみて、連想された人もいたかも知れないが、ヴ
ォーン ウィリアムスの第4交響曲の終楽章の、あの半音的主題の闖入するような扱いと、
この協奏曲の序奏の主題の扱いは、似たところがあるし、第4の第1楽章の俯瞰的視野のよ
うな情緒的構造は、やはり、その意図的な作曲のされ方において、随分共通性があることも
、このトムソン・シェリー盤の、群を抜いたような捉え方を、可能にしている理由のひとつ
かもしれない。 (2003/4/18ここまで)
ところで、こういった全く歌詞も何も付けられていない音楽について、先程のような”意味”
の(特に白抜き字の部分など)”解釈”などを、書いてしまうと 読んだ人たちの中には、こ
の曲を何度も聴いたけれども、自分はそんな”言葉”など、思いもしなかったし、大体、その
ような解釈みたいなものは、随分 押しつけられているような不自由な感じがする、と思う人
も やっぱりいるだろう。
とはいえ、私が書いた先程のような言い方は、まず、このような文章において、まとまった形
に、一応 何とか工夫して説明しようとして、ココで出てきた言葉に過ぎないので、このよう
な”言葉そのもの”を、他の人が思い浮かばないとしても、全く何の不思議もない。
しかし、そうかといって何でもいいのか?というと、まるでそうでない。
こういったことには、次のページの枠内に(ちょっと本文の主題から、離れる感じなので)書
いた文章で、答えとしたい。こちらのページ
次は、第4協奏曲の1楽章について、・・・・・・〈 NEXTページへ、〉
うな人物?について、まず制作年代の近い『聖なる森』(1882)という絵があってその絵は
、顔の描かれないそういった風体の人物たちが森で祈っているから、『死の島』での人物?
も、ひとつは、修道士みたいなものだろうと想像される。
また、ドレスデンに長く住み、そこで亡くなったフリードリッヒ(1774-1840)には、『海辺
の修道士』(1810頃)という絵があり、中央に小さな後ろ姿の長い衣を着た人物が、広大な
灰色の海辺の空間の中に描かれた有名な作品。 ベックリンは、スイス生まれで、絶えず
イタリアの南方に憧れた画家だったが、ドイツで絵の勉強をし、認められた画家で、50年
位前の世代のドイツ絵画の似た傾向をもつフリードリッヒを、当然意識したろうから、『死
の島』の真ん中の人物のようなものと『海辺の修道士』の関連は考えても良いであろう。
また、フリードリッヒは、ターナー(1775-1851)、コンスタブル(1776-1837)と殆ど同世代
で、あるイミ、同様に非古典的、非ルネッサンスの”風景の画家”であり、また ベートー
ヴェン(1770-1827)と同時代人でもある。 『海辺の修道士』は、ターナーの『Light and
Colour』と同じく、もう既に”抽象絵画”すれすれの作品で、そういった類の”進歩観”に
よるなら、ホイッスラー『花火』やゴッホの『烏の群れ飛ぶ麦畑』に先んじているともいえ
る。また実際、『海辺の修道士』の中央の小さな人物を除けば、灰色の分割された色面でし
か無く、そう観るなら、ジャクソンン・ポロック辺り( Bニューマンなど、例は、この類のもの何でも
別にいいけど・・2003/5/12付記)とも、大差ない。
ベックリンは、そういう”抽象”の方向に進まず、顔の見えない人間を残し、より意図的な
”形態”群の中に、一つとして置いた。この流れの方向が、ジョルジョ・デ・キリコ(1888
-1978)にも、つながっていったとも考えられ、キリコは、自らその影響を認め、『ベック
リン論』を書いているらしい。
そして、その影響関係の代表的例として、よく挙げられるのがベックリン『オデュッセウス
とカリプソ』(1882)とキリコの『神託の謎』(1909)の関係になる。ベックリンの絵画を、
もっと深く考えてみようとするとき、この2つの絵のことを参考にすると、とても役に立つ
のである。
例えば、ベックリンのこの絵にも、例の長い衣を着た後ろ姿の人物が重要な存在として、登
場してきている。この絵の場合、登場人物の関係と話しは、結構 はっきりしている。
後ろ姿の人物は、オデュッセウスで、彼はトロイア戦争で活躍して後、本国イタケに帰ろう
とするが、様々な困難に遭いなかなか帰国できない。その途中に、絵の右側の洞穴の前にい
る、美しい女性として描かれた妖精カリュプソの島に、難破したオデュッセウスは唯1人漂
着する。カリュプソは、親切に世話をしているうちに、オデュッセウスをとても好きになっ
たので、何とか引き留めようとする。
そこで”不死性”を与えるから留まって、とまでカリュプソは、申し出る。しかし、イタケ
で待つ、妻子の元に帰ろうとする固い決心を、オデュッセウスは変えないし、ゼウス神も、
帰してやれ という神託の命令を下したので、仕方なくカリュプソは、筏を与えて、帰国を
許す・・・
という話し。
(もっと細かく言うと、ややこしくなるが、ゼウスの意思を、直接 伝えているのは
ヘルメスで、一応直接は、頭部は、この伝令神のものになる・・・付記2005・7・28)
このベックリンの絵で特異なのは、そっぽを向いて、固まった岩のようなオデュッセウス、
(そして、それは、『死の島』での先程言った、”修道士”みたいな存在と大変よく似たも
のであることにも、当然注意して置いてほしいが)彫像のような優美なポーズを取るカリュ
プソと、何かバラバラの不可思議なムードがあることだが、そのことに関して、デ・キリコ
の『神託の謎』が、重要な参考になる。
キリコは、ニーチェ哲学に影響を受けているのは明らかだし、彼が広場で倒れたトリノの町
を1911年訪れ、強い印象を与えられ、そのイメージは絵に残されている。また、ヴァイニン
ガーとシュペングラーの本も、好んで読んでいたという。彼が、実際 絵についてどんな説
明をしたかとは、絵描きが、いちいち種明かしをして回るとは限らないから、その書いてい
ることを単純に受け取るより、まず、絵自体を見た方が良い。
『神託の謎』は、一見 全く謎めいた作品で、通常解説もベックリンの絵に対しての、関係
に触れる程度で、全くぼんやりした説明がなされているだけのように思う。
(ついでに、言っておくと、少なくとも日本の場合、音楽の分野では、その作品の意味内容に関する言語
表現が、臆病なまでに抑えられているか、音符的訓練に関して同じ様な話しばかり繰り返される他は、
非常に素朴な情緒の言語表現が与えられるだけみたいであり、一方、美術の分野では、その作品の意味
内容に関する言語表現が、”抽象的表現”などで、いたずらに膨らまされて、何も言っていないかんじ
になったり、また、やたらと西欧の美術表現には、固定したような”実証”できる修辞的語法が、歴史
的に存在したと思い込もうとしている、というような共に空虚な言語表現が溢れる状態になっていて、
分野で極端な違いが起こってしまっていることは注目に値する。)
私が思うに、この絵は”オデュッセウスとカリュプソ”という2人の真の関係を、解説して
いるのであって、すなわち、本当はカリュプソは、何でも良いのであって、真の関係は、カ
ーテンから、頭を出しているゼウスとオデュッセウスとの2者関係であり、愛し合っている
ように見える2人は、厚いベールで隔てられている。カリュプソは、”永遠の生”この場合
”永遠の愛”を約束しようとするが、恋人たちの意志、働きかけと無関係に、バラバラにな
ってしまう。目の前に見える甘美な愛は、オデュッセウス的本来の意志を、覆させることは
出来ない。というのも、オデュッセウスの意志は、本来、ゼウス神の意志であり(だから、
キリコの絵では、ベックリンの絵以上に後ろ姿の人物の”頭”が、欠けているように描かれ
ている。)彼は盲目の身体的固い意志で、故郷イタケに戻ろうとする訳で、頭はゼウスにあ
るのである。(ちなみに、キリコの絵では、後ろ姿の人物が、向かっている方向には、キリ
コの幼くして去ったギリシャのアテネの街が遠景で描かれているらしい)
近くにいると見える2人が、永遠なまでの”見えない隔絶した関係”を隠して並んでいる。
『死の島』でも、この解釈は参考になって、この絵は、後ろ姿の人物と、そのボートが向か
っているはずの、「死の島」との”本質的に隔絶した関係”が、問題となっていると考えら
れる。というのは、固まったようなオデュッセウスとカリュプソの間に、不可思議な断絶が
の雰囲気が、感じられたように、この島に向かう人物と、島の間には、ごく普通のボート遊
びのレジャーを楽しもうとする人と、その人が渡ろうとしている、どこか現実の島、といっ
た場合にある日常的文脈の”行動と目的”という雰囲気が、全くない、何か得体の知れない
”関連もしくは断裂”の雰囲気が重要なのである。
すなわち、ボートに乗った人物は、身動きもせず白い布に包まれ、生きたものかも判らない
遮断された存在で、ただパートナー的な女性が、ボートを漕いで運ぼうとしているだけで、
また、目的地である島も、通常 目的になりそうな望ましい感じでなく、糸杉がそびえる何
か死の匂いのする所であり、また、一方大事なことは、必ずしもそんなネガティヴだけのも
のでもなさそうなことで、例えば、蓬莱島ではないが、穏やかで静かな雰囲気は漂っている
し、島と融合したような見事な建造物は、人間の人工的構築物と自然の融合みたいなもので
もある。
だから、島と後ろ姿の人物との関係は、”行動目的と行動する人”という普通の関係でなく
むしろ、”オデュッセウスとカリュプソ”のように”神”が、真の関係を作っている。もし
くは、オデュッセウスのように厳しく意志を貫こうとする身を固めている人物、もしくは、
修道士のような人物(白黒の違いは別に考える必要はあるけど)が、緩やかな波のボートの
甘い戯れの気分に身を委ねながらも、本質的に”遮断された”存在であり、また、自ら ボ
ートを漕ぎ向かうのでなく、たまたまのパートナーに任せて漂うように進む過程の存在。そ
して、島と後ろ姿の人物は、一方で、強くつながっているのであって、それが目的地のよう
でもあり、「死」「消失」のようでもある場所、点、に何らかの力、関係によって操られる
ように進んでいく有様にもなる。
そして、ここから、ラフマニノフの一見 唐突でバラバラなムードを持つ、1番ピアノ協奏
曲の構成を、想い出してもらえば、その不思議な謎めいたような魅力を含めて、改めてとて
も近いことに、気付かないだろうか?
もちろん、ベックリンの絵の『死の島』の、ある重苦しい静かなような雰囲気や、怪奇映画
のようなイメージは、第1番ピアノ協奏曲には、あんまり無いし、交響詩『死の島』では、
もっぱら、そんな表面的イメージが再現されているが、一方、ベックリンの絵の『死の島』
を、想い起こす雰囲気は、交響曲2番なども含めて広い範囲で存在していること自体が重要
で、そう考えるならば、ラフマニノフの、感受性の半面の、ある基本的な態度である何か根
本的な次元が、問題になってくるだろう。
ラフマニノフの第1番ピアノ協奏曲と、ベックリンの絵の『死の島』の先程、少し詳しく触
れた”内容”みたいなものと、一番 違うところは、修道士もしくはオデュッセウス的存在
が、ロシア的ヴィルテュオーソ的存在として、もっと諸相に展開されて、”内容”に関わっ
ていることで、その他は、ほぼ重なった感じにすら見えてくる。
ここで、いままで書いたことを、繰り返すのに 少々近くなる部分もあるが、全て通してま
とめてみることは、必要なので《 協奏曲1番1楽章全体の流れ 》を、前に書いた部分より、
新たに付け加えた視点による見方を含めて、改めて書いておこう。
すなわち、まず、曲頭のファンファーレによって誘い出され、ピアノは非常に厳しい調子の
下降する序奏の音形を弾き出す。これは、独奏者の側の基本的立場といえるものでもあるが、
そこに独奏者に対する外部世界であるオーケストラは、非常にロシアの大地的?民衆的?と
いえるような切ない感じの対照的旋律をぶつけてくる。
その切なさに、対しても独奏ピアノは、やはり従わねばならないというように、しおらしい
感じで旋律を受け継ぎ、調子を合わせる。その音楽は、そのままの感じでは進まず、気散じ
で歩き回るようなピアノ部分を挟む、そこからやっとくつろげるような第2主題といえるよ
うな安らいだ音楽をオーケストラから得、そこからピアノはある種の勝利感を感ずるような
興奮した短い部分を奏する。
が、そこに安易な勝利感を打ち消すように、今度はオケが、序奏の厳しい音楽を激しく奏し
て、さらに、最初の旋律の部分が変形され、厳しい感じになり、序奏の要素も加わったりし
て、それが突き進む感じで展開され、曲頭に対応するようなファンファーレが、現れるとこ
ろまでオーケストラだけで行く。そこで折り返すようにピアノが戯れ止まって回転するよう
な軽い音楽となった後、最初の旋律が遠い感じでソロの管で鳴り、その旋律の最初の部分が
だんだん想い出されてくる感じで、繰り返され大きくなる。ここの展開部全体でもまとまっ
た重量感のある存在でなく、とくに展開部の後半は薄く遠い感じで、続く、1楽章の呈示的
部分のほぼ繰り返す部分と対照的な、”何か向こうの場所”になっていて、そこでは対立的
な序奏の固い感じの部分と最初の切ない旋律の部分が何か融合したようでもある。
そこでまた、ピアノ独奏の動きが激しくなった頂点に、序奏の厳しい音楽が半音階的な速い
動きで引き裂くように又割り込んできたあと、すぐ、最初の切ない感じの旋律を、呈示部と
違って、いきなりピアノ独奏で、そして前よりは力強い感じで弾き、そして、曲の構成とし
ては、後は呈示部と殆ど同じで、発展された要素があるというより、そのまま少し短縮した
感じで、続く、気散じの歩き回るような部分、オケでまた奏されるくつろいだ優しげな部分
が同じバラバラさで出てくる。違うのは、呈示部よりもっとピアノの受け持つ割合が増えて
いること、さらにくつろいだ部分で、オケのソロバイオリンが個人的ロマンスを想わせる調
子で絡むことぐらいである。
そして、その甘い雰囲気をバラバラにする感じで、また序奏の厳しい音楽が、激しく割り込
んできて直ぐ、ピアノ独奏のカディンツアになる。序奏部分のような重厚なピアノの低音の
響く和音をドンドンと鳴らした後、順序どうり、最初の切ない旋律を軽く予告程度にはさみ、
次にくつろいだ旋律までを、はじめてピアノが華やかな感じで弾き、カディンツアの最後に
1楽章全体の結論みたいにオーケストラ全体を圧する感じで、さっきの切ない旋律を最もエ
ネルギッシュな格好にして弾く。そこに、すぐオケがヴィヴァーチェで序奏の音形からくる
音楽を奏しだし、ソロのピアノを引きさらい、飛んでいくように終わる。
だから、この1楽章のながれは、序奏の厳しいカンジの音楽、直ぐ続く、その反対の切ない
ようなロシア的旋律、それから、くつろいだ感じの音楽という、分裂したような音楽の流れ
が、薄い感じの展開部を除くと、3回繰り返すことで、気分をつなぐような部分もほぼなく
、分裂を、意図的により濃縮して強調している構成になっている。
このバラバラさ、というものを考えるには、ちょっと、例として随分奇妙になるかもしれな
いが、参考までに云い足せば、同じようにトッカータみたいな部分がはじめに、出てくる月
光ソナタでも、旋律的な次の主題は、和音連打的な主題に連続的に移って行くし、再現部以
降、でも 呈示部でのそうした流れに加えて、減和音のアルペジオの激しい音があって、コ
ーダもそれを連続的に発展したもので、その主題が低音に行き、より刻んだ動きの中、旋律
が跳ねるようなオクターブで鳴り、大きなアルペジオ、右手の独奏部分?また旋律が戻って
きての、両手の上昇する和音の渦での終わり、という連続し、発展する気分の大きな部分が
あり、この中に冒頭のトッカータのような動きが何度も、挟まれたらどうなるか?というの
を想像してみると、近いかも知れない?
ただ、この中で発展的なのは、独奏ピアノの役割で、最初は序奏部分だけが主導して、第1
の旋律も第2の旋律もオケ主導。再現部では、序奏の音形をピアノが弾いた後、第1の旋律
も、ピアノで弾き出すが、第2の旋律は主としてオケ。カディンツアでピアノが3つの部分
全部引き受け、とくに最後に第1の旋律を情熱的に弾くわけで、役割が増大していること。
このことは、ピアノの独奏者が、ビルテュオーソ的なものを典型的に示す立場のものである
のを、考えるならば、以下のような”思想”を、読みとることは決して不可能ではない。
これは、外部世界に対して、厳しく自らを、意志的に律して始めた者が、外部世界の非意志
的、感傷的、大地的?優しさに触れて、そこに少し身を委ねようとする。そこでくつろげる
ことになることで、ある勝利感すら得られるが、直ぐに外部世界のもう1面の厳しさが噴出
して、打ち砕かれる。そこで、その者の視点は、遠くに移され、どこか遠くを彷徨うように
動いて後、また 意欲をもって戻ってくると再現部では、呈示部より、もっと積極的に非意
志的なものを認められ、くつろいだ中に、さらに個人的ロマンスさえ見いだせるようになる。
しかし、外部世界はまた試練の側面を噴出させ、雰囲気を打ち壊す。しかし、個人はそれに
答え、今まであったものに対して、すべて自分一人で、対応できることを示し、元々厳しく
自らを律する者であった、その個人は、反対の存在であるような感傷的な非意志的な優しさ
の旋律すらも、力強く肯定できるようにまでなっていることに到るが、そのある種の勝利は
、本質的関連性によって形成された物でなく、本質的にバラバラで、単に肉体的なまでの個
人的技芸に過ぎないから、すぐ一時的な物として崩壊して、永遠のような流れの中に消えて
しまう。・・・・・
こういった”ビルティオーソ的なものの諸相”は、大雑把にいえば、19世紀の以降の産業
社会の専門家、分業化における鍛錬した”有能な人々”の持つ問題から、の”芸術分野”に
おける一つの派生形態といえ、例えばドイツにおいては、 ”ワグネリアン”の格好をとっ
たもののは一つの顕れでもあり、やはり、ベックリンの『死の島』も、その類に属す、社会
全般の大きな傾向が、反映したものということが、理解されねばならない。
(ついでにいえば、アドルノらのオデュッセウスのとらえ方は、もうひとつ拡がりに欠け、
非常に西欧的な視点ともいえるもの。2003/4/25)
ただ、ロシアにおいては、単なる”専門家”という以上の、芸術的肉体的技芸、すなわち、
代表的には”演奏家”という形をとったため、ある単純な肉体的統一、勝利の現象を含めた
このラフマニノフでの”ビルテュオーソ的なものの諸相”の考え?に通じていると、考えて
良いだろうと思う。
バイロン・ジャニスの第1協奏曲の演奏の面白さは、ある”専門家”としての芸術的肉体的
技芸の、感覚がストレートに顕れた、それは演奏者としての資質が全体的に上手くあってい
ることからくることで、あるイミで演奏者としてのラフマニノフ以上に、語り口の音楽とは
言えないタイプで、1楽章でもカディンツァ辺りの輝かしいな鳴り方ばかり、耳に残って余
り全体を考えさせない。
しかし、この曲の複雑な情緒構造、一見 全く意図的でないように見える意図的な作られ方
を、考えた場合、こういった曲は、本来、聴取者のためにも「語り口」を、強く要求してい
る作品といえると思う。
トムソン・シェリー盤は、少々固い感じがするくらい、(この盤の場合は必ずしも悪い意味
でなく)各部分の旋律のつながりをきっちり鳴らし、オーケストラも、ソロと対等な存在感
で、拮抗するから、この曲の本質的な対照性が明確になるし、曲の部分的構成がはっきりす
るから、得体の知れないような不思議な、この曲の魅力の骨格をぼんやりさせない。
第1楽章に、比較して短い2,3楽章の演奏も、軽く扱わず、同様にきっちりとした演奏を
して、余分な部分に注意を惹いたり、妙にもっともらしく敷居を高くする、高尚ぶった表現
もしないので、北欧風の叙情の音楽と、フレンチカンカン風のけたたましい対比性もまた、
1楽章の内部の対比性の各々延長にあるもの、自己相似形を拡大している重要な形式的問題
もストレートに、見えてくる。
ソフロニツキやホロビッツが、スクリャービンのピアノ曲でやっているような「語り口」で
は、全くなくて、几帳面すぎるくらいの感覚だが、この曲の隠された意味を浮き立たせてく
れると言う点では、とても、”別種の”優れた”語り口”の演奏でもある。
実際、私の、この協奏曲のこれまでの描写をみて、連想された人もいたかも知れないが、ヴ
ォーン ウィリアムスの第4交響曲の終楽章の、あの半音的主題の闖入するような扱いと、
この協奏曲の序奏の主題の扱いは、似たところがあるし、第4の第1楽章の俯瞰的視野のよ
うな情緒的構造は、やはり、その意図的な作曲のされ方において、随分共通性があることも
、このトムソン・シェリー盤の、群を抜いたような捉え方を、可能にしている理由のひとつ
かもしれない。 (2003/4/18ここまで)
ところで、こういった全く歌詞も何も付けられていない音楽について、先程のような”意味”
の(特に白抜き字の部分など)”解釈”などを、書いてしまうと 読んだ人たちの中には、こ
の曲を何度も聴いたけれども、自分はそんな”言葉”など、思いもしなかったし、大体、その
ような解釈みたいなものは、随分 押しつけられているような不自由な感じがする、と思う人
も やっぱりいるだろう。
とはいえ、私が書いた先程のような言い方は、まず、このような文章において、まとまった形
に、一応 何とか工夫して説明しようとして、ココで出てきた言葉に過ぎないので、このよう
な”言葉そのもの”を、他の人が思い浮かばないとしても、全く何の不思議もない。
しかし、そうかといって何でもいいのか?というと、まるでそうでない。
こういったことには、次のページの枠内に(ちょっと本文の主題から、離れる感じなので)書
いた文章で、答えとしたい。こちらのページ
次は、第4協奏曲の1楽章について、・・・・・・〈 NEXTページへ、〉
◆HOME ◆BACK
|