:AB・・・・ヴァイオリン協奏曲
VIOLIN CONCERT (1939)
1)ヴァイオリン協奏曲 w ウォルトン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 ヤッシャ ハイフェッツ(vn)
(RCA)

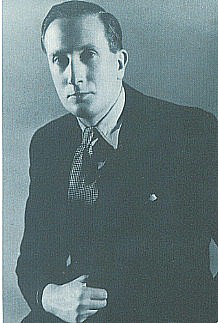 ”Jascha Heifetz(1901-87)”
J・ハィフェッツ の依嘱により、
彼の独奏用に1939年作曲されたこ
のVn協奏曲は同年12月7日にク
リーヴランドでロジンスキー指揮
で初演。最初の録音は41年シンシ
ナチー響 で ユージングーセンス
の指揮で行われた。そしてハイフ
ェッツは 1950年7月26日ウォルト
ン 自身の指揮で再録音している。
この曲は当時すでに神格化されて
いたヴァイオリニスト のための
作品で、またWWは本来 演奏家
の名技性にも馴染み易いタイプの
作曲家といえ、初演の際JHに対
して 演奏上不都合な点があれば
手を加えても構わないとの手紙も
書いている。これなど 当時のJHの名声のためもあるかもすれないが WWは、
のちにオペラ「トロイラスとクレシダ」でも、初演の版を、現実的なソロ歌手に
応じるため ”改良”を行っており、この種の”実際的感覚”は WWのひとつの
特徴といえる。この協奏曲の出版譜にもカディンツアなどでYHの助言を受け入れ
ているという。ハイフィッツが初めの録音盤を作った後、現在普通に演奏される
改訂版が1943年にできている。この版の演奏というだけでなく50年の自作自演に
よる再録音は、グーセンスとの最初の録音の演奏自体にも原因はあったろうと思
われる。 (⇒ 注※※:参照 2002/10/30)
たしかに、2楽章全般そして3楽章の、カディンツに至るぐらいまでのあいだハイフェッツらしい輝かしい音が聞かれは
するが、1楽章のコーダで、バイオリンの息の長いメロディーをフルートとファゴットが十八分音符でリレーして縁取る
部分がせわしい。また肝心のVnの重音の効果的な長いフレーズのあと展開部の頂点で勢いづいたオーケストラが
sub.vivaceで8分の6、8分の9、8分の6、 8分の12、8分の5、8分の3、8分の5、8分の12、8分の6、8分の9、8分の12、
4分の4と不規則的に頻繁に拍子を変える部分があるのだが、ここはストラビンスキーらの流行に近い感覚というより、
ウォルトンの大変特徴的な渦巻きの音楽を作り出しているところである。拍子の作る均質でない時間感覚も、優美な第2
主題を舞曲の簡単なシーソーの格好のバスの3拍子で伴奏した箇所より、ソロとオーケストラが交叉し合い情緒を発展させ
効果的な重音奏法で頂点を迎え、一旦収まったかのような所の直後、音の渦へと流れ落ちるまでの重要な締めくくりである
この部分を生むスリルの大きな要素になっている。(ウォルトンほど鋭く力強い渦巻きの音楽を書いた作曲家はいない・・
、全楽章の全体に増大していくエネルギーのような曲想からみてもその重さを感じなければならない。こういうところを
単に通俗的効果を高めるように受け取ったり、また軽く扱ってしまうのは非常にありがちな反応なのではあるが・・)
こういったところがグーセンスだと突発的で、リズムも均整な感覚にどちらかと言えば、整理されてしまっているようで
もある。例によって短くされ、そして劇的に流れ込む再現部、その終わりのフルートからファゴットの縁取りが続くなか
ハープがEとBの和音を4小節にわたって繰り返すところの45年のスコアでppで書かれている部分も、たいして意味を持た
ないチェロのピッチカートと出来る単調なリズムがむしろ息抜きのように強調して繰り返されるカンジになる。3楽章の練
習番号69-72にかけての最後のカデンツァを導くオーケストラの序奏めいたところも投げやりの勇ましさで、とくに打
楽器音が締まりがなく聞こえて 作曲家としては不満を感じたであろう?→(注 下)
。ある程度最初の録音の特徴は一貫性の無さ そして 簡単に言ってしまえばオーケストラは”伴奏"的演奏の傾向がある。
といっても、これは誰も知らない曲を演奏したグーセンスだけの問題というより 求めるソリスト側の原因も考えてみる
べきであろう。指揮者の考える曲の全体的プランと 演奏者が気持ちよく演奏し易いフレージング、息継ぎ は、もともと
一致しにくいし、むしろ ”矛盾”しつつ生成する。・・というところがある。
(もちろん、双方が無個性で機械的にやれば大して問題にならないことも多かろうが・・・2002/10/30)
ハイフェッツの晩年は、自ら弓を振りつつ指揮するのを好んだし、早く世に出たJHがいた20世紀の初めの”音楽学校”
(必然的に横繋がりもの・・)が「クラシック」音楽の土壌を完全に支配する前の楽団の経営は、興行師的な色彩が現在
より強かったことはいろいろ想像できるし それは”スター”に寄りかかった演奏に容易に重なる体質でもある。
41年盤の1楽章の前半でも非常に美しい曲線でVnが音を描いて見せるが、オーケストラはモンヤリと鳴るだけで済まして
いるかんじとなる。今世紀の他の”巨匠級”の演奏に比べても、むしろハイフェッツの演奏にはこのカンジのものがより、
目に付くようだ。それはJHの好み以上に両者の力関係や立場に果たしたJHの特別な位置が反映している可能性がある。
1920年のJH初のロンドン公演のあと、バーナードショーが、わざわざ手紙を送り「・・あんなに超人的な完成した
演奏をしたら、嫉妬深い神さまを怒らせ、あなたは若死にしますよ。・・毎晩ベッドに入る前に、お祈りをする代わり
に何かを下手に弾く事にしなさい。人間はあんな完全無欠に弾く大それたことはしてはならないのです。・・・・・」
と書いたそうだが、GBSは若い時 音楽批評をもっぱらやっていた時期もあったくらいで、単なる”スノッブ”ではなく、
音楽と共通する感受性を根本的にもっていたひとでもあるから、そう感じられるような演奏を実際したのだろう。が、
それ以上にジャーナリズムの効果をよく知り、狙ったこういった表現が 無意識的であれスノッブなものを作り出す。
ハイフェッツの”完璧性”という言い方は、多分に社会のフェティッシュなものを反映していることを考えねばならない。
合衆国の世界的ヘゲモニーのシンボルとして、トスカニーニー以上に物質的な固定性を持たされる必要があった。
現代奏法を確立したともいえるJHの演奏は、ある割り切りと徹底性の印象でもある。が やはり いつどのような場合でも
というのは誇張であり、LVBのVn協奏曲をはじめ、メンデルスゾーン、モーツアルトといった”定番メニュー”と
ロマン派的といっても そのうちのヴィアニャフスキーやブルッフといったある職人的なレパートリーには、たしかに、
これ以上のものを考えにくくする録音が残っている一方、その種のもの以外においては必ずしもそうでもなく、関心の
褪めた部分にそれなりの対応で済ます傾向があるのは否定できない。
むしろ、JHが”絶対性”のようなものを発揮するのは、ある”古典的””職人的”なものに限られるといった方が正しい
と思われる。バッハの無伴奏ソナタとパルティータ全曲のレコードの大きな成功が、「完全性」の印象を強めたには違いない
が、それでも1930年代にそれのみ録音された1と3のソナタの方が、明らかにJHは得意なのである。(とはいえ最近の
日本などではこの曲のもっと”もったい”をつけた演奏の方がありがたがられる傾向があるが・・・)
WWのVn協奏曲は、その種の曲に属さない。WW自身が指揮した1950年盤は、実際 旧盤の欠点は大きく改善されている。
オーケストラ部分がしっかり音楽に参加し、変な強調やバランスの悪さはなくなり、結果として一貫した流れが出来ている。
しかし、WWとの50年の演奏が最初のものと比較して文句無く優れているという訳でもない。41年盤の自発的なヒロイズム
に似たひらめきは薄まり、そもそもJHの「技巧」の完結性を願う体質と この協奏曲の執拗な意味の表出を迫る展開は
かならずしも一致しない。作曲家の自作自演の価値とは、しばしば問題となる話なのだが、ある場合 絶対化され易いし、
一方で作曲家の思考を無視した”浅薄な"演奏は常に行われてきた。
勿論 作曲家が作品に対する ある理解 をより持っている事は確かであろう。とはいってもそれは全てではないのである。
一般に作曲家の指揮は、デリケートなフレージングや奏法による音色の大きな効果に十分な関心が乏しい事が多い。ストラビ
ンスキーやRシュトラウスのような一般に評判の良くない人だけでなく、常に高く評価され 決定盤扱いのベンジャミン
ブリテンのようなひとでもそうなのである。(その意味でも”謎の作曲家”ベンジャミンブリテンの影の側面はもっと開拓され
、解明されうる余地がある・・)このように書いてきたから、といってこの自作自演の歴史的な盤の価値が、低いといって
いるので全く無い。むしろ、今日 たくさん並ぶようになったこの曲のカタログにおいても群を抜いて優れたものの一つ
といっていい。WWはちゃんとした指揮の出来る人だし、JHの演奏は良く聴けばやはり、素晴らしいのである。ただ、
セルとWWのsymNo2の場合程の希な幸運な出会いが、もう少しのところで欠けているということなのだ。
【以上 1999月12月頃記す・・2002年5月に上から25〜30行程の部分、書き足す】
注※※・・・上の文章でも、そう書いているつもりだが、別にグーセンスが良くない演奏家という
話ではない。この辺りの事情は、本来 いろいろと詳しい資料を調べてみた方がはっ
きりしたことが云える。ただ大事なのはグーセンス指揮において、この協奏曲の演奏
は、それほど 演奏者の執着がない場合、割と良くあり得る傾向になっているのでな
いか?というようなこと。まず ウォルトンの音楽らしい独特な感じを出す難しさ。
そして、ちゃんとした説得力をもたせて十分に技術的なものをクリアするのは やは
り、大変困難と言っていいのだろう。2002/10/30
2) ヴァイオリン協奏曲 パーヴォ ベルグルンド指揮 ボーンマスsym orch イダ ヘンデル (Vn)
1978年録音・・・・
イダ・ヘンデルの演奏が鋭く(良い意味でも悪い意味でも・・)、20世紀のヴィルティオーソの重要な一
人であり、それが発揮された録音であることをさておくとしても、WWの曲の演奏を史的に考えた場合、
特筆すべきものといった方がよさそうである。
というのも、ここにあるのは それまでのウォルトンの作品の演奏にもっぱらあった、いわゆる英国風の
あるローカルな穏健さをもったもの、もしくは作曲者自身の演奏スタイル を離れて、ちょうど 戦後の
マーラーブームの”オーケストラサウンドを、聞かせるための素材として、利用する傾向”と同じもの
(例えば、ショルティーがマーラー5番でやったような・・)が見られるのでないか。もしくは、その
ような感受性を経た後で、始めてなり得たかもしれない発想の演奏?
また このコンビの演奏以来、それ以前のものに対してこの傾向は新たな目立った特徴となったのかもし
れない。 だから、(WWの)交響曲などの演奏においても、それ以後に取り組んだ他の指揮者たちのや
り方の中に発見できる新しい要素の発端といえるかもしれない。 また この録音が、作曲者自身の最晩
年となる時期とほぼ重なる事とも関係があるだろうか?・・
(EMI)
3) ヴァイオリン協奏曲 ウィリアムウォルトン指揮 ロンドンs,o ユーディーメニューイン(Vn)
♪♪ メニューインとウォルトンの交流・・・ (EMI)
4) ヴァイオリン協奏曲 アンドレプレヴィン指揮 ロイヤルフィル ナイジェルケネディー (Vn)
(EMI)
メニューインと同じように、ビオラもこなせる ケネディーは、ヴィオラ協奏曲 も一緒にいれたLPを
10年くらい前に出していた。いかにも若い彼の楽しそうな演奏で、従来の この曲の演奏のほとんど
どれにもあった重苦しさは、まるでない。プレヴィンもチョンキョンファと一緒の時は ハイフイッツ
盤を、意識したよく似たスタイルだったが、これはケネディーに合わせているのだろう。ケネディーは
イギリス出身ということだが、この頃は意識的に 古くさい重苦しさを排除して行きたいという気持ち
が強かったようだ。とはいえ、この演奏は つまらなく 出来の悪いものには なっていない。この曲
のイメージ一新は、それなりに成功している。3楽章のカデンツァの不思議なグリッサンドもこの演奏
全体には似合っている。明るく風通しは良いが、適当な緊張感は保たれ退屈はしない。最近のケネディ
ーは、これに比べるともっと重厚な感じの演奏をするようになったといえるのかもしれない。
最近のブラームスのニ長調協奏曲を、ベルリンPOとやったものなどは、充分それがあったのでないか?
ある意味 かっての名人たちのような重々しさ、と同時に独特の荒々しさで、大きな響きの流れで全曲
を引っ張っていって、 また十分な名技性で最後までこなして見せた。
そこには、かっての「巨匠」たちと確かに 大きく違うものが、彼にはあるようだ。 ある音楽自体の
独立した絶対的価値から、何か離れていきたいという気持ちを感じる。 だから、彼の場合 重々しく
あっても、どこか親しみやすさ、かみ砕いてくれている優しさが起こってくる。これはサイモンラトル
ととても良く似た傾向でもある。(・・ベルリンpoとの縁は、何か中世のスコラ的汎ヨーロッパの時代
を感じさせてしまうが・・)いずれにせよ、いろいろ既に持っている人にとっては付け加えて損はない
1枚?
(・・・勿論、ラトルもケネディーも資質的には ブリテン向きのヒトと付け加えておいたた方が良い
だろうけども・・・)
【2000年2月頃記す・・2002年9月文章上のミスを置き換え修正?】
← ◇Back → HOME◆
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
注)・・・・出版譜で、こういったパーカッションの削除他、が実際に行われている。
”Jascha Heifetz(1901-87)”
J・ハィフェッツ の依嘱により、
彼の独奏用に1939年作曲されたこ
のVn協奏曲は同年12月7日にク
リーヴランドでロジンスキー指揮
で初演。最初の録音は41年シンシ
ナチー響 で ユージングーセンス
の指揮で行われた。そしてハイフ
ェッツは 1950年7月26日ウォルト
ン 自身の指揮で再録音している。
この曲は当時すでに神格化されて
いたヴァイオリニスト のための
作品で、またWWは本来 演奏家
の名技性にも馴染み易いタイプの
作曲家といえ、初演の際JHに対
して 演奏上不都合な点があれば
手を加えても構わないとの手紙も
書いている。これなど 当時のJHの名声のためもあるかもすれないが WWは、
のちにオペラ「トロイラスとクレシダ」でも、初演の版を、現実的なソロ歌手に
応じるため ”改良”を行っており、この種の”実際的感覚”は WWのひとつの
特徴といえる。この協奏曲の出版譜にもカディンツアなどでYHの助言を受け入れ
ているという。ハイフィッツが初めの録音盤を作った後、現在普通に演奏される
改訂版が1943年にできている。この版の演奏というだけでなく50年の自作自演に
よる再録音は、グーセンスとの最初の録音の演奏自体にも原因はあったろうと思
われる。 (⇒ 注※※:参照 2002/10/30)
たしかに、2楽章全般そして3楽章の、カディンツに至るぐらいまでのあいだハイフェッツらしい輝かしい音が聞かれは
するが、1楽章のコーダで、バイオリンの息の長いメロディーをフルートとファゴットが十八分音符でリレーして縁取る
部分がせわしい。また肝心のVnの重音の効果的な長いフレーズのあと展開部の頂点で勢いづいたオーケストラが
sub.vivaceで8分の6、8分の9、8分の6、 8分の12、8分の5、8分の3、8分の5、8分の12、8分の6、8分の9、8分の12、
4分の4と不規則的に頻繁に拍子を変える部分があるのだが、ここはストラビンスキーらの流行に近い感覚というより、
ウォルトンの大変特徴的な渦巻きの音楽を作り出しているところである。拍子の作る均質でない時間感覚も、優美な第2
主題を舞曲の簡単なシーソーの格好のバスの3拍子で伴奏した箇所より、ソロとオーケストラが交叉し合い情緒を発展させ
効果的な重音奏法で頂点を迎え、一旦収まったかのような所の直後、音の渦へと流れ落ちるまでの重要な締めくくりである
この部分を生むスリルの大きな要素になっている。(ウォルトンほど鋭く力強い渦巻きの音楽を書いた作曲家はいない・・
、全楽章の全体に増大していくエネルギーのような曲想からみてもその重さを感じなければならない。こういうところを
単に通俗的効果を高めるように受け取ったり、また軽く扱ってしまうのは非常にありがちな反応なのではあるが・・)
こういったところがグーセンスだと突発的で、リズムも均整な感覚にどちらかと言えば、整理されてしまっているようで
もある。例によって短くされ、そして劇的に流れ込む再現部、その終わりのフルートからファゴットの縁取りが続くなか
ハープがEとBの和音を4小節にわたって繰り返すところの45年のスコアでppで書かれている部分も、たいして意味を持た
ないチェロのピッチカートと出来る単調なリズムがむしろ息抜きのように強調して繰り返されるカンジになる。3楽章の練
習番号69-72にかけての最後のカデンツァを導くオーケストラの序奏めいたところも投げやりの勇ましさで、とくに打
楽器音が締まりがなく聞こえて 作曲家としては不満を感じたであろう?→(注 下)
。ある程度最初の録音の特徴は一貫性の無さ そして 簡単に言ってしまえばオーケストラは”伴奏"的演奏の傾向がある。
といっても、これは誰も知らない曲を演奏したグーセンスだけの問題というより 求めるソリスト側の原因も考えてみる
べきであろう。指揮者の考える曲の全体的プランと 演奏者が気持ちよく演奏し易いフレージング、息継ぎ は、もともと
一致しにくいし、むしろ ”矛盾”しつつ生成する。・・というところがある。
(もちろん、双方が無個性で機械的にやれば大して問題にならないことも多かろうが・・・2002/10/30)
ハイフェッツの晩年は、自ら弓を振りつつ指揮するのを好んだし、早く世に出たJHがいた20世紀の初めの”音楽学校”
(必然的に横繋がりもの・・)が「クラシック」音楽の土壌を完全に支配する前の楽団の経営は、興行師的な色彩が現在
より強かったことはいろいろ想像できるし それは”スター”に寄りかかった演奏に容易に重なる体質でもある。
41年盤の1楽章の前半でも非常に美しい曲線でVnが音を描いて見せるが、オーケストラはモンヤリと鳴るだけで済まして
いるかんじとなる。今世紀の他の”巨匠級”の演奏に比べても、むしろハイフェッツの演奏にはこのカンジのものがより、
目に付くようだ。それはJHの好み以上に両者の力関係や立場に果たしたJHの特別な位置が反映している可能性がある。
1920年のJH初のロンドン公演のあと、バーナードショーが、わざわざ手紙を送り「・・あんなに超人的な完成した
演奏をしたら、嫉妬深い神さまを怒らせ、あなたは若死にしますよ。・・毎晩ベッドに入る前に、お祈りをする代わり
に何かを下手に弾く事にしなさい。人間はあんな完全無欠に弾く大それたことはしてはならないのです。・・・・・」
と書いたそうだが、GBSは若い時 音楽批評をもっぱらやっていた時期もあったくらいで、単なる”スノッブ”ではなく、
音楽と共通する感受性を根本的にもっていたひとでもあるから、そう感じられるような演奏を実際したのだろう。が、
それ以上にジャーナリズムの効果をよく知り、狙ったこういった表現が 無意識的であれスノッブなものを作り出す。
ハイフェッツの”完璧性”という言い方は、多分に社会のフェティッシュなものを反映していることを考えねばならない。
合衆国の世界的ヘゲモニーのシンボルとして、トスカニーニー以上に物質的な固定性を持たされる必要があった。
現代奏法を確立したともいえるJHの演奏は、ある割り切りと徹底性の印象でもある。が やはり いつどのような場合でも
というのは誇張であり、LVBのVn協奏曲をはじめ、メンデルスゾーン、モーツアルトといった”定番メニュー”と
ロマン派的といっても そのうちのヴィアニャフスキーやブルッフといったある職人的なレパートリーには、たしかに、
これ以上のものを考えにくくする録音が残っている一方、その種のもの以外においては必ずしもそうでもなく、関心の
褪めた部分にそれなりの対応で済ます傾向があるのは否定できない。
むしろ、JHが”絶対性”のようなものを発揮するのは、ある”古典的””職人的”なものに限られるといった方が正しい
と思われる。バッハの無伴奏ソナタとパルティータ全曲のレコードの大きな成功が、「完全性」の印象を強めたには違いない
が、それでも1930年代にそれのみ録音された1と3のソナタの方が、明らかにJHは得意なのである。(とはいえ最近の
日本などではこの曲のもっと”もったい”をつけた演奏の方がありがたがられる傾向があるが・・・)
WWのVn協奏曲は、その種の曲に属さない。WW自身が指揮した1950年盤は、実際 旧盤の欠点は大きく改善されている。
オーケストラ部分がしっかり音楽に参加し、変な強調やバランスの悪さはなくなり、結果として一貫した流れが出来ている。
しかし、WWとの50年の演奏が最初のものと比較して文句無く優れているという訳でもない。41年盤の自発的なヒロイズム
に似たひらめきは薄まり、そもそもJHの「技巧」の完結性を願う体質と この協奏曲の執拗な意味の表出を迫る展開は
かならずしも一致しない。作曲家の自作自演の価値とは、しばしば問題となる話なのだが、ある場合 絶対化され易いし、
一方で作曲家の思考を無視した”浅薄な"演奏は常に行われてきた。
勿論 作曲家が作品に対する ある理解 をより持っている事は確かであろう。とはいってもそれは全てではないのである。
一般に作曲家の指揮は、デリケートなフレージングや奏法による音色の大きな効果に十分な関心が乏しい事が多い。ストラビ
ンスキーやRシュトラウスのような一般に評判の良くない人だけでなく、常に高く評価され 決定盤扱いのベンジャミン
ブリテンのようなひとでもそうなのである。(その意味でも”謎の作曲家”ベンジャミンブリテンの影の側面はもっと開拓され
、解明されうる余地がある・・)このように書いてきたから、といってこの自作自演の歴史的な盤の価値が、低いといって
いるので全く無い。むしろ、今日 たくさん並ぶようになったこの曲のカタログにおいても群を抜いて優れたものの一つ
といっていい。WWはちゃんとした指揮の出来る人だし、JHの演奏は良く聴けばやはり、素晴らしいのである。ただ、
セルとWWのsymNo2の場合程の希な幸運な出会いが、もう少しのところで欠けているということなのだ。
【以上 1999月12月頃記す・・2002年5月に上から25〜30行程の部分、書き足す】
注※※・・・上の文章でも、そう書いているつもりだが、別にグーセンスが良くない演奏家という
話ではない。この辺りの事情は、本来 いろいろと詳しい資料を調べてみた方がはっ
きりしたことが云える。ただ大事なのはグーセンス指揮において、この協奏曲の演奏
は、それほど 演奏者の執着がない場合、割と良くあり得る傾向になっているのでな
いか?というようなこと。まず ウォルトンの音楽らしい独特な感じを出す難しさ。
そして、ちゃんとした説得力をもたせて十分に技術的なものをクリアするのは やは
り、大変困難と言っていいのだろう。2002/10/30
2) ヴァイオリン協奏曲 パーヴォ ベルグルンド指揮 ボーンマスsym orch イダ ヘンデル (Vn)
1978年録音・・・・
イダ・ヘンデルの演奏が鋭く(良い意味でも悪い意味でも・・)、20世紀のヴィルティオーソの重要な一
人であり、それが発揮された録音であることをさておくとしても、WWの曲の演奏を史的に考えた場合、
特筆すべきものといった方がよさそうである。
というのも、ここにあるのは それまでのウォルトンの作品の演奏にもっぱらあった、いわゆる英国風の
あるローカルな穏健さをもったもの、もしくは作曲者自身の演奏スタイル を離れて、ちょうど 戦後の
マーラーブームの”オーケストラサウンドを、聞かせるための素材として、利用する傾向”と同じもの
(例えば、ショルティーがマーラー5番でやったような・・)が見られるのでないか。もしくは、その
ような感受性を経た後で、始めてなり得たかもしれない発想の演奏?
また このコンビの演奏以来、それ以前のものに対してこの傾向は新たな目立った特徴となったのかもし
れない。 だから、(WWの)交響曲などの演奏においても、それ以後に取り組んだ他の指揮者たちのや
り方の中に発見できる新しい要素の発端といえるかもしれない。 また この録音が、作曲者自身の最晩
年となる時期とほぼ重なる事とも関係があるだろうか?・・
(EMI)
3) ヴァイオリン協奏曲 ウィリアムウォルトン指揮 ロンドンs,o ユーディーメニューイン(Vn)
♪♪ メニューインとウォルトンの交流・・・ (EMI)
4) ヴァイオリン協奏曲 アンドレプレヴィン指揮 ロイヤルフィル ナイジェルケネディー (Vn)
(EMI)
メニューインと同じように、ビオラもこなせる ケネディーは、ヴィオラ協奏曲 も一緒にいれたLPを
10年くらい前に出していた。いかにも若い彼の楽しそうな演奏で、従来の この曲の演奏のほとんど
どれにもあった重苦しさは、まるでない。プレヴィンもチョンキョンファと一緒の時は ハイフイッツ
盤を、意識したよく似たスタイルだったが、これはケネディーに合わせているのだろう。ケネディーは
イギリス出身ということだが、この頃は意識的に 古くさい重苦しさを排除して行きたいという気持ち
が強かったようだ。とはいえ、この演奏は つまらなく 出来の悪いものには なっていない。この曲
のイメージ一新は、それなりに成功している。3楽章のカデンツァの不思議なグリッサンドもこの演奏
全体には似合っている。明るく風通しは良いが、適当な緊張感は保たれ退屈はしない。最近のケネディ
ーは、これに比べるともっと重厚な感じの演奏をするようになったといえるのかもしれない。
最近のブラームスのニ長調協奏曲を、ベルリンPOとやったものなどは、充分それがあったのでないか?
ある意味 かっての名人たちのような重々しさ、と同時に独特の荒々しさで、大きな響きの流れで全曲
を引っ張っていって、 また十分な名技性で最後までこなして見せた。
そこには、かっての「巨匠」たちと確かに 大きく違うものが、彼にはあるようだ。 ある音楽自体の
独立した絶対的価値から、何か離れていきたいという気持ちを感じる。 だから、彼の場合 重々しく
あっても、どこか親しみやすさ、かみ砕いてくれている優しさが起こってくる。これはサイモンラトル
ととても良く似た傾向でもある。(・・ベルリンpoとの縁は、何か中世のスコラ的汎ヨーロッパの時代
を感じさせてしまうが・・)いずれにせよ、いろいろ既に持っている人にとっては付け加えて損はない
1枚?
(・・・勿論、ラトルもケネディーも資質的には ブリテン向きのヒトと付け加えておいたた方が良い
だろうけども・・・)
【2000年2月頃記す・・2002年9月文章上のミスを置き換え修正?】
← ◇Back → HOME◆
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
注)・・・・出版譜で、こういったパーカッションの削除他、が実際に行われている。

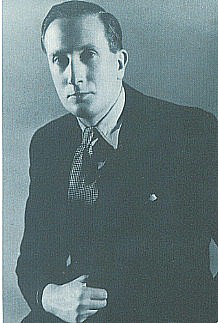 ”Jascha Heifetz(1901-87)”
J・ハィフェッツ の依嘱により、
彼の独奏用に1939年作曲されたこ
のVn協奏曲は同年12月7日にク
リーヴランドでロジンスキー指揮
で初演。最初の録音は41年シンシ
ナチー響 で ユージングーセンス
の指揮で行われた。そしてハイフ
ェッツは 1950年7月26日ウォルト
ン 自身の指揮で再録音している。
この曲は当時すでに神格化されて
いたヴァイオリニスト のための
作品で、またWWは本来 演奏家
の名技性にも馴染み易いタイプの
作曲家といえ、初演の際JHに対
して 演奏上不都合な点があれば
手を加えても構わないとの手紙も
書いている。これなど 当時のJHの名声のためもあるかもすれないが WWは、
のちにオペラ「トロイラスとクレシダ」でも、初演の版を、現実的なソロ歌手に
応じるため ”改良”を行っており、この種の”実際的感覚”は WWのひとつの
特徴といえる。この協奏曲の出版譜にもカディンツアなどでYHの助言を受け入れ
ているという。ハイフィッツが初めの録音盤を作った後、現在普通に演奏される
改訂版が1943年にできている。この版の演奏というだけでなく50年の自作自演に
よる再録音は、グーセンスとの最初の録音の演奏自体にも原因はあったろうと思
われる。 (⇒ 注※※:参照 2002/10/30)
たしかに、2楽章全般そして3楽章の、カディンツに至るぐらいまでのあいだハイフェッツらしい輝かしい音が聞かれは
するが、1楽章のコーダで、バイオリンの息の長いメロディーをフルートとファゴットが十八分音符でリレーして縁取る
部分がせわしい。また肝心のVnの重音の効果的な長いフレーズのあと展開部の頂点で勢いづいたオーケストラが
sub.vivaceで8分の6、8分の9、8分の6、 8分の12、8分の5、8分の3、8分の5、8分の12、8分の6、8分の9、8分の12、
4分の4と不規則的に頻繁に拍子を変える部分があるのだが、ここはストラビンスキーらの流行に近い感覚というより、
ウォルトンの大変特徴的な渦巻きの音楽を作り出しているところである。拍子の作る均質でない時間感覚も、優美な第2
主題を舞曲の簡単なシーソーの格好のバスの3拍子で伴奏した箇所より、ソロとオーケストラが交叉し合い情緒を発展させ
効果的な重音奏法で頂点を迎え、一旦収まったかのような所の直後、音の渦へと流れ落ちるまでの重要な締めくくりである
この部分を生むスリルの大きな要素になっている。(ウォルトンほど鋭く力強い渦巻きの音楽を書いた作曲家はいない・・
、全楽章の全体に増大していくエネルギーのような曲想からみてもその重さを感じなければならない。こういうところを
単に通俗的効果を高めるように受け取ったり、また軽く扱ってしまうのは非常にありがちな反応なのではあるが・・)
こういったところがグーセンスだと突発的で、リズムも均整な感覚にどちらかと言えば、整理されてしまっているようで
もある。例によって短くされ、そして劇的に流れ込む再現部、その終わりのフルートからファゴットの縁取りが続くなか
ハープがEとBの和音を4小節にわたって繰り返すところの45年のスコアでppで書かれている部分も、たいして意味を持た
ないチェロのピッチカートと出来る単調なリズムがむしろ息抜きのように強調して繰り返されるカンジになる。3楽章の練
習番号69-72にかけての最後のカデンツァを導くオーケストラの序奏めいたところも投げやりの勇ましさで、とくに打
楽器音が締まりがなく聞こえて 作曲家としては不満を感じたであろう?→(注 下)
。ある程度最初の録音の特徴は一貫性の無さ そして 簡単に言ってしまえばオーケストラは”伴奏"的演奏の傾向がある。
といっても、これは誰も知らない曲を演奏したグーセンスだけの問題というより 求めるソリスト側の原因も考えてみる
べきであろう。指揮者の考える曲の全体的プランと 演奏者が気持ちよく演奏し易いフレージング、息継ぎ は、もともと
一致しにくいし、むしろ ”矛盾”しつつ生成する。・・というところがある。
(もちろん、双方が無個性で機械的にやれば大して問題にならないことも多かろうが・・・2002/10/30)
ハイフェッツの晩年は、自ら弓を振りつつ指揮するのを好んだし、早く世に出たJHがいた20世紀の初めの”音楽学校”
(必然的に横繋がりもの・・)が「クラシック」音楽の土壌を完全に支配する前の楽団の経営は、興行師的な色彩が現在
より強かったことはいろいろ想像できるし それは”スター”に寄りかかった演奏に容易に重なる体質でもある。
41年盤の1楽章の前半でも非常に美しい曲線でVnが音を描いて見せるが、オーケストラはモンヤリと鳴るだけで済まして
いるかんじとなる。今世紀の他の”巨匠級”の演奏に比べても、むしろハイフェッツの演奏にはこのカンジのものがより、
目に付くようだ。それはJHの好み以上に両者の力関係や立場に果たしたJHの特別な位置が反映している可能性がある。
1920年のJH初のロンドン公演のあと、バーナードショーが、わざわざ手紙を送り「・・あんなに超人的な完成した
演奏をしたら、嫉妬深い神さまを怒らせ、あなたは若死にしますよ。・・毎晩ベッドに入る前に、お祈りをする代わり
に何かを下手に弾く事にしなさい。人間はあんな完全無欠に弾く大それたことはしてはならないのです。・・・・・」
と書いたそうだが、GBSは若い時 音楽批評をもっぱらやっていた時期もあったくらいで、単なる”スノッブ”ではなく、
音楽と共通する感受性を根本的にもっていたひとでもあるから、そう感じられるような演奏を実際したのだろう。が、
それ以上にジャーナリズムの効果をよく知り、狙ったこういった表現が 無意識的であれスノッブなものを作り出す。
ハイフェッツの”完璧性”という言い方は、多分に社会のフェティッシュなものを反映していることを考えねばならない。
合衆国の世界的ヘゲモニーのシンボルとして、トスカニーニー以上に物質的な固定性を持たされる必要があった。
現代奏法を確立したともいえるJHの演奏は、ある割り切りと徹底性の印象でもある。が やはり いつどのような場合でも
というのは誇張であり、LVBのVn協奏曲をはじめ、メンデルスゾーン、モーツアルトといった”定番メニュー”と
ロマン派的といっても そのうちのヴィアニャフスキーやブルッフといったある職人的なレパートリーには、たしかに、
これ以上のものを考えにくくする録音が残っている一方、その種のもの以外においては必ずしもそうでもなく、関心の
褪めた部分にそれなりの対応で済ます傾向があるのは否定できない。
むしろ、JHが”絶対性”のようなものを発揮するのは、ある”古典的””職人的”なものに限られるといった方が正しい
と思われる。バッハの無伴奏ソナタとパルティータ全曲のレコードの大きな成功が、「完全性」の印象を強めたには違いない
が、それでも1930年代にそれのみ録音された1と3のソナタの方が、明らかにJHは得意なのである。(とはいえ最近の
日本などではこの曲のもっと”もったい”をつけた演奏の方がありがたがられる傾向があるが・・・)
WWのVn協奏曲は、その種の曲に属さない。WW自身が指揮した1950年盤は、実際 旧盤の欠点は大きく改善されている。
オーケストラ部分がしっかり音楽に参加し、変な強調やバランスの悪さはなくなり、結果として一貫した流れが出来ている。
しかし、WWとの50年の演奏が最初のものと比較して文句無く優れているという訳でもない。41年盤の自発的なヒロイズム
に似たひらめきは薄まり、そもそもJHの「技巧」の完結性を願う体質と この協奏曲の執拗な意味の表出を迫る展開は
かならずしも一致しない。作曲家の自作自演の価値とは、しばしば問題となる話なのだが、ある場合 絶対化され易いし、
一方で作曲家の思考を無視した”浅薄な"演奏は常に行われてきた。
勿論 作曲家が作品に対する ある理解 をより持っている事は確かであろう。とはいってもそれは全てではないのである。
一般に作曲家の指揮は、デリケートなフレージングや奏法による音色の大きな効果に十分な関心が乏しい事が多い。ストラビ
ンスキーやRシュトラウスのような一般に評判の良くない人だけでなく、常に高く評価され 決定盤扱いのベンジャミン
ブリテンのようなひとでもそうなのである。(その意味でも”謎の作曲家”ベンジャミンブリテンの影の側面はもっと開拓され
、解明されうる余地がある・・)このように書いてきたから、といってこの自作自演の歴史的な盤の価値が、低いといって
いるので全く無い。むしろ、今日 たくさん並ぶようになったこの曲のカタログにおいても群を抜いて優れたものの一つ
といっていい。WWはちゃんとした指揮の出来る人だし、JHの演奏は良く聴けばやはり、素晴らしいのである。ただ、
セルとWWのsymNo2の場合程の希な幸運な出会いが、もう少しのところで欠けているということなのだ。
【以上 1999月12月頃記す・・2002年5月に上から25〜30行程の部分、書き足す】
注※※・・・上の文章でも、そう書いているつもりだが、別にグーセンスが良くない演奏家という
話ではない。この辺りの事情は、本来 いろいろと詳しい資料を調べてみた方がはっ
きりしたことが云える。ただ大事なのはグーセンス指揮において、この協奏曲の演奏
は、それほど 演奏者の執着がない場合、割と良くあり得る傾向になっているのでな
いか?というようなこと。まず ウォルトンの音楽らしい独特な感じを出す難しさ。
そして、ちゃんとした説得力をもたせて十分に技術的なものをクリアするのは やは
り、大変困難と言っていいのだろう。2002/10/30
2) ヴァイオリン協奏曲 パーヴォ ベルグルンド指揮 ボーンマスsym orch イダ ヘンデル (Vn)
1978年録音・・・・
イダ・ヘンデルの演奏が鋭く(良い意味でも悪い意味でも・・)、20世紀のヴィルティオーソの重要な一
人であり、それが発揮された録音であることをさておくとしても、WWの曲の演奏を史的に考えた場合、
特筆すべきものといった方がよさそうである。
というのも、ここにあるのは それまでのウォルトンの作品の演奏にもっぱらあった、いわゆる英国風の
あるローカルな穏健さをもったもの、もしくは作曲者自身の演奏スタイル を離れて、ちょうど 戦後の
マーラーブームの”オーケストラサウンドを、聞かせるための素材として、利用する傾向”と同じもの
(例えば、ショルティーがマーラー5番でやったような・・)が見られるのでないか。もしくは、その
ような感受性を経た後で、始めてなり得たかもしれない発想の演奏?
また このコンビの演奏以来、それ以前のものに対してこの傾向は新たな目立った特徴となったのかもし
れない。 だから、(WWの)交響曲などの演奏においても、それ以後に取り組んだ他の指揮者たちのや
り方の中に発見できる新しい要素の発端といえるかもしれない。 また この録音が、作曲者自身の最晩
年となる時期とほぼ重なる事とも関係があるだろうか?・・
(EMI)
3) ヴァイオリン協奏曲 ウィリアムウォルトン指揮 ロンドンs,o ユーディーメニューイン(Vn)
♪♪ メニューインとウォルトンの交流・・・ (EMI)
4) ヴァイオリン協奏曲 アンドレプレヴィン指揮 ロイヤルフィル ナイジェルケネディー (Vn)
(EMI)
メニューインと同じように、ビオラもこなせる ケネディーは、ヴィオラ協奏曲 も一緒にいれたLPを
10年くらい前に出していた。いかにも若い彼の楽しそうな演奏で、従来の この曲の演奏のほとんど
どれにもあった重苦しさは、まるでない。プレヴィンもチョンキョンファと一緒の時は ハイフイッツ
盤を、意識したよく似たスタイルだったが、これはケネディーに合わせているのだろう。ケネディーは
イギリス出身ということだが、この頃は意識的に 古くさい重苦しさを排除して行きたいという気持ち
が強かったようだ。とはいえ、この演奏は つまらなく 出来の悪いものには なっていない。この曲
のイメージ一新は、それなりに成功している。3楽章のカデンツァの不思議なグリッサンドもこの演奏
全体には似合っている。明るく風通しは良いが、適当な緊張感は保たれ退屈はしない。最近のケネディ
ーは、これに比べるともっと重厚な感じの演奏をするようになったといえるのかもしれない。
最近のブラームスのニ長調協奏曲を、ベルリンPOとやったものなどは、充分それがあったのでないか?
ある意味 かっての名人たちのような重々しさ、と同時に独特の荒々しさで、大きな響きの流れで全曲
を引っ張っていって、 また十分な名技性で最後までこなして見せた。
そこには、かっての「巨匠」たちと確かに 大きく違うものが、彼にはあるようだ。 ある音楽自体の
独立した絶対的価値から、何か離れていきたいという気持ちを感じる。 だから、彼の場合 重々しく
あっても、どこか親しみやすさ、かみ砕いてくれている優しさが起こってくる。これはサイモンラトル
ととても良く似た傾向でもある。(・・ベルリンpoとの縁は、何か中世のスコラ的汎ヨーロッパの時代
を感じさせてしまうが・・)いずれにせよ、いろいろ既に持っている人にとっては付け加えて損はない
1枚?
(・・・勿論、ラトルもケネディーも資質的には ブリテン向きのヒトと付け加えておいたた方が良い
だろうけども・・・)
【2000年2月頃記す・・2002年9月文章上のミスを置き換え修正?】
← ◇Back → HOME◆
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
注)・・・・出版譜で、こういったパーカッションの削除他、が実際に行われている。
”Jascha Heifetz(1901-87)”
J・ハィフェッツ の依嘱により、
彼の独奏用に1939年作曲されたこ
のVn協奏曲は同年12月7日にク
リーヴランドでロジンスキー指揮
で初演。最初の録音は41年シンシ
ナチー響 で ユージングーセンス
の指揮で行われた。そしてハイフ
ェッツは 1950年7月26日ウォルト
ン 自身の指揮で再録音している。
この曲は当時すでに神格化されて
いたヴァイオリニスト のための
作品で、またWWは本来 演奏家
の名技性にも馴染み易いタイプの
作曲家といえ、初演の際JHに対
して 演奏上不都合な点があれば
手を加えても構わないとの手紙も
書いている。これなど 当時のJHの名声のためもあるかもすれないが WWは、
のちにオペラ「トロイラスとクレシダ」でも、初演の版を、現実的なソロ歌手に
応じるため ”改良”を行っており、この種の”実際的感覚”は WWのひとつの
特徴といえる。この協奏曲の出版譜にもカディンツアなどでYHの助言を受け入れ
ているという。ハイフィッツが初めの録音盤を作った後、現在普通に演奏される
改訂版が1943年にできている。この版の演奏というだけでなく50年の自作自演に
よる再録音は、グーセンスとの最初の録音の演奏自体にも原因はあったろうと思
われる。 (⇒ 注※※:参照 2002/10/30)
たしかに、2楽章全般そして3楽章の、カディンツに至るぐらいまでのあいだハイフェッツらしい輝かしい音が聞かれは
するが、1楽章のコーダで、バイオリンの息の長いメロディーをフルートとファゴットが十八分音符でリレーして縁取る
部分がせわしい。また肝心のVnの重音の効果的な長いフレーズのあと展開部の頂点で勢いづいたオーケストラが
sub.vivaceで8分の6、8分の9、8分の6、 8分の12、8分の5、8分の3、8分の5、8分の12、8分の6、8分の9、8分の12、
4分の4と不規則的に頻繁に拍子を変える部分があるのだが、ここはストラビンスキーらの流行に近い感覚というより、
ウォルトンの大変特徴的な渦巻きの音楽を作り出しているところである。拍子の作る均質でない時間感覚も、優美な第2
主題を舞曲の簡単なシーソーの格好のバスの3拍子で伴奏した箇所より、ソロとオーケストラが交叉し合い情緒を発展させ
効果的な重音奏法で頂点を迎え、一旦収まったかのような所の直後、音の渦へと流れ落ちるまでの重要な締めくくりである
この部分を生むスリルの大きな要素になっている。(ウォルトンほど鋭く力強い渦巻きの音楽を書いた作曲家はいない・・
、全楽章の全体に増大していくエネルギーのような曲想からみてもその重さを感じなければならない。こういうところを
単に通俗的効果を高めるように受け取ったり、また軽く扱ってしまうのは非常にありがちな反応なのではあるが・・)
こういったところがグーセンスだと突発的で、リズムも均整な感覚にどちらかと言えば、整理されてしまっているようで
もある。例によって短くされ、そして劇的に流れ込む再現部、その終わりのフルートからファゴットの縁取りが続くなか
ハープがEとBの和音を4小節にわたって繰り返すところの45年のスコアでppで書かれている部分も、たいして意味を持た
ないチェロのピッチカートと出来る単調なリズムがむしろ息抜きのように強調して繰り返されるカンジになる。3楽章の練
習番号69-72にかけての最後のカデンツァを導くオーケストラの序奏めいたところも投げやりの勇ましさで、とくに打
楽器音が締まりがなく聞こえて 作曲家としては不満を感じたであろう?→(注 下)
。ある程度最初の録音の特徴は一貫性の無さ そして 簡単に言ってしまえばオーケストラは”伴奏"的演奏の傾向がある。
といっても、これは誰も知らない曲を演奏したグーセンスだけの問題というより 求めるソリスト側の原因も考えてみる
べきであろう。指揮者の考える曲の全体的プランと 演奏者が気持ちよく演奏し易いフレージング、息継ぎ は、もともと
一致しにくいし、むしろ ”矛盾”しつつ生成する。・・というところがある。
(もちろん、双方が無個性で機械的にやれば大して問題にならないことも多かろうが・・・2002/10/30)
ハイフェッツの晩年は、自ら弓を振りつつ指揮するのを好んだし、早く世に出たJHがいた20世紀の初めの”音楽学校”
(必然的に横繋がりもの・・)が「クラシック」音楽の土壌を完全に支配する前の楽団の経営は、興行師的な色彩が現在
より強かったことはいろいろ想像できるし それは”スター”に寄りかかった演奏に容易に重なる体質でもある。
41年盤の1楽章の前半でも非常に美しい曲線でVnが音を描いて見せるが、オーケストラはモンヤリと鳴るだけで済まして
いるかんじとなる。今世紀の他の”巨匠級”の演奏に比べても、むしろハイフェッツの演奏にはこのカンジのものがより、
目に付くようだ。それはJHの好み以上に両者の力関係や立場に果たしたJHの特別な位置が反映している可能性がある。
1920年のJH初のロンドン公演のあと、バーナードショーが、わざわざ手紙を送り「・・あんなに超人的な完成した
演奏をしたら、嫉妬深い神さまを怒らせ、あなたは若死にしますよ。・・毎晩ベッドに入る前に、お祈りをする代わり
に何かを下手に弾く事にしなさい。人間はあんな完全無欠に弾く大それたことはしてはならないのです。・・・・・」
と書いたそうだが、GBSは若い時 音楽批評をもっぱらやっていた時期もあったくらいで、単なる”スノッブ”ではなく、
音楽と共通する感受性を根本的にもっていたひとでもあるから、そう感じられるような演奏を実際したのだろう。が、
それ以上にジャーナリズムの効果をよく知り、狙ったこういった表現が 無意識的であれスノッブなものを作り出す。
ハイフェッツの”完璧性”という言い方は、多分に社会のフェティッシュなものを反映していることを考えねばならない。
合衆国の世界的ヘゲモニーのシンボルとして、トスカニーニー以上に物質的な固定性を持たされる必要があった。
現代奏法を確立したともいえるJHの演奏は、ある割り切りと徹底性の印象でもある。が やはり いつどのような場合でも
というのは誇張であり、LVBのVn協奏曲をはじめ、メンデルスゾーン、モーツアルトといった”定番メニュー”と
ロマン派的といっても そのうちのヴィアニャフスキーやブルッフといったある職人的なレパートリーには、たしかに、
これ以上のものを考えにくくする録音が残っている一方、その種のもの以外においては必ずしもそうでもなく、関心の
褪めた部分にそれなりの対応で済ます傾向があるのは否定できない。
むしろ、JHが”絶対性”のようなものを発揮するのは、ある”古典的””職人的”なものに限られるといった方が正しい
と思われる。バッハの無伴奏ソナタとパルティータ全曲のレコードの大きな成功が、「完全性」の印象を強めたには違いない
が、それでも1930年代にそれのみ録音された1と3のソナタの方が、明らかにJHは得意なのである。(とはいえ最近の
日本などではこの曲のもっと”もったい”をつけた演奏の方がありがたがられる傾向があるが・・・)
WWのVn協奏曲は、その種の曲に属さない。WW自身が指揮した1950年盤は、実際 旧盤の欠点は大きく改善されている。
オーケストラ部分がしっかり音楽に参加し、変な強調やバランスの悪さはなくなり、結果として一貫した流れが出来ている。
しかし、WWとの50年の演奏が最初のものと比較して文句無く優れているという訳でもない。41年盤の自発的なヒロイズム
に似たひらめきは薄まり、そもそもJHの「技巧」の完結性を願う体質と この協奏曲の執拗な意味の表出を迫る展開は
かならずしも一致しない。作曲家の自作自演の価値とは、しばしば問題となる話なのだが、ある場合 絶対化され易いし、
一方で作曲家の思考を無視した”浅薄な"演奏は常に行われてきた。
勿論 作曲家が作品に対する ある理解 をより持っている事は確かであろう。とはいってもそれは全てではないのである。
一般に作曲家の指揮は、デリケートなフレージングや奏法による音色の大きな効果に十分な関心が乏しい事が多い。ストラビ
ンスキーやRシュトラウスのような一般に評判の良くない人だけでなく、常に高く評価され 決定盤扱いのベンジャミン
ブリテンのようなひとでもそうなのである。(その意味でも”謎の作曲家”ベンジャミンブリテンの影の側面はもっと開拓され
、解明されうる余地がある・・)このように書いてきたから、といってこの自作自演の歴史的な盤の価値が、低いといって
いるので全く無い。むしろ、今日 たくさん並ぶようになったこの曲のカタログにおいても群を抜いて優れたものの一つ
といっていい。WWはちゃんとした指揮の出来る人だし、JHの演奏は良く聴けばやはり、素晴らしいのである。ただ、
セルとWWのsymNo2の場合程の希な幸運な出会いが、もう少しのところで欠けているということなのだ。
【以上 1999月12月頃記す・・2002年5月に上から25〜30行程の部分、書き足す】
注※※・・・上の文章でも、そう書いているつもりだが、別にグーセンスが良くない演奏家という
話ではない。この辺りの事情は、本来 いろいろと詳しい資料を調べてみた方がはっ
きりしたことが云える。ただ大事なのはグーセンス指揮において、この協奏曲の演奏
は、それほど 演奏者の執着がない場合、割と良くあり得る傾向になっているのでな
いか?というようなこと。まず ウォルトンの音楽らしい独特な感じを出す難しさ。
そして、ちゃんとした説得力をもたせて十分に技術的なものをクリアするのは やは
り、大変困難と言っていいのだろう。2002/10/30
2) ヴァイオリン協奏曲 パーヴォ ベルグルンド指揮 ボーンマスsym orch イダ ヘンデル (Vn)
1978年録音・・・・
イダ・ヘンデルの演奏が鋭く(良い意味でも悪い意味でも・・)、20世紀のヴィルティオーソの重要な一
人であり、それが発揮された録音であることをさておくとしても、WWの曲の演奏を史的に考えた場合、
特筆すべきものといった方がよさそうである。
というのも、ここにあるのは それまでのウォルトンの作品の演奏にもっぱらあった、いわゆる英国風の
あるローカルな穏健さをもったもの、もしくは作曲者自身の演奏スタイル を離れて、ちょうど 戦後の
マーラーブームの”オーケストラサウンドを、聞かせるための素材として、利用する傾向”と同じもの
(例えば、ショルティーがマーラー5番でやったような・・)が見られるのでないか。もしくは、その
ような感受性を経た後で、始めてなり得たかもしれない発想の演奏?
また このコンビの演奏以来、それ以前のものに対してこの傾向は新たな目立った特徴となったのかもし
れない。 だから、(WWの)交響曲などの演奏においても、それ以後に取り組んだ他の指揮者たちのや
り方の中に発見できる新しい要素の発端といえるかもしれない。 また この録音が、作曲者自身の最晩
年となる時期とほぼ重なる事とも関係があるだろうか?・・
(EMI)
3) ヴァイオリン協奏曲 ウィリアムウォルトン指揮 ロンドンs,o ユーディーメニューイン(Vn)
♪♪ メニューインとウォルトンの交流・・・ (EMI)
4) ヴァイオリン協奏曲 アンドレプレヴィン指揮 ロイヤルフィル ナイジェルケネディー (Vn)
(EMI)
メニューインと同じように、ビオラもこなせる ケネディーは、ヴィオラ協奏曲 も一緒にいれたLPを
10年くらい前に出していた。いかにも若い彼の楽しそうな演奏で、従来の この曲の演奏のほとんど
どれにもあった重苦しさは、まるでない。プレヴィンもチョンキョンファと一緒の時は ハイフイッツ
盤を、意識したよく似たスタイルだったが、これはケネディーに合わせているのだろう。ケネディーは
イギリス出身ということだが、この頃は意識的に 古くさい重苦しさを排除して行きたいという気持ち
が強かったようだ。とはいえ、この演奏は つまらなく 出来の悪いものには なっていない。この曲
のイメージ一新は、それなりに成功している。3楽章のカデンツァの不思議なグリッサンドもこの演奏
全体には似合っている。明るく風通しは良いが、適当な緊張感は保たれ退屈はしない。最近のケネディ
ーは、これに比べるともっと重厚な感じの演奏をするようになったといえるのかもしれない。
最近のブラームスのニ長調協奏曲を、ベルリンPOとやったものなどは、充分それがあったのでないか?
ある意味 かっての名人たちのような重々しさ、と同時に独特の荒々しさで、大きな響きの流れで全曲
を引っ張っていって、 また十分な名技性で最後までこなして見せた。
そこには、かっての「巨匠」たちと確かに 大きく違うものが、彼にはあるようだ。 ある音楽自体の
独立した絶対的価値から、何か離れていきたいという気持ちを感じる。 だから、彼の場合 重々しく
あっても、どこか親しみやすさ、かみ砕いてくれている優しさが起こってくる。これはサイモンラトル
ととても良く似た傾向でもある。(・・ベルリンpoとの縁は、何か中世のスコラ的汎ヨーロッパの時代
を感じさせてしまうが・・)いずれにせよ、いろいろ既に持っている人にとっては付け加えて損はない
1枚?
(・・・勿論、ラトルもケネディーも資質的には ブリテン向きのヒトと付け加えておいたた方が良い
だろうけども・・・)
【2000年2月頃記す・・2002年9月文章上のミスを置き換え修正?】
← ◇Back → HOME◆
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
注)・・・・出版譜で、こういったパーカッションの削除他、が実際に行われている。