ソロモンというピアニストは、良く知られたショパンのノクターンの伴奏型又月光ソナタといわれてい る曲の3連音符などの細かく変化していく音の流れをレガートに非常に拘って弾いてみせ、静かで不思 議な波の動きをもつ音楽を作り出し、その演奏を成功させている。 このことは、これらの曲が、水の イメージにつながる要素を、元々持っていることを証しているともいえる。 水のイメージにこだわる芸術家たちの名前をレオナルド他幾つか挙げることが出来る。水のイメージは、
 人の手に掴む事の出来ない、指の間から流れ出してしまうものであり、それをコントロールするには、
渦や、流していくこと を考えねばならず、静止的な体系とは、少なくともなかなか折り合いのつか
ないものの代表として受け取られていた。レオナルドは、学者的な画家であったともいえるが、学者的
な著述に自らを、固定した訳ではなかった。レオナルドの水の描写は、幾何的形態に囚われたところが
あるが、それでも 多くの彼の絵画には、流れるような動きの統一が、画面において指向されている。
勿論、何となく水の動きを感じる芸術作品には、いろんなレベルと傾向がある。ある方向において、
水のイメージを徹底すると、演劇的感覚は、相通じるところがある。
劇場において、私たちは、感情的カタルシスを求めているということは、しかたのないことで、元来そ
ういう媒体なのである。細かい筋道だった理屈など、普通 通じはしない。ともかく、感情の渦で観客
を押し流してしまう技術というものが、普通別に存在する。もちろん、その感情の渦には程度の高い低い
があるのだが、体系的な真理を求める方向の発想とは、別の現実的必然性を持つある「思考法」である。
シェーンベルクの「ファンタジー」とウォルトンの「トッカータ」の曲の展開の違い、とまた 共通性
とを理解するには、言って みれば、こういった思考法の違いに由来するものを、考えることにヒント
がある。ウォルトンの水面の憂鬱から発する音楽だろうと、シェーンベルクの会話したり、皮肉なワル
ツに心を沈める音楽だろうと、両者に共通する静かな中間部は、不可避の現実である産業技術社会との、
対応関係の問題や困難と、真にかみ合うことの出来る、静かに自らに生ずる情動と共に自らを見つめる
意識なのであり、それが、両者のこの2つの曲において、徹底した多層的な他の情動との関係、振幅の
つながりの要所として存在し、そして全曲が出来ているということは、重要である。
(産業技術社会の軋轢から逃れて、政治的な架空の理念や経済的な架空の貨幣構造をユートピア的に
想定し、それを現実に押しつけようとすることはかって色々試みられた。しかし、それは結局近代
のシステムの波の中に呑み込まれたし、むしろ、それはそのシステムの都市的な余剰として、一部
の機能として、最初からの役目を持っていたしそれ以上のものではなかったのであるetc・・・)(2002/9/22)
※ 文末参照・・・商品、価値、音楽、等々
トッカータには、ある程度、動機的な統一的設計がされているが、それ以上に注目すべきは、ある劇的効
果の関心で、特に 速い足取りのような部分と、最後のピアノの駆け下りるイメージのある速度であり、
中間部の不安な瞑想の向かうべき困難には、こうして処せられる。荒々しい暴力的なまでの血の記憶の
現実のようなエキゾティックなメロディーのコーダも付け合わされ、それはつねに突発的に支配する。
それが、正しかろうとそうで無くても良く、スピードと情緒的な勝負が要求され、「流していけば良い」
という、いわば未来任せのこの方法。
別様にいえば資本主義とも、いわれているもののリアルな写し絵となる方法 というのも、結局 言い
過ぎにはならない。一方、シェーンベルクにとっては、そこが砂漠の世界だろうと、完結した正しさを
追い求めることが、必要で、それが彼の現実への対処であった。
〈その方向が戦後の官僚主義の世界に利用されたのは現実の皮肉であった・・〉
同じ半音階的に発達した和声を背景とした 今世紀の多くの音楽の内( それはまた私たちが今取り
上げるに足る音楽の大部分でもある)でも、こういった問題へのイメージを伴うものは、稀といえる。
ドビュッシーは、極度に都会的、技術的に、洗練された静かな感覚を持っていたが、徹底した激しい情緒
人の手に掴む事の出来ない、指の間から流れ出してしまうものであり、それをコントロールするには、
渦や、流していくこと を考えねばならず、静止的な体系とは、少なくともなかなか折り合いのつか
ないものの代表として受け取られていた。レオナルドは、学者的な画家であったともいえるが、学者的
な著述に自らを、固定した訳ではなかった。レオナルドの水の描写は、幾何的形態に囚われたところが
あるが、それでも 多くの彼の絵画には、流れるような動きの統一が、画面において指向されている。
勿論、何となく水の動きを感じる芸術作品には、いろんなレベルと傾向がある。ある方向において、
水のイメージを徹底すると、演劇的感覚は、相通じるところがある。
劇場において、私たちは、感情的カタルシスを求めているということは、しかたのないことで、元来そ
ういう媒体なのである。細かい筋道だった理屈など、普通 通じはしない。ともかく、感情の渦で観客
を押し流してしまう技術というものが、普通別に存在する。もちろん、その感情の渦には程度の高い低い
があるのだが、体系的な真理を求める方向の発想とは、別の現実的必然性を持つある「思考法」である。
シェーンベルクの「ファンタジー」とウォルトンの「トッカータ」の曲の展開の違い、とまた 共通性
とを理解するには、言って みれば、こういった思考法の違いに由来するものを、考えることにヒント
がある。ウォルトンの水面の憂鬱から発する音楽だろうと、シェーンベルクの会話したり、皮肉なワル
ツに心を沈める音楽だろうと、両者に共通する静かな中間部は、不可避の現実である産業技術社会との、
対応関係の問題や困難と、真にかみ合うことの出来る、静かに自らに生ずる情動と共に自らを見つめる
意識なのであり、それが、両者のこの2つの曲において、徹底した多層的な他の情動との関係、振幅の
つながりの要所として存在し、そして全曲が出来ているということは、重要である。
(産業技術社会の軋轢から逃れて、政治的な架空の理念や経済的な架空の貨幣構造をユートピア的に
想定し、それを現実に押しつけようとすることはかって色々試みられた。しかし、それは結局近代
のシステムの波の中に呑み込まれたし、むしろ、それはそのシステムの都市的な余剰として、一部
の機能として、最初からの役目を持っていたしそれ以上のものではなかったのであるetc・・・)(2002/9/22)
※ 文末参照・・・商品、価値、音楽、等々
トッカータには、ある程度、動機的な統一的設計がされているが、それ以上に注目すべきは、ある劇的効
果の関心で、特に 速い足取りのような部分と、最後のピアノの駆け下りるイメージのある速度であり、
中間部の不安な瞑想の向かうべき困難には、こうして処せられる。荒々しい暴力的なまでの血の記憶の
現実のようなエキゾティックなメロディーのコーダも付け合わされ、それはつねに突発的に支配する。
それが、正しかろうとそうで無くても良く、スピードと情緒的な勝負が要求され、「流していけば良い」
という、いわば未来任せのこの方法。
別様にいえば資本主義とも、いわれているもののリアルな写し絵となる方法 というのも、結局 言い
過ぎにはならない。一方、シェーンベルクにとっては、そこが砂漠の世界だろうと、完結した正しさを
追い求めることが、必要で、それが彼の現実への対処であった。
〈その方向が戦後の官僚主義の世界に利用されたのは現実の皮肉であった・・〉
同じ半音階的に発達した和声を背景とした 今世紀の多くの音楽の内( それはまた私たちが今取り
上げるに足る音楽の大部分でもある)でも、こういった問題へのイメージを伴うものは、稀といえる。
ドビュッシーは、極度に都会的、技術的に、洗練された静かな感覚を持っていたが、徹底した激しい情緒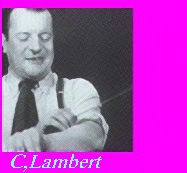 と、深く結びつけることには関心が無かった。ドイツ的緻密さに近いものはあるにせよ、バルトークに
頻繁にある不協和音の激しさは、本当に充実した静かな意識する音楽と対応してはいず、あるポーズとし
て型にはまったもので、西欧中心国に対する外部の人間群、としての抗議のパターンになっている。
(バルトークの弦楽四重奏などでの緩徐楽章は、ベルクやシェーンベルクを思わすものが多いが、粘り
を失って薄められ、常識的な感覚のものになる・・・・・)
「出会い」の経験を、その一回性や、物語り性に託して、大袈裟にかたるのは、かなり馬鹿げたことだ
が、偶然がそこに作用してはいるものの、それはそれなりに理由がある。
例えば、むしろ、近しい位置関係にもあり、作品から影響が見て取れるにも関わらず、バルトークが殆ど、
接触求めてこないことが、新ウィーン樂派からは不信に思われていた。
若い頃 新ウィーン楽派に興味を持っていたにもかかわらずブリテンは、Fブリッジや両親に強くその
傾向を反対されていた。
1934年大陸に赴いたブリテンは、ウィーンにアルバンベルクに会うつもりで出向いたが、不在の知らせ
を受け、結局、35年に死んだベルクとは、一生会うこともなく、また シェーンベルクとも接点は無か
ったらしい。
片や、ウォルトンの方は、直接会ってはいるものの、前述のようにあまり愉快なものでもなかった。
しかし、新ウィーン派のようにある意味内側に吸収された人々を除けば、他の誰よりもシェーンベルク
的なものに最も正面から接近し、すれ違った人と見るのは、オーバーな話ではないと思う。あえても
っと言えばイギリス現代音楽の成立とドイツ音楽の転化がすれ違った歴史のあらわれ?
12音音楽以降のドグマテックな素朴進化論といえる立場への批判の姿勢を、後年の彼がとっていること
が、《「無調は、表現の内のひとつだ・・WW」「中道はローマに通じない唯一の道だ・・AS」》こう
いった行き違いの起こった理由の基本的な原因の1つであると当然いえる。
単純な対立だけと受け取るのは、誤りと思う。むしろ、デリケートだが、ある本質的違いであるところ
に、この対比の面白さがある。ウォルトンは、20世紀のオペラ音楽としてヒンデミットの「・・マティス
」とともに、ベルクの「ヴォツェック」を常に高く評価していた。また、シェーンベルクに関しても、
70年頃のインタビューで、12音主義の教義は、認めないが、作曲の大家としてのシェーンベルクを十分
評価していることをのべている。逆に、シェーンベルクは、彼の理論とどうつながるか微妙な問題をはら
むにもかかわらず、イギリス民謡が世界で最も、美しい民謡だと公言してはばからなかったし、また、
アドルノは、、シェーンベルクは 再婚をしたころから、ファッションに気を配るようになって、イギリ
ス風の服装・みだしなみにこだわっているみたいなのが、滑稽に思われたことを、敢えて書いているが、
それは、ある種の軽いイギリス紳士コンプレックスが、シェーンベルクにあったことを、指摘している
ものでもある。師匠筋の小柄なシェーンベルクよりも、長身のベルクの方が、同じく長身のウォルトン
(ノルマン風?・・出会った頃のSシットウエルの感想。)と並べた場合、容姿の上でも、耽美派的な前
者と良く出来た対称を描くのだが、「ウォルトンは、ベルクの裏返し・・」というようなことは、彼らの
作品に関しても、ある程度 面白い言い方となるのである。そんな具合に ベルクの方と比較する
発想は、十分理由のあることで、作品の別の面に、光をあてるものだが、話がそれるので、今は脇に
置かせてもらう。
ピアノ四重奏が、作曲家公認の曲として、39年・54年にレコーディングされるくらいだったのに対して、
同じようにランバートらも、評価したものだし、その内容の充実度を考えても、こちらだけが埋もれてし
まったのは、なおまだ疑問として残る。むしろ、そこには、いろんな「不運な事情」といっていいいくつ
かの大きな問題を考えねばならない。
後年のセリエリスム等に反対する立場的問題を、作曲者が取ったこととの関連は勿論あるのだが、それを
含めて考えてもそれだけじゃなく、まずそれが無調的傾向を示しているものについては、確かにそこに
特別な印象を残すのであって、それは見逃せない事でもある。(後年の本人の意識とは少し違って)
その曲が良く出来ている、もしくはかならずしもそうでもない、に関わらず初期の弦楽四重奏曲と共に、
それらは、むしろシェーンベルクの作品以上にと言った方がいい、何かしら“悪魔的ニュアンス”を伴う
印象がある。 そのことは、その本来の、また未来における価値判断とは、別にして、シェーンベルク
の無調的作品が、本質的に“近代批判”の立場から出てきたものであり、その意味で近代のパラダイムか
ら、はずれた弱者を包含するような立場であるに対して、ウォルトンのそれは、この時、単純な強者の立
場とは、ほど遠いにせよ“近代”の発想に直結したものから来ていることに重大な理由が見つけられると、
いう問題があることを述べておく。即ち その点に、意識的にならなければ、こういったニュアンスは、
普通 不必要に作品の出来の悪さと錯覚され易いという傾向を、「事情」として挙げておこう。
シェーンベルク以後のセリエリスム的なものもしくは、マスコミむけの前衛パフォーマンスは、管理さ
れた社会に さほど抵抗を生まない。初期のピアノ四重奏とこの曲を並べれば、確かに”アンファンテ
リブル”というような言葉が思い浮かぶが、トッカータのような傾向の諸作品は無調的であるとないと
に限らず、むしろ それが娯楽的でも、また単なる専門家的知識の対象として捉えて済むものでもないと
いう性格に問題がある。
それは、かってマーラーの多くの交響曲がそうとられたように、芸術らしい芸術でもないと言う性格
でもあり、(余裕と寛容を余り感じさせない生々しさ・・)そういった感じがある子供じみたものと誤
解されるものの由来の一つである。こういった作品は、明らかに陳腐であったり、ある職業的なものでも
なく 聴くものを生の現実に向かわせるが、実は人々が、最も抵抗を示すのは そのようなありのまま
の姿を示したものであるのだ。このことが法則的事実ですらあるのは、作曲者自身にしてもそのことは、
起こるということで、ある意味作曲者の本質を最も示した、トッカータのような作品に対しては、特に
振り返ると遠ざけたくなってしまう。
半世紀前と違い、世界中のさまざまなことが、手近にして見聞きできる今日、私たちが、やるべきこ
とといえば、こうした作品に対して、例えばその「音楽」であることの表面的な形にとらわれず、そ
の各部分のイメージの連続を、私たちの生活の様々な分野の事象との類似性や違いを比較して、そも
そも私たちが何を感じていたかを、より広い視点で見てみることであり、場合によっては、今まで単
に子供じみたものと考えられたことにも境界を置かないことでもある。
そういったことで、様々なかっての作品に対しても、本当の価値を新たに見せてくれるだろう。
また 結局、ある管理的なものが優先されるだけの社会による閉ざされた未来に裂け目を入れる最も
効果的な方法でもあるのだが、それは即ち世界の様相の変化ということ。そこでこういった「トッカ
ータ」のような類の音楽は自ずとさらに誇らしく蘇ってくるとは云えないだろうか?
【いちおうEND・・//2001、8月19日記述】
(注や譜例を中心に必要な部分を、付け足して議論をより解かり易く
改良していくつもりです・・・・2001年12月17日・・・・・・・)
と、深く結びつけることには関心が無かった。ドイツ的緻密さに近いものはあるにせよ、バルトークに
頻繁にある不協和音の激しさは、本当に充実した静かな意識する音楽と対応してはいず、あるポーズとし
て型にはまったもので、西欧中心国に対する外部の人間群、としての抗議のパターンになっている。
(バルトークの弦楽四重奏などでの緩徐楽章は、ベルクやシェーンベルクを思わすものが多いが、粘り
を失って薄められ、常識的な感覚のものになる・・・・・)
「出会い」の経験を、その一回性や、物語り性に託して、大袈裟にかたるのは、かなり馬鹿げたことだ
が、偶然がそこに作用してはいるものの、それはそれなりに理由がある。
例えば、むしろ、近しい位置関係にもあり、作品から影響が見て取れるにも関わらず、バルトークが殆ど、
接触求めてこないことが、新ウィーン樂派からは不信に思われていた。
若い頃 新ウィーン楽派に興味を持っていたにもかかわらずブリテンは、Fブリッジや両親に強くその
傾向を反対されていた。
1934年大陸に赴いたブリテンは、ウィーンにアルバンベルクに会うつもりで出向いたが、不在の知らせ
を受け、結局、35年に死んだベルクとは、一生会うこともなく、また シェーンベルクとも接点は無か
ったらしい。
片や、ウォルトンの方は、直接会ってはいるものの、前述のようにあまり愉快なものでもなかった。
しかし、新ウィーン派のようにある意味内側に吸収された人々を除けば、他の誰よりもシェーンベルク
的なものに最も正面から接近し、すれ違った人と見るのは、オーバーな話ではないと思う。あえても
っと言えばイギリス現代音楽の成立とドイツ音楽の転化がすれ違った歴史のあらわれ?
12音音楽以降のドグマテックな素朴進化論といえる立場への批判の姿勢を、後年の彼がとっていること
が、《「無調は、表現の内のひとつだ・・WW」「中道はローマに通じない唯一の道だ・・AS」》こう
いった行き違いの起こった理由の基本的な原因の1つであると当然いえる。
単純な対立だけと受け取るのは、誤りと思う。むしろ、デリケートだが、ある本質的違いであるところ
に、この対比の面白さがある。ウォルトンは、20世紀のオペラ音楽としてヒンデミットの「・・マティス
」とともに、ベルクの「ヴォツェック」を常に高く評価していた。また、シェーンベルクに関しても、
70年頃のインタビューで、12音主義の教義は、認めないが、作曲の大家としてのシェーンベルクを十分
評価していることをのべている。逆に、シェーンベルクは、彼の理論とどうつながるか微妙な問題をはら
むにもかかわらず、イギリス民謡が世界で最も、美しい民謡だと公言してはばからなかったし、また、
アドルノは、、シェーンベルクは 再婚をしたころから、ファッションに気を配るようになって、イギリ
ス風の服装・みだしなみにこだわっているみたいなのが、滑稽に思われたことを、敢えて書いているが、
それは、ある種の軽いイギリス紳士コンプレックスが、シェーンベルクにあったことを、指摘している
ものでもある。師匠筋の小柄なシェーンベルクよりも、長身のベルクの方が、同じく長身のウォルトン
(ノルマン風?・・出会った頃のSシットウエルの感想。)と並べた場合、容姿の上でも、耽美派的な前
者と良く出来た対称を描くのだが、「ウォルトンは、ベルクの裏返し・・」というようなことは、彼らの
作品に関しても、ある程度 面白い言い方となるのである。そんな具合に ベルクの方と比較する
発想は、十分理由のあることで、作品の別の面に、光をあてるものだが、話がそれるので、今は脇に
置かせてもらう。
ピアノ四重奏が、作曲家公認の曲として、39年・54年にレコーディングされるくらいだったのに対して、
同じようにランバートらも、評価したものだし、その内容の充実度を考えても、こちらだけが埋もれてし
まったのは、なおまだ疑問として残る。むしろ、そこには、いろんな「不運な事情」といっていいいくつ
かの大きな問題を考えねばならない。
後年のセリエリスム等に反対する立場的問題を、作曲者が取ったこととの関連は勿論あるのだが、それを
含めて考えてもそれだけじゃなく、まずそれが無調的傾向を示しているものについては、確かにそこに
特別な印象を残すのであって、それは見逃せない事でもある。(後年の本人の意識とは少し違って)
その曲が良く出来ている、もしくはかならずしもそうでもない、に関わらず初期の弦楽四重奏曲と共に、
それらは、むしろシェーンベルクの作品以上にと言った方がいい、何かしら“悪魔的ニュアンス”を伴う
印象がある。 そのことは、その本来の、また未来における価値判断とは、別にして、シェーンベルク
の無調的作品が、本質的に“近代批判”の立場から出てきたものであり、その意味で近代のパラダイムか
ら、はずれた弱者を包含するような立場であるに対して、ウォルトンのそれは、この時、単純な強者の立
場とは、ほど遠いにせよ“近代”の発想に直結したものから来ていることに重大な理由が見つけられると、
いう問題があることを述べておく。即ち その点に、意識的にならなければ、こういったニュアンスは、
普通 不必要に作品の出来の悪さと錯覚され易いという傾向を、「事情」として挙げておこう。
シェーンベルク以後のセリエリスム的なものもしくは、マスコミむけの前衛パフォーマンスは、管理さ
れた社会に さほど抵抗を生まない。初期のピアノ四重奏とこの曲を並べれば、確かに”アンファンテ
リブル”というような言葉が思い浮かぶが、トッカータのような傾向の諸作品は無調的であるとないと
に限らず、むしろ それが娯楽的でも、また単なる専門家的知識の対象として捉えて済むものでもないと
いう性格に問題がある。
それは、かってマーラーの多くの交響曲がそうとられたように、芸術らしい芸術でもないと言う性格
でもあり、(余裕と寛容を余り感じさせない生々しさ・・)そういった感じがある子供じみたものと誤
解されるものの由来の一つである。こういった作品は、明らかに陳腐であったり、ある職業的なものでも
なく 聴くものを生の現実に向かわせるが、実は人々が、最も抵抗を示すのは そのようなありのまま
の姿を示したものであるのだ。このことが法則的事実ですらあるのは、作曲者自身にしてもそのことは、
起こるということで、ある意味作曲者の本質を最も示した、トッカータのような作品に対しては、特に
振り返ると遠ざけたくなってしまう。
半世紀前と違い、世界中のさまざまなことが、手近にして見聞きできる今日、私たちが、やるべきこ
とといえば、こうした作品に対して、例えばその「音楽」であることの表面的な形にとらわれず、そ
の各部分のイメージの連続を、私たちの生活の様々な分野の事象との類似性や違いを比較して、そも
そも私たちが何を感じていたかを、より広い視点で見てみることであり、場合によっては、今まで単
に子供じみたものと考えられたことにも境界を置かないことでもある。
そういったことで、様々なかっての作品に対しても、本当の価値を新たに見せてくれるだろう。
また 結局、ある管理的なものが優先されるだけの社会による閉ざされた未来に裂け目を入れる最も
効果的な方法でもあるのだが、それは即ち世界の様相の変化ということ。そこでこういった「トッカ
ータ」のような類の音楽は自ずとさらに誇らしく蘇ってくるとは云えないだろうか?
【いちおうEND・・//2001、8月19日記述】
(注や譜例を中心に必要な部分を、付け足して議論をより解かり易く
改良していくつもりです・・・・2001年12月17日・・・・・・・)
②← 戻る →◆ HOMEへ、