:AD2
1:ヴァイオリンとピアノのためのトッカータ 2:ヴァイオリンソナタ
3:ヴァイオリンとピアノのための2つの小品 4:無伴奏チェロのためのパッサカリア
1:ヴァイオリンとピアノのためのトッカータ(1923)
”Toccta for violin and piano”
(初演1925)
● Kenneth Sillito(vl)、Hamish Milne(pf) jan1992・rec・ (CHANDOS 9291)
1947年のイ短調の弦楽四重奏と違う方の、1921年に出来た弦楽四重奏曲と同様、このトッカータ 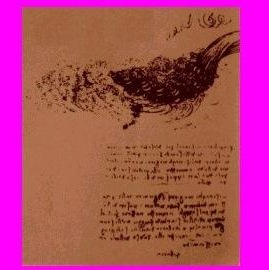 は、作曲者自身によって「削除扱い」になってしまった”不運な”初期の作品である。とはいえ、
この扱いの経過の問題を含めていろんな意味で特別興味深い作品であることは強調されて良い。
この作品は、シャンドスの全集に収められた録音が、殆どプレミアレコーディングに近いもので、
公に広く知られる初めてのものといえるみたいである。1983年に、この曲の譜面が出てきた時こ
の第1ページのみ行方不明だったそうで、その部分は1997年1月にやっと発掘されたものらしい。
1997年3月オールダムでポール・バリット(vl)キャスリン・エドワーズ(pf)で初めてそれが、
公開演奏された訳だから、このCDの演奏は、その問題部分を何らかの形で補ったか、どうかした
譜面によるわけで、残念ながら不完全なものでもあるようだ。とはいえ、vlのケネス・シリィト
は、全集の他の演奏にも見られるように鋭利なタッチとフレージングの感覚がWWにむいた人だし、
pfのミルン?も良さそうなので、「削除扱い」のこの曲が今もこうやって相当良好な演奏で聞く
ことが、現実に出来る。
兄弟的な作品の弦楽四重奏曲の方は、1923年8月のザルツブルグの第1回国際現代音楽祭・ISCM・
でも発表された以前から日本の音楽事典などにも記載のあった当の曲である。その時のザルツブ
ルグで、ヒンデミットとは仲良くなった他、実はウォルトンは、新ウィーン楽派のシェーンベル
クらにも直接 対面している。必ずしも愉快なともいえない印象のものだったため、オズバート
シットウェルらの間接的回想、と後年のウォルトン自身の回想を含め、幾つかの断片的なもので、
内容は、少し矛盾している。またシェーンベルク側からの話しもないため、全容はある程度想像
するしかない。ウォルトンは、当時イギリスでは余り知られていなかったシェーンベルクの音楽
を、以前から、先輩格のウォーロックの薦めで、学んでいた。また、アルバン・ベルクは、ウォ
ルトンを、「イギリスにおける無調音楽のリーダー的存在」と考え、演奏が 上手く行かなかっ
たのにも、かかわらずウォルトンの音楽に特に興味を持ってくれた。それでアルバンベルクは、
シェーンベルクに会うようにしてくれる。通訳の役割のL、バーナーズを伴い、近くの湖畔の場
所に対面に行った
は、作曲者自身によって「削除扱い」になってしまった”不運な”初期の作品である。とはいえ、
この扱いの経過の問題を含めていろんな意味で特別興味深い作品であることは強調されて良い。
この作品は、シャンドスの全集に収められた録音が、殆どプレミアレコーディングに近いもので、
公に広く知られる初めてのものといえるみたいである。1983年に、この曲の譜面が出てきた時こ
の第1ページのみ行方不明だったそうで、その部分は1997年1月にやっと発掘されたものらしい。
1997年3月オールダムでポール・バリット(vl)キャスリン・エドワーズ(pf)で初めてそれが、
公開演奏された訳だから、このCDの演奏は、その問題部分を何らかの形で補ったか、どうかした
譜面によるわけで、残念ながら不完全なものでもあるようだ。とはいえ、vlのケネス・シリィト
は、全集の他の演奏にも見られるように鋭利なタッチとフレージングの感覚がWWにむいた人だし、
pfのミルン?も良さそうなので、「削除扱い」のこの曲が今もこうやって相当良好な演奏で聞く
ことが、現実に出来る。
兄弟的な作品の弦楽四重奏曲の方は、1923年8月のザルツブルグの第1回国際現代音楽祭・ISCM・
でも発表された以前から日本の音楽事典などにも記載のあった当の曲である。その時のザルツブ
ルグで、ヒンデミットとは仲良くなった他、実はウォルトンは、新ウィーン楽派のシェーンベル
クらにも直接 対面している。必ずしも愉快なともいえない印象のものだったため、オズバート
シットウェルらの間接的回想、と後年のウォルトン自身の回想を含め、幾つかの断片的なもので、
内容は、少し矛盾している。またシェーンベルク側からの話しもないため、全容はある程度想像
するしかない。ウォルトンは、当時イギリスでは余り知られていなかったシェーンベルクの音楽
を、以前から、先輩格のウォーロックの薦めで、学んでいた。また、アルバン・ベルクは、ウォ
ルトンを、「イギリスにおける無調音楽のリーダー的存在」と考え、演奏が 上手く行かなかっ
たのにも、かかわらずウォルトンの音楽に特に興味を持ってくれた。それでアルバンベルクは、
シェーンベルクに会うようにしてくれる。通訳の役割のL、バーナーズを伴い、近くの湖畔の場
所に対面に行った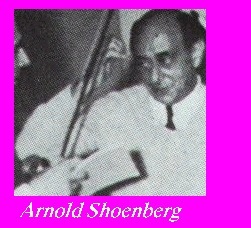 そうである。・・・・
ウォルトンらがやってくる前に、そこにあったピアノでシェーンベルクは、作曲みたいなものを
やっていて気まずい雰囲気だったようで、そして少し話をして、シェーンベルク流のピアノを使
った厳格な作曲法みたいな話題もちらつくが、ウォルトンらは、興味がわかず居心地が悪く、全
体に不愉快でもあり、ちょっとで帰る。その後戻ってみると ピアノにあった作曲に関する記号
?みたいなものも,無くなっていた・・・というような状況かもしれない ?
後年の発言のトーンと違い、ウォルトン自身がシェーンベルクは怒っていたとも言っていた時期
もあったようだが、いろんな意図もはいる事柄だから、ただ一見して帰ったというより、常識的
に考えても、短いデリケートな感じの会見であったというのが本当みたいに思われる。
当時、21歳のウォルトンは、シットウェル家の人々からもやんちゃな白面の少年扱いだったし、
対して、48歳のシェーンベルク(cfアルバンベルクは38歳)は、グレの歌の成功の後 当時彼の
一生のうち最も経済的に恵まれた時期でもあり、明らかに大家的存在で、そして当時 12音技法
の確立に頭が一杯だったはずで、またメモを持ち歩いて作曲のアイディアを書き込むのは、彼の
クセで、それを置き忘れて作曲が遅れることもあった。
前年このザルツブルグで1908年作のソプラノ付きの第2弦楽四重奏曲が、大きな好評のうちに再演さ
れていたシェーンベルクとは、むしろ、それと同時期のピアノのための3つの小品op11ぐらいの無調的な
時代の作品と並べて考えれば、SQとトッカータのウォルトンと非常に表現的なある強いアナーキーな
感じという点などから、類似性があると見るのは自然な受け取り方で、ベルクあたりの感じたことも
近いかと思われる。
ただシェーンベルクは23年当時、始めて12音技法を体系的に用いた21年の「ピアノ組曲op25」以来、
それを用いた大形式の作品を文学に頼らず、構成する方法を模索していた時代で、交響曲のような形
式を4楽章の淡々とした抽象的な試みの味わいで埋めた「木管5重奏op26」(1924年完成)という、
シェーンベルクの作品中でも最も秘経めかした規則性を目指した作品などを、作曲中でもあった。また
「和声学」の21年に増補改訂された部分で、「・・私は、音楽家で無調のものとは関わりがない。・・
色彩の関係も、無スペクトル的とか、無補色的というのが、有り得ないように、無調的という反対物は
有り得ない。・・」無調という概念を”理論的に”単なる消極的でしかないものとして否定しているし、
1925年の自作の歌詞による「3つの風刺op28」に付随させた序文で、「・・現代的であると思われたい
ために不協和音を寄せ集めるが、論理的な結論を引き出す勇気は持っていない。論理的な結論は、不協
和音より先行する協和音によって生じてくる・・、不協和音を使用しながらなぜ彼らだけにそれが許さ
れるのか説明できない人々、調性をぐらつかせても適当に完全な三和音の信仰を時々告白するエセ調性
主義者,こういうやり方では 形式、建築術への自分の郷愁を満足させることは不可能だと自ずとわか
るだろう。違ったやり方をするべきで恐らくそれは可能だ・・」と言い、また同様に~に帰れという人
々や、民族主義者なども強硬に批判される。以上のような主張から、またその当時の圧倒的なドイツ音
楽の権威を考えても、ザルツブルクでのシェーンベルクとウォルトンは相当距離があったことが、想像
される。ただシェーンベルクは、この文章で続けて、すべての主義者に反対すると言っているし、最後
に「時に才能を見せ、評価すべき他人の仕事をこのようにからかうことは私が普段していることよりは
良くはないであろう。が私は出来る限り自分をここで表現したということで、こんな風に真剣に考えざ
るを得ない私の姿は、他人にはまた別の意味で面白かろう。それが、結局この文章で私が言いたかった
ことであるのだ。」というように付け加えている。
シェーンベルクの12音技法の大規模な使用は、より発達して28年の「オーケストラの変奏曲op31」「ヴ
ァイオリン協奏曲op36(35年)」を経て、攻撃的なまでの表現力の現れを見せるが、そこを経由した後、
ほぼ最晩年の49年の「ヴァイオリンとピアノのためのファンタジーop47」に至ると、消化された12音技
法とある種の透明なロマンティシズムの復活を聴いてとる事が出来る。
一方は、限定された聴衆相手のものにせよ既に高い定評のある‘名曲’で、一方は、殆ど 今
まで世に出ていなかった若書きの曲だともいえるのだが、単純にいっても元々は共に自由な形式が選
ばれ、共に2つの楽器のために各々独立性が強く与えられたのもので、作品の長さもほぼ同じくらい
である。それだけでも、ここで「ファンタジー」と「トッカータ」をある平行的な要素で、考える
てみる事は無駄ではないと思われる。少なくも、全体的にいって木管5重奏におけるよりは作曲者の
距離は縮まっている。
「ファンタジー」について、レーボヴィッツは、「ヴァイオリンのパートを書き上げてから、その
‘事が済んだ後に’ピアノパートが、書き足されたよう(に独立的だ・・と)な作られ方をしている。」
と言っている。
一般に”ピアノ伴奏付き”というように題名に付け足されるものの、伴奏的といえば和声的展開によ
る大ざっぱな背景づけみたいな従的関係の傾向をもつものだが、優れた曲ほど対等な関係に近づく場
合が見られるし、そして、この曲のピアノパートは複雑な変化が与えられ活動的で、十二分にヴァイ
オリンと対等な存在感もある。にもかかわらず従的と言えなくもない奇妙な2面性が顕れているとこ
ろがこの曲の大きな特徴と言っていいかも知れない。
というのも、この曲の場合、伴奏とは主役に対する、存在すべての性格付けであって、ヴァイオリン
が、ある主張の進行のような、旋律的流れの全てを独立的に最後まで保つのに、ピアノは全く対比的
な断片的な不協和音の一見不連続な無時間的散らばりでほとんどVnと共有するフレーズの関係無くし
遠くした、役割りを独立的に果たす。そして このことが、対立させ、解体し合うことによる、曲の
本質と深くつながっている。
1965年10月の、メニューインとG・グールドが、この「ファンタジー」を演奏した映像を、私たちは
今、容易に見ることが出来るが、それとともに、2人が対立したような立場をとって見せた、短い議
論もそこに付け足されている。(ここの演奏は映像無しで聴いても、それ自体とても優れていること
が判るものだと思う・。2003-9/5もちろん、メニューインの方は、譜面を見ながら弾いているけど・・・)
メニューインは反シェーンベルク的意見として、点描主義に移っていったような12音音楽のようなも
のは、協和音、不協和音の関係も作れず、音の違いの変化が乏しく、休止の頻用やダイナミックの指
示が極端になり、またジェスチャー”のようなもので変化をつける他無いのでないかという疑念を、
そうである。・・・・
ウォルトンらがやってくる前に、そこにあったピアノでシェーンベルクは、作曲みたいなものを
やっていて気まずい雰囲気だったようで、そして少し話をして、シェーンベルク流のピアノを使
った厳格な作曲法みたいな話題もちらつくが、ウォルトンらは、興味がわかず居心地が悪く、全
体に不愉快でもあり、ちょっとで帰る。その後戻ってみると ピアノにあった作曲に関する記号
?みたいなものも,無くなっていた・・・というような状況かもしれない ?
後年の発言のトーンと違い、ウォルトン自身がシェーンベルクは怒っていたとも言っていた時期
もあったようだが、いろんな意図もはいる事柄だから、ただ一見して帰ったというより、常識的
に考えても、短いデリケートな感じの会見であったというのが本当みたいに思われる。
当時、21歳のウォルトンは、シットウェル家の人々からもやんちゃな白面の少年扱いだったし、
対して、48歳のシェーンベルク(cfアルバンベルクは38歳)は、グレの歌の成功の後 当時彼の
一生のうち最も経済的に恵まれた時期でもあり、明らかに大家的存在で、そして当時 12音技法
の確立に頭が一杯だったはずで、またメモを持ち歩いて作曲のアイディアを書き込むのは、彼の
クセで、それを置き忘れて作曲が遅れることもあった。
前年このザルツブルグで1908年作のソプラノ付きの第2弦楽四重奏曲が、大きな好評のうちに再演さ
れていたシェーンベルクとは、むしろ、それと同時期のピアノのための3つの小品op11ぐらいの無調的な
時代の作品と並べて考えれば、SQとトッカータのウォルトンと非常に表現的なある強いアナーキーな
感じという点などから、類似性があると見るのは自然な受け取り方で、ベルクあたりの感じたことも
近いかと思われる。
ただシェーンベルクは23年当時、始めて12音技法を体系的に用いた21年の「ピアノ組曲op25」以来、
それを用いた大形式の作品を文学に頼らず、構成する方法を模索していた時代で、交響曲のような形
式を4楽章の淡々とした抽象的な試みの味わいで埋めた「木管5重奏op26」(1924年完成)という、
シェーンベルクの作品中でも最も秘経めかした規則性を目指した作品などを、作曲中でもあった。また
「和声学」の21年に増補改訂された部分で、「・・私は、音楽家で無調のものとは関わりがない。・・
色彩の関係も、無スペクトル的とか、無補色的というのが、有り得ないように、無調的という反対物は
有り得ない。・・」無調という概念を”理論的に”単なる消極的でしかないものとして否定しているし、
1925年の自作の歌詞による「3つの風刺op28」に付随させた序文で、「・・現代的であると思われたい
ために不協和音を寄せ集めるが、論理的な結論を引き出す勇気は持っていない。論理的な結論は、不協
和音より先行する協和音によって生じてくる・・、不協和音を使用しながらなぜ彼らだけにそれが許さ
れるのか説明できない人々、調性をぐらつかせても適当に完全な三和音の信仰を時々告白するエセ調性
主義者,こういうやり方では 形式、建築術への自分の郷愁を満足させることは不可能だと自ずとわか
るだろう。違ったやり方をするべきで恐らくそれは可能だ・・」と言い、また同様に~に帰れという人
々や、民族主義者なども強硬に批判される。以上のような主張から、またその当時の圧倒的なドイツ音
楽の権威を考えても、ザルツブルクでのシェーンベルクとウォルトンは相当距離があったことが、想像
される。ただシェーンベルクは、この文章で続けて、すべての主義者に反対すると言っているし、最後
に「時に才能を見せ、評価すべき他人の仕事をこのようにからかうことは私が普段していることよりは
良くはないであろう。が私は出来る限り自分をここで表現したということで、こんな風に真剣に考えざ
るを得ない私の姿は、他人にはまた別の意味で面白かろう。それが、結局この文章で私が言いたかった
ことであるのだ。」というように付け加えている。
シェーンベルクの12音技法の大規模な使用は、より発達して28年の「オーケストラの変奏曲op31」「ヴ
ァイオリン協奏曲op36(35年)」を経て、攻撃的なまでの表現力の現れを見せるが、そこを経由した後、
ほぼ最晩年の49年の「ヴァイオリンとピアノのためのファンタジーop47」に至ると、消化された12音技
法とある種の透明なロマンティシズムの復活を聴いてとる事が出来る。
一方は、限定された聴衆相手のものにせよ既に高い定評のある‘名曲’で、一方は、殆ど 今
まで世に出ていなかった若書きの曲だともいえるのだが、単純にいっても元々は共に自由な形式が選
ばれ、共に2つの楽器のために各々独立性が強く与えられたのもので、作品の長さもほぼ同じくらい
である。それだけでも、ここで「ファンタジー」と「トッカータ」をある平行的な要素で、考える
てみる事は無駄ではないと思われる。少なくも、全体的にいって木管5重奏におけるよりは作曲者の
距離は縮まっている。
「ファンタジー」について、レーボヴィッツは、「ヴァイオリンのパートを書き上げてから、その
‘事が済んだ後に’ピアノパートが、書き足されたよう(に独立的だ・・と)な作られ方をしている。」
と言っている。
一般に”ピアノ伴奏付き”というように題名に付け足されるものの、伴奏的といえば和声的展開によ
る大ざっぱな背景づけみたいな従的関係の傾向をもつものだが、優れた曲ほど対等な関係に近づく場
合が見られるし、そして、この曲のピアノパートは複雑な変化が与えられ活動的で、十二分にヴァイ
オリンと対等な存在感もある。にもかかわらず従的と言えなくもない奇妙な2面性が顕れているとこ
ろがこの曲の大きな特徴と言っていいかも知れない。
というのも、この曲の場合、伴奏とは主役に対する、存在すべての性格付けであって、ヴァイオリン
が、ある主張の進行のような、旋律的流れの全てを独立的に最後まで保つのに、ピアノは全く対比的
な断片的な不協和音の一見不連続な無時間的散らばりでほとんどVnと共有するフレーズの関係無くし
遠くした、役割りを独立的に果たす。そして このことが、対立させ、解体し合うことによる、曲の
本質と深くつながっている。
1965年10月の、メニューインとG・グールドが、この「ファンタジー」を演奏した映像を、私たちは
今、容易に見ることが出来るが、それとともに、2人が対立したような立場をとって見せた、短い議
論もそこに付け足されている。(ここの演奏は映像無しで聴いても、それ自体とても優れていること
が判るものだと思う・。2003-9/5もちろん、メニューインの方は、譜面を見ながら弾いているけど・・・)
メニューインは反シェーンベルク的意見として、点描主義に移っていったような12音音楽のようなも
のは、協和音、不協和音の関係も作れず、音の違いの変化が乏しく、休止の頻用やダイナミックの指
示が極端になり、またジェスチャー”のようなもので変化をつける他無いのでないかという疑念を、 語る。
これは、確かにこの曲の構成を見ても、ある面 的を射た発想と思う。レイボィッツの分析を元に、
全体を区分すると、①出だしの第1主題とそれに続く部分②短く第1主題が出た後から、対比的な
柔らかく始まる第2主題の部分③第2主題から派生したレシタチーボ的おしゃべり部分④第2主題
の展開的な表出部分⑤急に気分を転じて悪ふざけ的な横やり風のスケルツオ⑥そこから、メノモッ
ソや経過的部分のあと続いて、第1主題が出て、第2主題に関係した部分と絡んでコーダ。
レイボイッツは、この曲全体を、交響曲的な4つの楽章に割り振って、ソナタ形式的な各部分が、同
時に、4楽章の関係にもあるというややこしい解釈をしている。けれど、第1主題部分が1楽章で第
2主題的部分の楽章が別々でソナタの形式にある、というのも弁証法的思考を考えれば、不自然だし
むしろ、12音音楽ではちゃんとしたソナタの展開部を作るより、ジェスチュアー的にもはっきり違い
が判りやすい、レシタティーボ、やスケルッツオ的部分を中間部分として作った方が無理がない感じ
になるということで、その後、省略された再現部を置いた形とも解釈できる。ただレイボイッツが、
そういった風に言いたがった(多少、大袈裟に)のも、理由があって、曲の時間的長さの割に、盛ら
れた感情が、重いという事情である。(もちろんシェーンベルクが1楽章形式にこだわったのは、理
由がありそのことは、この曲の構成にも関係があるがひとまず置いておく・・・)
決断の意志的な第1主題、静かな気分から信念に発展していくような第2主題、皮肉なワルツを経て
レシタチーボの会話が、④の部分で一旦結論的な信念の表明になるが、また覆されてスケルツオの悪
魔と戦い、出発の決意の第1主題や基本的テーマが出てくるが、なおも掻き乱され断ち切られるよう
に終わるという流れ。
そもそも、シェーンベルクの12音技法が、物神崇拝的な音楽情緒に対して、非偶像崇拝的な戒律を、
求めるものだと考える時、(作曲者自身のテクストによるモーゼとアロンのテーマが正にそれだ・・)
この曲の展開は、無調の砂漠を彷徨い、飽くなき悪魔との戦いを続けるユダヤ教のラヴィの姿そのも
のに思えてくる。
実際、メニューインとの、この会話の中でグールドも、この曲には旧約聖書的なパッセージに満ちて
いると答えている。メニューインが、ジェスチュアーというコトバを、使ったのは、この種の音楽が、
ちょうどハムレットの亡霊シーンやラヴシーンを、元々知っていれば セリフが音節でバラバラにさ
れていても、どんなシーンか判る いわば、パントマイムを理解するような意味で、ジェスチャーの
音楽と彼は言っている訳で、また主として批判、ネガティヴな意図を込めている。シェークスピアの
肝心の言葉が無くなってしまっているという、のは、その後の「象徴は世の中に溢れています。が、
長調と短調のようなものは、それだけで愉しいとか、悲しいとか(笑い)伝わるものがあるわけです
ね・・」という話しとつながっている。すなわち、この種の無調的音楽には、長調や短調にある肝心
なものがない、言葉の意味のないシェークスピアのようであるという話しみたいだが、この類似した
考えのしばしばある主張は、そのまま受け入れるわけにはいかない。無調的音楽は、単純に調が無い
といえるものでは本当はないこと。(全ての音楽は何らかの調が存在する・・とシェーンベルク自身言
っている)確かにある程度の単調さを、反語的に受け入れることによって失う物は、あったが同時に
得る物がある場合も存在すること。そしてまず何より、調性音楽といわれているものが、その学習の
され方、捉えられ方が、常に偏見と思い込みによって、受け入れられており、それがそこに付帯する
“自然な感情”があるようにもなる。モードなどとの関係は本当は不明なままで、自然で本来的であ
るとするのは、歪められた視点で、こういった問題が 結局 そのやや不当に誇張されているシェー
クスピアのジェスチャーという比喩にもつながってくる。
しかし、上記のことを踏まえた上で、メニューインのこの元々ネガティヴな言い方を考えた場合、反
面、この「ファンタジー」に関しては、やはり、ある重要な特徴を語ることにもなる。特に、ファン
タジーのピアノの部分のフレーズは、他のソロのピアノ作品 特に、作品11の3つの小品などのいろ
んな部分のアイディアを、そのまま 引き継いでいて、ただ そのような破壊的なエネルギー原理?
による単純な秩序でなく、それをモザイクのようにバラバラにしてより把握できる多層的な「形」に
置き直している。それは、動機的構成術を、フルに使いこなすやり方のピアノのパートの元々の題材
の可能性を尽くしたような書法、勿論 調性を感じさせる要素を体系的に除去しようとしていく12音
技法の元来の発想の発展であるのだが、この場合 線的なバイオリンの流れと無時間的なそのピアノ
のパートへ分解され、また1つの作品に再構成するということにもなり「晩年的な」シェーンベルク
の発想の典型の一つが顕れていると云うことも出来る。シェークスピアの分解というような、ある面
誇張した言い方でなく、この場合 事実に即して言えば、表現主義的な作品の要素をモザイク的に分
解して、先に挙げた形式論理も持ちつつ、再構成しているといった方が、誤解がない。こう見るなら、
かっての表現主義的作品に対して、この場合 失ったものはさほどではなく、一方 得た物は大きい
という意味で、バラバラにする操作とジェスチャー的な傾向は、むしろ全く積極的な特徴とされるべ
きことになる。心の広いメニューインは、最後に「既成概念を疑うのは良いことです」と結ぶ・・・
【この章の第2ページに続く。→② //2001、8月19日記述】
語る。
これは、確かにこの曲の構成を見ても、ある面 的を射た発想と思う。レイボィッツの分析を元に、
全体を区分すると、①出だしの第1主題とそれに続く部分②短く第1主題が出た後から、対比的な
柔らかく始まる第2主題の部分③第2主題から派生したレシタチーボ的おしゃべり部分④第2主題
の展開的な表出部分⑤急に気分を転じて悪ふざけ的な横やり風のスケルツオ⑥そこから、メノモッ
ソや経過的部分のあと続いて、第1主題が出て、第2主題に関係した部分と絡んでコーダ。
レイボイッツは、この曲全体を、交響曲的な4つの楽章に割り振って、ソナタ形式的な各部分が、同
時に、4楽章の関係にもあるというややこしい解釈をしている。けれど、第1主題部分が1楽章で第
2主題的部分の楽章が別々でソナタの形式にある、というのも弁証法的思考を考えれば、不自然だし
むしろ、12音音楽ではちゃんとしたソナタの展開部を作るより、ジェスチュアー的にもはっきり違い
が判りやすい、レシタティーボ、やスケルッツオ的部分を中間部分として作った方が無理がない感じ
になるということで、その後、省略された再現部を置いた形とも解釈できる。ただレイボイッツが、
そういった風に言いたがった(多少、大袈裟に)のも、理由があって、曲の時間的長さの割に、盛ら
れた感情が、重いという事情である。(もちろんシェーンベルクが1楽章形式にこだわったのは、理
由がありそのことは、この曲の構成にも関係があるがひとまず置いておく・・・)
決断の意志的な第1主題、静かな気分から信念に発展していくような第2主題、皮肉なワルツを経て
レシタチーボの会話が、④の部分で一旦結論的な信念の表明になるが、また覆されてスケルツオの悪
魔と戦い、出発の決意の第1主題や基本的テーマが出てくるが、なおも掻き乱され断ち切られるよう
に終わるという流れ。
そもそも、シェーンベルクの12音技法が、物神崇拝的な音楽情緒に対して、非偶像崇拝的な戒律を、
求めるものだと考える時、(作曲者自身のテクストによるモーゼとアロンのテーマが正にそれだ・・)
この曲の展開は、無調の砂漠を彷徨い、飽くなき悪魔との戦いを続けるユダヤ教のラヴィの姿そのも
のに思えてくる。
実際、メニューインとの、この会話の中でグールドも、この曲には旧約聖書的なパッセージに満ちて
いると答えている。メニューインが、ジェスチュアーというコトバを、使ったのは、この種の音楽が、
ちょうどハムレットの亡霊シーンやラヴシーンを、元々知っていれば セリフが音節でバラバラにさ
れていても、どんなシーンか判る いわば、パントマイムを理解するような意味で、ジェスチャーの
音楽と彼は言っている訳で、また主として批判、ネガティヴな意図を込めている。シェークスピアの
肝心の言葉が無くなってしまっているという、のは、その後の「象徴は世の中に溢れています。が、
長調と短調のようなものは、それだけで愉しいとか、悲しいとか(笑い)伝わるものがあるわけです
ね・・」という話しとつながっている。すなわち、この種の無調的音楽には、長調や短調にある肝心
なものがない、言葉の意味のないシェークスピアのようであるという話しみたいだが、この類似した
考えのしばしばある主張は、そのまま受け入れるわけにはいかない。無調的音楽は、単純に調が無い
といえるものでは本当はないこと。(全ての音楽は何らかの調が存在する・・とシェーンベルク自身言
っている)確かにある程度の単調さを、反語的に受け入れることによって失う物は、あったが同時に
得る物がある場合も存在すること。そしてまず何より、調性音楽といわれているものが、その学習の
され方、捉えられ方が、常に偏見と思い込みによって、受け入れられており、それがそこに付帯する
“自然な感情”があるようにもなる。モードなどとの関係は本当は不明なままで、自然で本来的であ
るとするのは、歪められた視点で、こういった問題が 結局 そのやや不当に誇張されているシェー
クスピアのジェスチャーという比喩にもつながってくる。
しかし、上記のことを踏まえた上で、メニューインのこの元々ネガティヴな言い方を考えた場合、反
面、この「ファンタジー」に関しては、やはり、ある重要な特徴を語ることにもなる。特に、ファン
タジーのピアノの部分のフレーズは、他のソロのピアノ作品 特に、作品11の3つの小品などのいろ
んな部分のアイディアを、そのまま 引き継いでいて、ただ そのような破壊的なエネルギー原理?
による単純な秩序でなく、それをモザイクのようにバラバラにしてより把握できる多層的な「形」に
置き直している。それは、動機的構成術を、フルに使いこなすやり方のピアノのパートの元々の題材
の可能性を尽くしたような書法、勿論 調性を感じさせる要素を体系的に除去しようとしていく12音
技法の元来の発想の発展であるのだが、この場合 線的なバイオリンの流れと無時間的なそのピアノ
のパートへ分解され、また1つの作品に再構成するということにもなり「晩年的な」シェーンベルク
の発想の典型の一つが顕れていると云うことも出来る。シェークスピアの分解というような、ある面
誇張した言い方でなく、この場合 事実に即して言えば、表現主義的な作品の要素をモザイク的に分
解して、先に挙げた形式論理も持ちつつ、再構成しているといった方が、誤解がない。こう見るなら、
かっての表現主義的作品に対して、この場合 失ったものはさほどではなく、一方 得た物は大きい
という意味で、バラバラにする操作とジェスチャー的な傾向は、むしろ全く積極的な特徴とされるべ
きことになる。心の広いメニューインは、最後に「既成概念を疑うのは良いことです」と結ぶ・・・
【この章の第2ページに続く。→② //2001、8月19日記述】


◆ memo:この演奏は、Bモンサンジョンの編集でLD化された「グレングールドコレクション1/2」
のうち、1の中に収録されていて以前から見ることが出来たもので、最近ではNHK・BS2で、
1の方がすべて放送されていたから(9月頃から3週にわたって)さらに目にした人も
多いでしょう。本来Vn奏者でグールドの生前からの友人だったモンサンジョンのおかげで、
こういった映像を手近に見ることができるようになったとも云えるが、反面 CBCの番組など
の断片的な演奏部分をピックアップして編集したのがこのコレクションなので、元の番組の
全体の流れで演奏なども聴いた方が、本来の意図に沿うものだとも思うが・・・
【この注2001、12月14日記述】
は、作曲者自身によって「削除扱い」になってしまった”不運な”初期の作品である。とはいえ、 この扱いの経過の問題を含めていろんな意味で特別興味深い作品であることは強調されて良い。 この作品は、シャンドスの全集に収められた録音が、殆どプレミアレコーディングに近いもので、 公に広く知られる初めてのものといえるみたいである。1983年に、この曲の譜面が出てきた時こ の第1ページのみ行方不明だったそうで、その部分は1997年1月にやっと発掘されたものらしい。 1997年3月オールダムでポール・バリット(vl)キャスリン・エドワーズ(pf)で初めてそれが、 公開演奏された訳だから、このCDの演奏は、その問題部分を何らかの形で補ったか、どうかした 譜面によるわけで、残念ながら不完全なものでもあるようだ。とはいえ、vlのケネス・シリィト は、全集の他の演奏にも見られるように鋭利なタッチとフレージングの感覚がWWにむいた人だし、 pfのミルン?も良さそうなので、「削除扱い」のこの曲が今もこうやって相当良好な演奏で聞く ことが、現実に出来る。 兄弟的な作品の弦楽四重奏曲の方は、1923年8月のザルツブルグの第1回国際現代音楽祭・ISCM・ でも発表された以前から日本の音楽事典などにも記載のあった当の曲である。その時のザルツブ ルグで、ヒンデミットとは仲良くなった他、実はウォルトンは、新ウィーン楽派のシェーンベル クらにも直接 対面している。必ずしも愉快なともいえない印象のものだったため、オズバート シットウェルらの間接的回想、と後年のウォルトン自身の回想を含め、幾つかの断片的なもので、 内容は、少し矛盾している。またシェーンベルク側からの話しもないため、全容はある程度想像 するしかない。ウォルトンは、当時イギリスでは余り知られていなかったシェーンベルクの音楽 を、以前から、先輩格のウォーロックの薦めで、学んでいた。また、アルバン・ベルクは、ウォ ルトンを、「イギリスにおける無調音楽のリーダー的存在」と考え、演奏が 上手く行かなかっ たのにも、かかわらずウォルトンの音楽に特に興味を持ってくれた。それでアルバンベルクは、 シェーンベルクに会うようにしてくれる。通訳の役割のL、バーナーズを伴い、近くの湖畔の場 所に対面に行った
そうである。・・・・ ウォルトンらがやってくる前に、そこにあったピアノでシェーンベルクは、作曲みたいなものを やっていて気まずい雰囲気だったようで、そして少し話をして、シェーンベルク流のピアノを使 った厳格な作曲法みたいな話題もちらつくが、ウォルトンらは、興味がわかず居心地が悪く、全 体に不愉快でもあり、ちょっとで帰る。その後戻ってみると ピアノにあった作曲に関する記号 ?みたいなものも,無くなっていた・・・というような状況かもしれない ? 後年の発言のトーンと違い、ウォルトン自身がシェーンベルクは怒っていたとも言っていた時期 もあったようだが、いろんな意図もはいる事柄だから、ただ一見して帰ったというより、常識的 に考えても、短いデリケートな感じの会見であったというのが本当みたいに思われる。 当時、21歳のウォルトンは、シットウェル家の人々からもやんちゃな白面の少年扱いだったし、 対して、48歳のシェーンベルク(cfアルバンベルクは38歳)は、グレの歌の成功の後 当時彼の 一生のうち最も経済的に恵まれた時期でもあり、明らかに大家的存在で、そして当時 12音技法 の確立に頭が一杯だったはずで、またメモを持ち歩いて作曲のアイディアを書き込むのは、彼の クセで、それを置き忘れて作曲が遅れることもあった。 前年このザルツブルグで1908年作のソプラノ付きの第2弦楽四重奏曲が、大きな好評のうちに再演さ れていたシェーンベルクとは、むしろ、それと同時期のピアノのための3つの小品op11ぐらいの無調的な 時代の作品と並べて考えれば、SQとトッカータのウォルトンと非常に表現的なある強いアナーキーな 感じという点などから、類似性があると見るのは自然な受け取り方で、ベルクあたりの感じたことも 近いかと思われる。 ただシェーンベルクは23年当時、始めて12音技法を体系的に用いた21年の「ピアノ組曲op25」以来、 それを用いた大形式の作品を文学に頼らず、構成する方法を模索していた時代で、交響曲のような形 式を4楽章の淡々とした抽象的な試みの味わいで埋めた「木管5重奏op26」(1924年完成)という、 シェーンベルクの作品中でも最も秘経めかした規則性を目指した作品などを、作曲中でもあった。また 「和声学」の21年に増補改訂された部分で、「・・私は、音楽家で無調のものとは関わりがない。・・ 色彩の関係も、無スペクトル的とか、無補色的というのが、有り得ないように、無調的という反対物は 有り得ない。・・」無調という概念を”理論的に”単なる消極的でしかないものとして否定しているし、 1925年の自作の歌詞による「3つの風刺op28」に付随させた序文で、「・・現代的であると思われたい ために不協和音を寄せ集めるが、論理的な結論を引き出す勇気は持っていない。論理的な結論は、不協 和音より先行する協和音によって生じてくる・・、不協和音を使用しながらなぜ彼らだけにそれが許さ れるのか説明できない人々、調性をぐらつかせても適当に完全な三和音の信仰を時々告白するエセ調性 主義者,こういうやり方では 形式、建築術への自分の郷愁を満足させることは不可能だと自ずとわか るだろう。違ったやり方をするべきで恐らくそれは可能だ・・」と言い、また同様に~に帰れという人 々や、民族主義者なども強硬に批判される。以上のような主張から、またその当時の圧倒的なドイツ音 楽の権威を考えても、ザルツブルクでのシェーンベルクとウォルトンは相当距離があったことが、想像 される。ただシェーンベルクは、この文章で続けて、すべての主義者に反対すると言っているし、最後 に「時に才能を見せ、評価すべき他人の仕事をこのようにからかうことは私が普段していることよりは 良くはないであろう。が私は出来る限り自分をここで表現したということで、こんな風に真剣に考えざ るを得ない私の姿は、他人にはまた別の意味で面白かろう。それが、結局この文章で私が言いたかった ことであるのだ。」というように付け加えている。 シェーンベルクの12音技法の大規模な使用は、より発達して28年の「オーケストラの変奏曲op31」「ヴ ァイオリン協奏曲op36(35年)」を経て、攻撃的なまでの表現力の現れを見せるが、そこを経由した後、 ほぼ最晩年の49年の「ヴァイオリンとピアノのためのファンタジーop47」に至ると、消化された12音技 法とある種の透明なロマンティシズムの復活を聴いてとる事が出来る。 一方は、限定された聴衆相手のものにせよ既に高い定評のある‘名曲’で、一方は、殆ど 今 まで世に出ていなかった若書きの曲だともいえるのだが、単純にいっても元々は共に自由な形式が選 ばれ、共に2つの楽器のために各々独立性が強く与えられたのもので、作品の長さもほぼ同じくらい である。それだけでも、ここで「ファンタジー」と「トッカータ」をある平行的な要素で、考える てみる事は無駄ではないと思われる。少なくも、全体的にいって木管5重奏におけるよりは作曲者の 距離は縮まっている。 「ファンタジー」について、レーボヴィッツは、「ヴァイオリンのパートを書き上げてから、その ‘事が済んだ後に’ピアノパートが、書き足されたよう(に独立的だ・・と)な作られ方をしている。」 と言っている。 一般に”ピアノ伴奏付き”というように題名に付け足されるものの、伴奏的といえば和声的展開によ る大ざっぱな背景づけみたいな従的関係の傾向をもつものだが、優れた曲ほど対等な関係に近づく場 合が見られるし、そして、この曲のピアノパートは複雑な変化が与えられ活動的で、十二分にヴァイ オリンと対等な存在感もある。にもかかわらず従的と言えなくもない奇妙な2面性が顕れているとこ ろがこの曲の大きな特徴と言っていいかも知れない。 というのも、この曲の場合、伴奏とは主役に対する、存在すべての性格付けであって、ヴァイオリン が、ある主張の進行のような、旋律的流れの全てを独立的に最後まで保つのに、ピアノは全く対比的 な断片的な不協和音の一見不連続な無時間的散らばりでほとんどVnと共有するフレーズの関係無くし 遠くした、役割りを独立的に果たす。そして このことが、対立させ、解体し合うことによる、曲の 本質と深くつながっている。 1965年10月の、メニューインとG・グールドが、この「ファンタジー」を演奏した映像を、私たちは 今、容易に見ることが出来るが、それとともに、2人が対立したような立場をとって見せた、短い議 論もそこに付け足されている。(ここの演奏は映像無しで聴いても、それ自体とても優れていること が判るものだと思う・。2003-9/5もちろん、メニューインの方は、譜面を見ながら弾いているけど・・・) メニューインは反シェーンベルク的意見として、点描主義に移っていったような12音音楽のようなも のは、協和音、不協和音の関係も作れず、音の違いの変化が乏しく、休止の頻用やダイナミックの指 示が極端になり、またジェスチャー”のようなもので変化をつける他無いのでないかという疑念を、
語る。 これは、確かにこの曲の構成を見ても、ある面 的を射た発想と思う。レイボィッツの分析を元に、 全体を区分すると、①出だしの第1主題とそれに続く部分②短く第1主題が出た後から、対比的な 柔らかく始まる第2主題の部分③第2主題から派生したレシタチーボ的おしゃべり部分④第2主題 の展開的な表出部分⑤急に気分を転じて悪ふざけ的な横やり風のスケルツオ⑥そこから、メノモッ ソや経過的部分のあと続いて、第1主題が出て、第2主題に関係した部分と絡んでコーダ。 レイボイッツは、この曲全体を、交響曲的な4つの楽章に割り振って、ソナタ形式的な各部分が、同 時に、4楽章の関係にもあるというややこしい解釈をしている。けれど、第1主題部分が1楽章で第 2主題的部分の楽章が別々でソナタの形式にある、というのも弁証法的思考を考えれば、不自然だし むしろ、12音音楽ではちゃんとしたソナタの展開部を作るより、ジェスチュアー的にもはっきり違い が判りやすい、レシタティーボ、やスケルッツオ的部分を中間部分として作った方が無理がない感じ になるということで、その後、省略された再現部を置いた形とも解釈できる。ただレイボイッツが、 そういった風に言いたがった(多少、大袈裟に)のも、理由があって、曲の時間的長さの割に、盛ら れた感情が、重いという事情である。(もちろんシェーンベルクが1楽章形式にこだわったのは、理 由がありそのことは、この曲の構成にも関係があるがひとまず置いておく・・・) 決断の意志的な第1主題、静かな気分から信念に発展していくような第2主題、皮肉なワルツを経て レシタチーボの会話が、④の部分で一旦結論的な信念の表明になるが、また覆されてスケルツオの悪 魔と戦い、出発の決意の第1主題や基本的テーマが出てくるが、なおも掻き乱され断ち切られるよう に終わるという流れ。 そもそも、シェーンベルクの12音技法が、物神崇拝的な音楽情緒に対して、非偶像崇拝的な戒律を、 求めるものだと考える時、(作曲者自身のテクストによるモーゼとアロンのテーマが正にそれだ・・) この曲の展開は、無調の砂漠を彷徨い、飽くなき悪魔との戦いを続けるユダヤ教のラヴィの姿そのも のに思えてくる。 実際、メニューインとの、この会話の中でグールドも、この曲には旧約聖書的なパッセージに満ちて いると答えている。メニューインが、ジェスチュアーというコトバを、使ったのは、この種の音楽が、 ちょうどハムレットの亡霊シーンやラヴシーンを、元々知っていれば セリフが音節でバラバラにさ れていても、どんなシーンか判る いわば、パントマイムを理解するような意味で、ジェスチャーの 音楽と彼は言っている訳で、また主として批判、ネガティヴな意図を込めている。シェークスピアの 肝心の言葉が無くなってしまっているという、のは、その後の「象徴は世の中に溢れています。が、 長調と短調のようなものは、それだけで愉しいとか、悲しいとか(笑い)伝わるものがあるわけです ね・・」という話しとつながっている。すなわち、この種の無調的音楽には、長調や短調にある肝心 なものがない、言葉の意味のないシェークスピアのようであるという話しみたいだが、この類似した 考えのしばしばある主張は、そのまま受け入れるわけにはいかない。無調的音楽は、単純に調が無い といえるものでは本当はないこと。(全ての音楽は何らかの調が存在する・・とシェーンベルク自身言 っている)確かにある程度の単調さを、反語的に受け入れることによって失う物は、あったが同時に 得る物がある場合も存在すること。そしてまず何より、調性音楽といわれているものが、その学習の され方、捉えられ方が、常に偏見と思い込みによって、受け入れられており、それがそこに付帯する “自然な感情”があるようにもなる。モードなどとの関係は本当は不明なままで、自然で本来的であ るとするのは、歪められた視点で、こういった問題が 結局 そのやや不当に誇張されているシェー クスピアのジェスチャーという比喩にもつながってくる。 しかし、上記のことを踏まえた上で、メニューインのこの元々ネガティヴな言い方を考えた場合、反 面、この「ファンタジー」に関しては、やはり、ある重要な特徴を語ることにもなる。特に、ファン タジーのピアノの部分のフレーズは、他のソロのピアノ作品 特に、作品11の3つの小品などのいろ んな部分のアイディアを、そのまま 引き継いでいて、ただ そのような破壊的なエネルギー原理? による単純な秩序でなく、それをモザイクのようにバラバラにしてより把握できる多層的な「形」に 置き直している。それは、動機的構成術を、フルに使いこなすやり方のピアノのパートの元々の題材 の可能性を尽くしたような書法、勿論 調性を感じさせる要素を体系的に除去しようとしていく12音 技法の元来の発想の発展であるのだが、この場合 線的なバイオリンの流れと無時間的なそのピアノ のパートへ分解され、また1つの作品に再構成するということにもなり「晩年的な」シェーンベルク の発想の典型の一つが顕れていると云うことも出来る。シェークスピアの分解というような、ある面 誇張した言い方でなく、この場合 事実に即して言えば、表現主義的な作品の要素をモザイク的に分 解して、先に挙げた形式論理も持ちつつ、再構成しているといった方が、誤解がない。こう見るなら、 かっての表現主義的作品に対して、この場合 失ったものはさほどではなく、一方 得た物は大きい という意味で、バラバラにする操作とジェスチャー的な傾向は、むしろ全く積極的な特徴とされるべ きことになる。心の広いメニューインは、最後に「既成概念を疑うのは良いことです」と結ぶ・・・ 【この章の第2ページに続く。→② //2001、8月19日記述】

