自転車は前へ進むものなのにバックミラーがついている。
仏像の眼は前の方を見ているが、半分は静かに自分の心の中を見つめておられる。
ところが、私たちはとかくお金や名誉を追い求め、自分の外側だけを見つめ、他人の目を気にしながら、ただあくせくと働いている。
「迷う」という字は人間が米を食べて走っている形であると言った人がいたが、なるほどと考えさせられる。
米を食べて一体、どこへ行こうとしているのであろうか。
あなたはどこから来たのですか?、あなたはどこへ行くのですか?、あなたはなんですか?と、いつも言っていた芸術家を思い出す。
人生はよく旅にたとえられるが、進んでいく方向が大切だと思う。
日本からハワイへ行くのなら、ハワイ行きの飛行機に乗らねばならない。
まちがえてロシアやアメリカの方へ進んだら、時間がたつほど目的地よリ遠くへ離れていってまう。
ある老人が、「歳をとったことが情けないのではない。むなしく過ぎた人生がやりきれないのだ」と言っていたが、そろそろ人生のたそがれを迎えようとする私には、決して他人事だとは思えない。
私は教職にあった頃、入学式や始業式などに「始めに終わリを思うことが大切だ。悔いを残さぬように一日一日を燃えて生きてほしい」と、生徒たちに教え諭してきた。
しかし、私自身、この60年間いったい何をしてきたのか、と尋ねられても、胸を張って答えられるものは何もない。
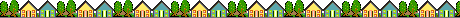
小説家山本有三はその作品の中で、「たった一度しかない人生、たったひとりしかない自分を生かしきれなかったら、人間に生まれてきた甲斐がないじゃないか」と、述べている。
子供の頃、人間は死ぬと、怖いエンマさまの前に連れて行かれ、「お前は娑婆で一体何をしてきたか」と、厳しく問いただされ、ウソを言うと舌を抜かれる、こいう話を聞かされた。
作家の大仏次郎は、「私が死んでエンマさまの前に立たされたら、何も言うことはないのだが、ただ一つ、幼少の頃から便所を出るとき、次に人る人のために草履をきちんとそろえてきた。これだけは胸を張って言える」と、雑誌に書いていた。
親鸞さまのご和讃に、『本願力にあひぬれば、むなしくすぐるひとぞなき・・・・』という歌がある。
毎日欲にふりまわされ、思うようにならぬと腹をたて、愚痴を言う。
急がなくてもよいことを急ぎ、争わなくてもよいような、つまらぬことを争っている。
こんな生活を何年間、何十年間繰リ返しても、結局は、むなしさだけしか残らないのではなかろうか。
貧農のこせがれから関白太政大臣にまで昇進して、立身出世の代名詞のように言われている豊臣秀吉でも、
「露と落ち露と散りにし我が身かな
なにはのことも夢のまた夢」
という辞世の歌を残している。
ある大学教授が、
「2階へものを取りに上がって何をとりにきたのか忘れてしまうことがある。
途中でふと思い出すことがあるが、そのときはうれしい。
からだが先に出てきてしまったのである。
その用事は何であったのか思い出せぬまま、ぼくはすごすごあの世ヘ戻る。」
という詩を書いている。
出生の本懐を忘れて、すごすご戻るようなとがあってはならない。
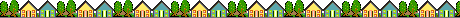
では、どうすればよいのだろうか。
私が私だと思っているその奥深いところに、平素は気付きにくいが、実はもうひとりのすばらしい自己がいる。
その私に出会い、この真の私の声を、心の耳で聞いて生きることが大切なのである。
石川啄木の歌に、
「旅に出たき夫の心
叱り泣く妻子の心
朝の食卓」
というのがある。
芸術の道を追求し、よりよい作品を作るために啄木は旅に出ようとする。
家計の苦しかった妻は、夫のわがままと思い反対し、ロ論となる。
楽しかるベき朝の食卓が、子供も巻き込んで修羅場となった。
ところが、同じ啄木の歌に、
「友みなが我よりえらくみゆる日よ
花を買ひきて妻と親しむ」
という有名なのがある。
久しぶリにクラス会に出席してみると、級友の多くはりっぱに成長し、堂々としている。
学生時代、学業成績では誰にも負けなかった啄木は、相変わらずの貧乏暮しであった。
強い劣等感を抱いて帰宅する途中、花屋の前を通った。
妻は花が大好きだったことを思い出し、一輪買って帰り、活けてもらって二人で楽しい一時を過ごしたというのである。
また、日本で初めて倫理学という学問を確立した和辻哲朗博士の父親の葬儀の折りの様子をもう一つ記してみよう。
和辻博士の父は田舎の村長も務めた名士であった。
土地の習慣で、葬儀の参列者はみな火葬場まで足を運びお参りしたが、葬主の博士は、参列者一人一人に、「生前はお世話になりました」と、ていねいに挨拶しなければならなかった。
東大の名誉教授で、文化勲章も授賞している大学者が、名もない農民の一人一人に頭を下げることに初めはたいヘん抵抗があった。
お辞儀をくり返しているうちに自分の考え違いに気付き、心から深々と頭が下がったという。
自分の今日あるのは、ひとえに周囲の人々のおかげであったと気付かされたのであった。
石川啄木も和辻哲朗も、おれがおれがとうぬぼれ、自我中心に生きてきたが、ほんとうは妻のおかげ、村人たらがあったればこそと両手を合わせ、ほんとうの自己・もうひとりの私の世界に転じることによって、真の幸せを感ずることができたわけである。
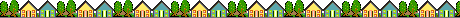
人間はみな、得することが好きで損は嫌いである。
楽を求め苦を嫌がる。
そして、自分と自分の家族の幸せばかリを追い求めている。
税金は他人に払ってほしいし、福祉は自分が受けたいと、虫のいいことばかり考えがちである。
しかし、エゴの塊である自分の心の奥深いところに、意味のあることなら喜んで苦労したい、つらくても、たとえ損をしても人々のために奉仕したいという、ピカッと光ったすばらしい自己がいる。
この真実の自己に出会い、このもうひとりの私の願いに生きるとき、人間は真の生きがいを感ずるようになるのである。
念仏というのは、この“もうひとりの私”を思い出すことであり、もうひとりの私にめざめた心が信心であり、もうひとりの私にめざめさせてくれる働きが本願なのである。
何かと忙しい毎日であるが、自分の心の中に奥ゆかしい床の間を設け、そこに“もうひとりの私”と書いた掛軸を掛け、真実の私の声を心の耳で聞きながら、浄土への旅を続けたいものである。
(元.門前高校長)
|
 山
元 哲 朗
山
元 哲 朗 山
元 哲 朗
山
元 哲 朗