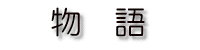
1988 (c) 斎藤毬雄(Holly)
「二台のホンダ」
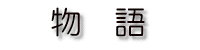
「二台のホンダ」
春間もない三月のある日の朝、太陽がこんにちはする前に俺は目覚めた。ベッドを離れガウンをはおり、カーテンを開ける。昨日の雨がうそのように、雲一つない。窓を開けると、冷たい風が入ってきた。だがそれは、実にすがすがしい風だった。首都高は、車もまばらで、長距離のトラックが爆音を立ててカッ飛んでいるだけだ。ふと、遠くの東京タワーに目を移すと、同時に、イルミネイションが消えた。窓を閉めて、隣の部屋に移り、ソファーに腰掛けダンヒルに火をつける。卓上デジタルが6時を示す。同時に、CDがonになる。ライオネルリッチーが静かに流れる。ダンヒルをもみ消し、仕度をすませる。カチッ、キュルキュル、ヒューン。セル一発、俺のホンダが目覚める。暖気を終え、チョークを戻すと、ホンダはストンと回転を落とし、静かにアイドリングを続ける。
R20を西へ向かう。調布の友人が、このあたりはよくマッポが出没すると言っていた。スロットルをもどし、車の流れに乗る。小一時間もたっただろうか、俺とホンダは、大垂水峠にさしかかった。VFR750のサスとGT201はよくねばる。軽くリーンウィズで流した。そうこうするうちに、最初の目的地、相模湖に着いた。平日の朝、駐車場はガラガラ。二輪用のスペースに、VTが休んでいる。スッとその横に俺のホンダを止めた。このクォーターのライダーも今着いたらしい。ラパイドを脱ぎかけて、俺のホンダに目を奪われたらしく、手が、顎ヒモにかかったきりだ。赤地に胸にVラインの入ったツナギだ。ボディラインからして女性か。幸先のいいツーリングのスタートになりそうだ。ホンダレディは、やっとラバイドを脱いだ。俺も、黒のV3を脱ぐ。
「やあ。」
「どうも。」
これが、俺と陽子の最初の会話だった。
「一人で?」
「うん。」
「へぇ、どこから。」
「東京。」
「俺も一人なんだ。どう、どうせだから、そこら一緒に。」
「そうね。」
俺と陽子は、雪が残る湖岸を、ブラブラ歩いた。
「VTはいつから?」
「一年前。」
「じゃあ、モデルチェンジしてすぐ買ったの?」
「そう、詳しいね。」
「一応ね。」
「君のほうは?」
「あたしもそのくらいかな。でもまだ中免だし、あのホンダが初代バイクなの。」
「なんか飲もうか。」
「そうね。」
とは言っても店はまだ開いておらず、俺達は、自販機の缶入りコーヒーで、冷えきった身体を暖めた。ちかくのベンチに腰をおろし、ダンヒルに火をつける。
「で、今からどこまで?」
「俺は長野の方まで行くんだけど。」
「そう!あたしも。」
ふと、陽子の目が輝いた。
「じゃあ、途中まで一緒に行こうか。」
「ええ。」
クールを装いながらも口元は微笑を浮かべていた。まだ背伸びしている年頃なんだな、と俺はそのとき悟った。
グローブをはめラパイドを被る。
「乗ってみるか?」
と、俺は俺のホンダを指差した。
「いいの?」
「ここだけね。」
「わあ!」
その時こぼした素直な笑顔。それが、陽子が俺に見せたはじめたの笑顔だった。
俺がその気になった理由は彼女のホンダをじっくり見たからである。立ちゴケの痕はない。左側にバンクのさせすぎでこけた痕があるだけ。 タイヤも均等に擦り減っている。そして何よりもバイク自体が良く手入れされていてキレイだ。陽子自身に劣らぬくらいに・・・。
陽子はゆっくりとサイドをはらい、セルを回す。ミッションを一段踏み込む。2、3度空吹かしをして半クラをキープしてスタート。初めて乗るナナハンに少々力が入っているようだ。だがそれも数分もしないうちにとれた。俺の思った通り、200kg余りの車体を軽々とまではいかないものの、それなりに乗りこなしている。アクセルワークが良いのだ。Uターンも難無くこなす。大型を持っていないのが不思議なくらいだ。10分もしただろうか、VTの横で、陽子はVFのサイドをゆっくりかけた。俺と目を遭わせるなり
「すごいわ、やっぱりナナハンは。」
高ぶる気持ちを静めながらの一言である。
「そう、喜んでもらえたかな。」
「ふふっ、あたし陽子、斎藤陽子っていうの。よろしくね。」
「おれ、松本瞬。よろしく。」
二台のホンダは、また、R20を西へむかった・・・。
深夜の高速湾岸線、リミッターと戦いながらZRを転がす。助手席で眠る女が一人、奈美子である。音大に通う彼女は、海が好きだ。この日も、九十九里を見たいと言う彼女の言うがまま、犬吠までZRを駆けた。夕方、家を出た僕たちを待っていたものは、車の群れであった。
「だから言っただろう。平日の夕方なんてこれなんだから。」
「だって・・・。」
「日が暮れるぞ。もどるか?」
「いいの、夜の海も、またいいわ。」
「ああ、そうかもしれないな。」
− − − 二年前、僕がZRを買って、鬼のようにドライブばかりしていた頃のことである。いろは坂を攻めに行き、帰路についてしばらくすると、前方に親指を立てて腕を出している少女が見えた。
「ヒッチハイクかな。乗せてやるか。」
ZRは、静かに歩道に沿って止まった。助手席のロックをはずし、リアハッチを開ける。
「荷物、後ろに積んで。」
「はい。」
うむ、はっきり言って、かわいい。ラッキーだこれは。
「ひとり?」
「はい。」
「どこまで?」
「東京までなんですけど。」
「運がいいね君、この車、今から東京まで一直線。」
「わあ本当ですかあ。」
「マジ、だって俺、家が世田谷だから。」
「あたし練馬なんです。」
うむ、これはナイスとしか言い様がない。小説みたいな話だ。
「日光へはずっとヒッチハイクで?」
「いえ、東武で。」
「えっ、じゃあ、なんで。」
「財布、落っことしちゃって。」
「それは災難だったね。」
「そうなんです。それでその後の予定がパーになっちゃって。」
「予定って言うと?」
「一泊二日で日光を見物しようとしてたんです。ところが財布落としたときはもう銀行も閉まってて、おまけに明日は日曜だし。」
「へえ、それじゃ、帰るにも帰りたくないんじゃない?本当は。」
「ええ、実は・・・。」
「良かったら、僕が案内してあげようか、日光を。」
「えっ、でも・・・。」
「ははは、心配しなさんな。君みたいな、かわいい女の子と知り合いになれたお礼さ。」
「まあっ。」
「その代わり費用はそっち持ちだよ。いいね。貸しとくからさ。」
「はい。どうもありがとうございます。」
ミッションをローに入れる。スロットルを開ける。なぜか、RB20DETも軽快だ。僕らは日光市内へ今日の宿を探しに向かった。
次の日、二人と一台は日光、奥日光の名所を巡り、すっかり打ち解けて、帰路についた。
「楽しかったね。」
「うん、すっごく。また来たいわ。あなたと。」
「いいよ。いつでも。」
R4を小山まで来たところである。奈美子がぽつりとつぶやいた。
「海が見たい。」
「えっ。」
「九十九里なら行けるでしょ。」
「そりゃまあ。でも遅くなっちゃうよ。」
「いいの。」
そう言われて、僕はR16を左に折れた。R16からR126に入りR126から堀川浜へ出た。誰もいない秋の夕暮れの浜辺は、どことなくセンチメンタルだ。助手席のロックが外れた。二人は波打ちぎわまで歩き、静かに白波を見つめていた。奈美子のその白波を見つめる瞳は、どこか悲しげだった。うつむき加減に彼女はぽつりとつぶやいた。
「あたしね・・・、失恋したの・・・。」
彼女の瞳に光るものがあった。僕は何も答えなかった。ただ、彼女のその細い肩をそっと抱き寄せてやった。
「ふふふふっ。」と、由貴は笑った。どうもこれが癖らしい。
「何がおかしいの。」
と、僕が聞く。朝日がテーブルを照らし、グラスの影がきらめき、揺れている。
「だって、ふふ。」
と、また笑う。妙な女だと僕は思った。
「ほら。」
と、由貴は僕の顔を指した。
「ほっぺた。」
と言われて、僕は左手を左の頬にあてた。
「ああ。」
顔に一粒の炭水化物の塊、つまり御飯がついていたのだ。
「そうならそうと、早く言えよなあ。」
僕は少しふくれた。
「ふふふふっ。」
と、また由貴は笑った。
− − − もうすぐ春とは言っても夜はまだ寒い。僕は厚着をしてホンダにまたがった。あてのないミニツーリングだ。僕は環七を北へ向かった。十二時とは言え、東京のそれも環七では交通量は多い。でもそのうちすくだろうと思いつつタクシーと競り合う。さすがに一時を過ぎれば車の流れは、疎らになる。シグナルグランプリで、車の一団を抜け出せば、そこから先の道は僕だけのもの。誰もいない幹線道路を飛ばす快感は、一度味わった者にしかわからない。
僕は環七からR17を左に折れた。暫くすると大きな橋に出る。荒川にかかる戸田橋である。橋の真中の歩道にホンダを休ませる。メットを脱ぎミラーに掛ける。ホンダに腰掛け深く一呼吸する。心地よい疲労感が全身を駆け抜ける。この快感はバイクでしか得られないものだ。ポケットからキャメルを取り出す。満天の星を見つめながら、ジッポーに火を付ける。ふと、感謝の意を込めてホンダに目をやる。そして、キャメルに火を付ける。深く一服吸い深呼吸。ニコチンが全身に回る。高ぶっていた神経が安らぎを覚える。この快感はスモーカーにしか絶対にわからない。埼玉の星は綺麗だ。でも何故か絵にならないのは確かだった。今度の休日に信州へ行こうとその時僕は心に誓った。
キャメルを揉み消し、ホンダの眠りを覚ます。再び気分を引き締めアクセルを開く。歩道から、一気にUターン。一路東京へ。
R17から環七へ入る。側道から本線に入る時、追い越し車線を走るヤマハが目に映った。メットの後ろから、長い髪が靡いている。ヤマハの後ろに付いて走る。品川ナンバーだ。どこまで行くのだろう。家に帰る途中だろうか。ならば、城南エリアまで行くはずだ。ホンダとヤマハは、暫く抜きつ抜かれつ深夜の環七を並走した。
三つめの信号に二台とも捕まった。停止線にホンダとヤマハが並んだ。アライとショウエイのシールドが開く。水銀燈に照らされてショウエイの中のパッチリした二重の瞳が浮かんだ。心なしか微笑んでいるように見える。シグナルが変わるまで二人は見詰め合った。二つのシールドが閉まる。ヤマハが先にスタートした。ホンダが後を追う。排気量は三倍。ホンダはヤマハの前に出た。ホンダがアクセルを緩める。ヤマハはホンダの右に並ぶ。彼女は左手を差し伸べた。二つ先のシグナルがイエローになった。ヤマハがアクセルを絞る。ホンダは軽く右足を踏み込む。ヤマハは回転を合わせてミッションを落とす。なかなかやるな。手を繋いだまま、ホンダとヤマハは止まった。再びシールドが開く。
「やるじゃん。」
と僕が言う。
「まあね。」
と彼女が言う。これが僕と由貴の最初の会話だった。繋いだ手を解きながら僕が言った。
「どこまで?」
「世田谷。」
と彼女が言った。二人は両手をエンジンに持っていく。
「寒いね。」
「そうね。」
シグナルがグリーンになった。
世田谷の標識が目に入った。不思議と信号に捕まらない。駒留陸橋を過ぎると、二台は側道に入った。上馬の交差点の信号は赤だった。停止線の三百メートル手前で僕は右を指した。彼女は左を指した。ホンダとヤマハは二台とも右折のレーンに入って止まった。
「ふふふふっ。」
ショウエイのシールド越しに、その声は聞こえた。
ホームページへ